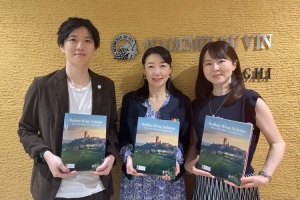一次試験を突破した皆さん、おめでとうございます。しかし忘れてはいけないのは、ソムリエ呼称を受験される皆さんは三次試験が控えているということです。三次試験のサービス実技と論述は、いわば総合力のテスト。なかでも論述試験は10月頭に、試飲試験とセットで行われるため、試飲だけでなく、論述の準備が必要になります。
合格率は比較的高いといわれますが、「油断」や「準備不足」で惜しくも不合格になってしまうケースもあります。ここでは、本番で力を出し切るための論述対策について、最終チェックポイントを整理します。
【目次】
1. 論述の位置づけと出題傾向
2. 合格者の共通点は「普段からの準備」
3. 本番を想定した書き方のポイント
4. 頻出テーマ別 準備リスト
5. 毎日200文字書こう
6. 講師からの応援メッセージ
7. 準備は自信につながる
1. 論述の位置づけと出題傾向
論述は200文字前後の短文作文が中心です。テーマは幅広く、ワインの基礎知識や料理とのペアリング、接客時の対応、時事的な話題まで出題されます。過去には次のような問題が出ました。
- 「赤ワインを冷やして飲みたいお客様に料理を提案してください」
- 「オレンジワインについて説明してください」
- 「サステイナブルな取り組みの事例を挙げて説明してください」
- 「小売価格1万円相当のワインにクレームがあった場合の対応」
いずれも、飲食店で働いていたら、現場でお客様から聞かれそうな内容で、サービス中に即答できる力が試されます。

2. 合格者の共通点は「普段からの準備」
論述で評価されるのは、知識量だけではありません。短時間でまとめる力、そして接客の現場を意識した文章力が求められます。合格者に共通するのは、次のような習慣です。
- 白紙にしない粘り強さ。「わからなくても何か書く」姿勢
- ワインの特徴を3ワードで表す能力(例:ソーヴィニヨン・ブラン=柑橘・ハーブ・爽快)
- 料理提案では「素材+ソース+付け合わせ」にも触れる
- 主要国・主要品種の特徴は即答できるように暗記
- 機関誌や業界ニュースから時事ネタを収集
こうした準備は、一夜漬けでは身につきません。普段の練習で繰り返すことが重要です。
3. 本番を想定した書き方のポイント
試験では時間配分が重要です。問題を見た瞬間に5秒で骨子を作り、残りの時間で一気に書き切ります。構成の型を身につけると、安定して書けるようになります。
特に料理に関する問題は定番で、ほぼ毎年出題されています。書き方に関してもコツがあり、これまでソムリエ協会主催の勉強会や機関誌でも紹介されてきました。下記は、その要約バージョンです。フォーマットを押さえて書いて高得点を狙いましょう。
例:「ワイン〇〇に合う料理を提案してください」
- ワインの特徴を述べる(3ワードを意識して手短に紹介)
- 料理を提案し、その特徴を述べる(素材・ソース・付け合わせまで)
- 合う理由
ポイントはただ料理を提案するのではなく、必ずどうしてそのワインと料理が合うのかを述べることです。
4. 頻出テーマ別 準備リスト
以下はよく見かける出題パターンのため、試験までに、文章化してストックしておくと安心です
1. 料理提案系
主要国の代表的品種のスタイル確認。ワインを軽めの白、重めの白、軽めの赤、重めの赤の4スタイルにわけてペアリング案を3パターン用意
2. 時事・制度系
GI(地理的表示)、サステイナブル、オーガニック、缶ワイン、Sober curios(ソバ―キュリアス)、Zebra striping(ゼブラ ストライピング)
3. お客様対応系
クレーム対応、シュチュエーションごとワイン提案など
4. ワインの種類説明
オレンジワイン、ロゼの醸造法、ペットナットなど
5. 毎日200文字書こう

合格者が口をそろえて言うのが「書く練習の量が合否を分ける」ということです。過去問や想定問題を1日1問、ストップウォッチで計りながら5分以内に200文字程度で書く習慣をつけましょう。書き終えたら模範解答と比較し、表現や構成を見直します。
香りや味わい、調理法の語彙を増やすことも大切です。「爽やか」だけでなく「レモングラスのような香り」「ミネラル感を伴う塩味」など、表現の幅を持たせると加点につながります。
「自分でリズムを作るのが苦手」という人は、アカデミー・デュ・ヴァンでも論述に特化した論述試験対策クラスが開講されるので、そういったものを利用するのも良いでしょう。
6. 講師からの応援メッセージ
アカデミー・デュ・ヴァンの講師陣からも、受験生への温かいメッセージが届いています。
 伊田明弘講師
伊田明弘講師
「論述試験ではワインの知識やトレンド、実際の接客やワイン提案を言葉で表現します。好きなワインの事なら文章を書くのもきっと楽しいはず。コツコツとワイン日記を書くつもりで毎日取り組んでみましょう。担当講師一同でサポートします!」
 林麻由美講師
林麻由美講師
「本番で迷わないのは、日々の迷いと向き合い、答えを探す練習を積んだ人だけ。今の1問が未来を変える力になります。小さな努力を重ねた先に、自信と合格が待っています。」
 メイス謙講師
メイス謙講師
「三次試験は、あなたの知識と感性を形にする場。これまでの経験を信じ、必ず何かを書くようにしてください。心から応援しています。」
 紫貴あき講師
紫貴あき講師
「年々難しくなっている三次試験、合格のヒケツは“準備力”。毎日、書く練習をしましょう。時間を計って、実際に手を動かすことで自分の弱点も見えてきます。悩むより行動ーー今日から早速はじめましょう。」
たくさんの受講生を合格に導いた講師陣の言葉ですから、勇気をもらえますね。
7. 準備は自信につながる
3次試験は知識、現場力、時間管理の総合勝負です。短文構成の型を身につけ、頻出テーマを押さえておくことが合格への近道となります。本番では「白紙にしない」「接客目線で書く」「時間内に書き切る」を徹底しましょう。早い段階から、コツコツと準備を重ねれば、当日の自信につながります。
あなたがこれまで積み上げてきた努力は、必ず文章にも現れます。最後の壁を乗り越え、晴れてソムリエとしての一歩を踏み出しましょう!