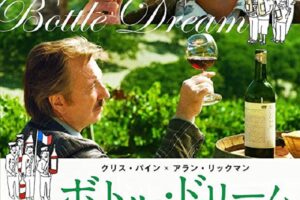ワインは毎年、秋が来れば仕込まれる。偉大と称されるワインは皆、ブドウが摘まれ、酵母の力で酒に変わった年――ヴィンテージをラベルに記している(シャンパーニュなどで一部例外はあるが)。好天続きで、労せずして優品が量産されたような年もあれば、雨、霜、雹、熱波といった天候イベントによって、造り手が唇を噛んだ年もある。ただ、どれひとつとして同じ年はなく、優れたワインはどこの地域の産であれ、ヴィンテージの個性が刻印されている。
本連載では、第二次世界大戦が終わった年から現在に至るまでのヴィンテージを、世相や文化とともに、ひとつずつ解説していく。ワイン産地の解説としては、フランスの二大銘醸地であるボルドー、ブルゴーニュを中心とするが、折にふれて他国、他産地の状況も紹介していく。
本記事では、1952年を取上げよう。ヨーロッパにおける作柄は、総じて良好ながらも、かなりのムラがあった。そんな年に、イベリア半島の閉ざされた国では、酒精強化の伝統産地でひっそり突然変異が起きていた。
【目次】
1. 1952年はどんな年だったか?
● 世界の出来事
● 日本の出来事
● カルチャー(本、映画など)
2. 1952年にはどんなワインが造られたか?
● ボルドーワインの1952年ヴィンテージ
● ブルゴーニュワインの1952年ヴィンテージ
● その他の産地
● 伝説のワインは生まれたか
3. 1952年ヴィンテージのまとめ
1. 1952年はどんな年だったか?
世界の出来事
世界は相変わらず穏やかではなかった。この年には、米ソ冷戦がもう一段階、ステップを上ったのだ。核開発の進展による、「恐怖の均衡」時代への突入である。1952年11月、アメリカ合衆国は原爆よりも数段破壊力が大きい、水素爆弾の実験に成功する。また、イギリスも米国の技術援助のもとで核実験に成功し、米ソに続く核兵器保有国となった。地球滅亡と同義な「核による全面戦争」への恐怖のもと、米ソは直接の軍事対決を避けつつ、秘密工作やプロパガンダといったイデオロギー戦争に注力するようになる。一方で、米ソによる代理戦争の場と化した朝鮮半島では、1952年になっても休戦交渉が難航を続いていて、武力衝突は止まなかった。北朝鮮、韓国の後ろ盾となったソ連、アメリカはともに、振り上げた拳を下ろせなくなっていたのだ。

1952年11月1日米国は人類初の水爆実験であるアイビー作戦を行なった
水爆実験から3日後の11月4日、アメリカ国民は共和党のドワイト・アイゼンハワーを、第34代大統領に選んだ。アイゼンハワーの当選は、戦後の米国政治における重要な転換点となる。「核の大量保有による抑止力強化」へと舵を切ったのが、この政治家だったのだ。アイゼンハワーは後年、「ドミノ理論」(ある一国が共産主義化すると、ドミノ倒しのように周辺諸国へ波及するという主張)に依拠し、ベトナム戦争へと米国を突入させた大統領でもある。
フランスはこの年、欧州防衛共同体(EDC)構想をめぐって揺れた。2年前のNATO理事会において、西ドイツの再軍備を、アメリカが提起したのを根元とする問題だ。他のNATO加盟国が米国の提案に賛成する中、フランスは唯一反対し、同年EDCを対案として出した。NATOと同じく、各国軍の連合体である「汎ヨーロッパ防衛軍」が、協力して東側に対峙するというスキームなのだが、西ドイツの軍のみ自立的な指揮権を持たないとしている。「長年の宿敵ドイツ」と軍事的に手を結ぶか否かで、フランスの世論は二分され、内政が停滞し、外交にも負の影響が出た。最終的には、1954年のフランス国民議会でEDC条約は批准されず、この構想は消滅している。1955年のパリ協定で、西ドイツの再軍備は承認された。
フランスが、「軍事大国ドイツ」という過去の亡霊と戦っていたとき、仏独国境の東側では、分かれたドイツをひとつにする試みがなされていた。1952年3月、「スターリン・ノート」と呼ばれる外交文書を通じ、東西ドイツの再統一と中立化が、ソ連から西側へ持ちかけられたのだ。しかし、西側諸国はこの提案を、結束への妨害と捉えて拒否する。交渉決裂を受けて、ソ連の指導者スターリンは東ドイツの社会主義統一党(SED)に全権を付与し、独裁体制が確立された。工業は国有化され、農業では集団農場が奨励されるなど、ソ連と同様の国体となっていく。東ドイツのワイン産業も、中央計画経済の制約下に置かれ、停滞を余儀なくされた。
欧州の西側諸国による協調的発展が軌道に乗りつつある中で、イベリア半島の二国(スペイン、ポルトガル)は、いずれも独裁政治体制のもと、国際的に孤立していた。フランコ首相が治めるスペインでは、自給自足的経済政策「アウタルキー」が採られていたが、うまく機能せず、国民は困窮の中にあった。1952年には食料配給制が廃止されたものの、貿易赤字が累積し、ワインを含む産物の輸出は振るわなかった。ポルトガルも、アントニオ・サラザール首相による独裁体制「エスタド・ノヴォ」(1933~1974年)のまっただ中で、ナショナリズムとカトリシズムを土台とする、保守的な統治が行なわれていた。エスタド・ノヴォの語は「新しい国家」を意味するが、その中身はアジアやアフリカの植民地を永続させようとする、時代遅れの体制であった。

ヨーロッパ最長の独裁政権「エスタド・ノヴォ」を敷いたポルトガルの首相、アントニオ・サラザール(1968年頃)
日本の出来事
前年に締結されたサンフランシスコ平和条約が、1952年4月28日に発効し、同日にGHQも廃止された。日米安保条約も同時に発効したのに加え、この日には中華民国(台湾)とのあいだに、日華平和条約が締結された(発効は同年8月5日)。中華人民共和国(中国)という、ソ連に次ぐ共産主義大国の成立(1949年)および、朝鮮戦争(1950~1953年)というアジア情勢に対応した、反共同盟の一環として結ばれた条約である。アメリカの占領から解放され、主権を回復した日本は、そのまま西側陣営へと正式に組み込まれた。台湾や韓国といった資本主義国とともに、東アジアで共産主義勢力に対峙するという、今日まで続く構図が出来上がったのがこの年である。
国内政治では、自衛隊創設に向けた議論が始まっている。前身である警察予備隊は、朝鮮戦争が勃発した1950年、国内治安強化を目的にマッカーサー元帥の命で誕生していた。これが1952年10月、保安庁の新設に伴い「保安隊」に改組される。先立つ同年の3月、吉田茂首相は参議院において、「自衛のための戦力は違憲ではない」と答弁した。防衛庁が設置され、自衛隊が発足したのはその2年後だ。東アジアの軍事的緊張が高まり、アメリカが日本の再軍備を求めるようになったのが、その背景にはあった。共産主義勢力への警戒は、日本国内にも向けられており、同年7月には破壊活動防止法が成立・施行されている(当時は、日本共産党が武装闘争を行なっていた)。

保安隊の「特車」。実態は戦車以外の何物でもないが、憲法第9条との関係から曖昧な呼称が採られていた
経済面では、朝鮮戦争による特需がまだ続いており、国民の暮らしは上を向いていた。この年、東京や地方に多数の民間放送局が開局され、ラジオが無料の娯楽として急速に普及しはじめる(1951年にラジオの民間放送が始まるまで、ラジオ受信機所持は政府による許可制で、聴取料を支払う必要もあった)。
大きな震災が、この年にはあった。3月4日の十勝沖地震で、津波などにより死者が28名、行方不明者が5名、建物の被害が8973棟発生した。十勝沖は、マグニチュード8クラスの大地震が周期的に起きる地域で、2003年にも再び大きな災害が発生している。
1952年の社会面に載った出来事としては、青梅事件、木造地区警察署襲撃事件、菅生事件、吹田事件、枚方事件など、日本共産党や新左翼、在日朝鮮人らが公安・警察と対立した事案が目立つ。東西冷戦激化の、反映と見られるだろう。
皇室関係のニュースとしては、皇太子明仁親王(平成天皇、現上皇)の成年式および立太子の礼が、皇居仮宮殿で行われた。儀式に参加した吉田茂首相は、奉答文で自らを「臣茂」と呼んだのだが、これが激しい批判にさらされる。「戦前の、天皇と臣民の関係性を想起させる」というのが、その理由だった。「象徴としての天皇」という新しい概念は、まだ浸透しきっていなかった。
カルチャー(本、映画など)
芥川賞の受賞作は、五味康祐の『喪神』 と、松本清張の『或る「小倉日記」伝』の二作。五味は新しい剣豪小説の名手になり、オーディオ評論家としても高名になった。松本は以降、『点と線』、『砂の器』、『黒革の手帖』など、社会派ミステリーの傑作を発表し続け、国民的作家となる。直木賞の受賞作は、藤原審爾の『罪な女』他と、立野信之の『叛乱』である。1952年の日本におけるベストセラー1位は、安田徳太郎による『人間の歴史』だった。医師である著者が、独自の視点で書いた一般人向けの歴史書で、全6巻の合計で販売数は100万部を超えた。この年に出版された、重要な日本文学をもうひとつ挙げると、大岡昇平の『野火』になるだろう。フィリピン戦線での著者の体験を下敷きにした作品で、極限状況での人肉食というタブーに切り込んだ。
海外文学に目を向けると、1952年にアメリカで一番売れたのは、戦争小説の『ケイン号の反乱』であった(刊行は前年)。著者のハーマン・ウォークは、本作でピューリッツァー賞を受賞している。2年後には、ハンフリー・ボガード主演で映画化もされた。このほか、ジョン・スタインベックによる壮大な家族の物語、『エデンの東』も1952年の刊行で、年末にはベストセラーになっている。同作も3年後に映画化され、ジェームズ・ディーンが初主演、出世作となった。スタインベックも、過去に『怒りの葡萄』でピューリッツァー賞を受賞しており、後年にはノーベル文学賞も授かっている。
1952年のノーベル文学賞の受賞者は、フランスの作家フランソワ・モーリアック(1855-1970)だ。代表作は、『テレーズ・デスケルー』、『愛の砂漠』など。仏で最も権威のある文学賞、アカデミー・フランセーズ賞をも1926年に受賞している国民的作家で、ボルドー地方出身の著名人としても知られる。第一次大戦に従軍したうえ、第二次大戦中は対独レジスタンス運動に参加、手記を地下出版した闘士だ。戦前は反ファシスト主義者の立場で言論を展開し、戦後は急進的カトリック保守主義者として、共産主義に立ち向かった。

ジョン・スタインベック著 『エデンの東』 初版本の表紙
日本映画については、映画雑誌『キネマ旬報』が年間第1位に選んだのが、黒澤明監督の『生きる』だった。黒澤は前年に、『羅生門』がヴェネツィアで金獅子賞を穫ったばかりで、脂が乗り、ヒット作を連発し始めた時期である。『生きる』も海外で高い評価を受け、1954年のベルリン国際映画祭において、ベルリン市政府特別賞を受けた。『生きる』は、市役所の課長が主人公という地味な設定ながら、ヒューマニズムを深く掘り下げた傑作に仕上がっている。
アメリカ映画の世界はどうだったか。この年のアカデミー賞作品賞を受けたのは、ヴィンセント・ミネリ監督のミュージカル映画、『巴里のアメリカ人』である(公開は前年の1951年)。作品賞だけでなく、美術賞、撮影賞など、合計7部門の受賞になった。主演を務めた俳優・歌手のジーン・ケリーは、1952年公開のミュージカル映画の大傑作、 『雨に唄えば』でも主演および監督をしている。この年のハリウッドにおける、マン・オブ・ザ・イヤーだと文句なしに言えるだろう。両作品とも、後年に舞台化された。

映画 『雨に唄えば』 のポスター
ヨーロッパの国際映画祭の筆頭であるカンヌではこの年、グランプリが2作品出た。オーソン・ウェルズ監督・主演の『オセロ』(シェイクスピアの同名戯曲の映画化/公開は前年)と、イタリア人監督レナート・カステラーニの『2ペンスの希望』(1952年公開)である。ウェルズの『オセロ』は、母国アメリカではなぜか評価されず、配給元が見つかるまで3年以上かかった。ヴェネツィア国際映画祭で最高の作品に贈られる金獅子賞は、前年公開のルネ・クレマン監督によるフランス映画、 『禁じられた遊び』 である。この年のヴェネツィアでは、溝口健二監督の『西鶴一代女』が国際賞を受賞しており、前年の黒澤に続く快挙とされた。第2回のベルリン国際映画祭は、部門別の表彰を取りやめて、全ジャンルからひとつ最高の映画を選ぶ形へと変わった。スウェーデン人監督アルネ・マットソンによる、『春の悶え』が、この年の金熊賞に輝いた(公開は前年)。
西洋音楽の世界では1952年、一里塚となった重要な作品が発表される。アメリカ人の前衛作曲家ジョン・ケージによる、『4分33秒』だ。楽譜に記されているのは、曲名である演奏時間のみ。会場で、演奏者は一切音を出さない。聴衆はその場に立会い、単なる偶然によって生じるノイズをただ聞くという、究極の実験作である。いわゆる「クラシック/古典」の音楽が、第一次大戦の頃から現代化、先鋭化していった果てが、ケージによる「沈黙という音」だった。
ファイン・アートとしての音楽がここまで尖ってくると、一般人はもう付いていけない。ポピュラー音楽が、アメリカで広がり始める。ジャズやロックが爆発するまでは、あと少しだ。1952年のビルボード年間チャートで最高位に輝いたのは、インストゥルメンタル曲の『ブルー・タンゴ』。軽快な管弦楽曲を得意とする作曲家ルロイ・アンダーソンの作品で、かつての「わかりやすかったクラシック」を、手軽に大衆化させた趣きの音楽だ。
1952年に生を受けた著名人について、手短に紹介しよう。政治の世界では、東京都知事の小池百合子、ロシア連邦大統領ウラジミール・プーチンなど。スポーツ界では、野球選手の小林繁、体操選手のニコライ・アンドリアノフ、F1ドライバーのネルソン・ピケら。映画界では井筒和幸、ロバート・ゼメキス、ガス・ヴァン・サントら、文学界では村上龍、漫画界では秋本治、音楽の分野では坂本龍一、中島みゆき、さだまさし、浜田省吾、ゲイリー・ムーア、ジョー・ストラマー、デヴィッド・バーンら。俳優では、沖雅也、水谷豊、草刈正雄、松坂慶子、スティーヴン・セガール、ロビン・ウィリアムズ、ミッキー・ロークら。ファッション界ではジャン・ポール・ゴルチェが、ゲーム界では宮本茂が、それぞれこの年の生まれである。
死没者としては、イギリス国王ジョージ6世、幼児教育法の開発で知られるマリア・モンテッソーリ、アメリカ・プラグマティズムを代表する哲学者ジョン・デューイ、アフリカ系アメリカ人として初めてオスカーを受賞した俳優ハティ・マクダニエル、トヨタ自動車の創業者(第2代社長)の豊田喜一郎などがいる。
2. 1952年にはどんなワインが造られたか?
ボルドーワインの1952年ヴィンテージ
悪い年ではなかったが、エリアやシャトーによってバラツキがあった。イギリス市場にワインが届いたとき、商人たちは「寝かせておくべき」ヴィンテージだと喧伝したそうだが、すべてがそうではなかったようだ。古酒の神様マイケル・ブロードベントの採点は、赤に対する評価が「二つ星から四つ星」と、幅をもたせてある(満点は五つ星)。甘口白については三つ星で、悪くはない。ボルドーのヴィンテージに関する大著を書いたニール・マーティンも、1952に対して比較的好意的だ。「過小評価されている年で、手を出すべきでない銘柄は多いものの、注意深く調べれば見るべきワインも少なくない」と、記している。
1月から3月までの気温は低く、成熟期間のスタートが遅くなった。4月の終わりから気温が上がり、5月後半からの開花と結実はまずまずうまく運ぶ。6月の気温は高く、ブドウ樹の生育は進んだが、6月17日に雹が降り、ソーテルヌで大きな被害が出た。8月5日には、左岸のサン・テステフとリストラックにも雹が降っている。とはいえ、8月終わりまでの夏、気温はずっと高めで推移し、時折ブドウ樹を潤す雨が降るという好ましい展開だった。しかし、摘み取りが始まった9月に天候は崩れ、雨が降って冷え込んだ。カビが広がるまでにと収穫をと急いだため、シャトーによっては未熟な風味の赤ワインしか出来なかった。エリア別だと、メドックが厳しく、グラーヴと右岸はより好ましかった(摘み取り時期の早いメルロのほうが、秋雨の被害に遭わなかったため)。甘口白もこの年、摘み取り開始が早かった。

ブルゴーニュワインの1952年ヴィンテージ
品質はかなり良い年だが、量は少ない。ボルドー赤と同じく、ブルゴーニュでも赤白問わず、骨格のしっかりした長期熟成型のワインが生まれている。。発売当時、赤はタンニンが強すぎると評されたが、歳月とともによいバランスになった。しかし、悲惨な天候だった前年(1951)の影響で、この年のブドウ樹は、わずかな果実しか実らせていない。ブロードベントの評価は、赤白ともに四つ星である。ブルゴーニュのヴィンテージに関する大著を書いたアレン・メドウズも、同じく四つ星の評価だ。
春先から好天が続いた。花の数ははじめから少なかったものの、結実はスムーズに進んだ。夏の気温はずっと高く、雨もよいタイミングと量で降ってくれたので、ブドウは健全な状態でよく熟した。果皮が分厚く、果汁が少なく、凝縮したワインが生まれそうだった。しかし、収穫前の9月になると冷え込み、雨もかなり降ったため、偉大と呼べる水準にはあと一歩届かないヴィンテージになった。シャブリ地区では7月3日に雹が降り、一級畑で被害が出た。

その他の産地
ローヌ渓谷は、南北ともに素晴らしい年になり、特に南部が優れていた。こちらでも、堅牢で長い寿命の赤ワインが生まれている。ロワール渓谷も悪くない年で、ヴーヴレ、ボヌゾーといった地区の甘口白が、高く評価された。アルザスも同じく、良好なワインが仕込まれている。シャンパーニュは、ブロードベントが五つ星を付けた抜群のヴィンテージで、堅いけれど長く生きる力をもった、年号の入りの泡が多く発売された。
ドイツは、ブロードベントの三つ星。悪くはないが、非常に優れているわけでもなかった。氏によれば、1950年代末までに販売、消費されてしまったらしい。
イタリアは、全体的に良好なヴィンテージで(ブロードベント三つ星~四つ星)、ピエモンテが特に優れていた。1952年のバローロは、今でも市場で見つかる(ただし、当時のバローロはごく少数のネゴシアンしか詰めていなかったので、生産者の選択肢はあまりない)。
スペインの1952年には、ほぼ唯一の高級産地だったリオハにおいて、卓越したワインがいくつも生まれた。7月は涼しかったが、6月と8月は酷暑で、ブドウが完熟した。それでも、この時代のワインは驚くほどアルコール度数が低い。老舗名門マルケス・デ・リスカルの当時の旗艦銘柄、レセルバ・メドックの1952年は、10.8%のアルコールしかなかった(前後のヴィンテージも、おおむね11%台のアルコール度数)。
世界三大甘口ワインの一角、ハンガリーのトカイには、グレート・ヴィンテージが到来した。とはいえ、ハンガリーでは1947年から、共産主義政府によってワイン造りが統制されており、東西冷戦が終結する1989年までは輸出も制限されていた(主要輸出先はロシアで、西側諸国には流れなかった)。ワイナリーやブドウ畑は国有化、集団化され、質より量が優先された時代だ。それでも、1952年には最高のトカイ・アスーが生産されている。
ポートワインの産地ドウロ渓谷はこの年、ブロードベントからひとつも星をもらえなかった。「雨が多く陰鬱」と、一言で片付けられている。ヴィンテージ宣言をしたシッパーはいなかった。そんな年のこの産地から、後述する赤のスティルワイン、バルカ・ヴェーリャが初めて仕込まれたのは興味深い。同じ国の酒精強化の産地で、マデイラはまずまずの三つ星評価。品種では甘口にするマルヴァジアと、中辛口にするヴェルデーリョが良かったようだ。
1952年のカリフォルニア(ナパ)は、かなり優れたヴィンテージだった。非常に気温の低い期間があったにもかかわらず、力強く凝縮したワインが誕生している。
伝説のワインは生まれたか
この年のボルドー赤について、マイケル・ブロードベントは、ある程度熟成が進んだ1960年代から飲み始めている。前評判通り、一部のワインは長く保ったようだ。ボルドーの専門家ジェーン・アンソンも2020年の時点で、「今でも素晴らしい銘柄は多くある」と記している。メドックが難しかったのは上述の通りで、五大シャトーではムートンとオー・ブリオンが、ブロードベントの四つ星で最高評価、ラフィットについては「最上の状態で」二つ星と振るわなかった。それでも、五つ星を獲得したボルドーのシャトーは3つあり、右岸のラ・ミッション・オー・ブリオン、左岸のペトリュス、そしてアンジェリュスである。ニール・マーティンも、この年最良のワインの筆頭に、ペトリュスを持ってきている。甘口白については、ブロードベントによる記録は少なく、クリマン、クーテがともに三つ星を与えられているのみ。イケムは、6月の雹で収量の9割を失い、前年に続いて生産されなかった。辛口白では、オー・ブリオン・ブランに四つ星が贈られている。
ブロードベントは、この年のブルゴーニュ赤について、少なくない数の銘柄に五つ星を与えている。赤ではまず、DRCのロマネ・コンティ、リシュブール、ラ・ターシュに。このほか、ヴォギュエのミュジニ、アンリ・グージュのニュイ・サン・ジョルジュ・クロ・デ・ポレ、ジョゼフ・ドルーアンのグラン・エシェゾーもだ。1952年のロマネ・コンティといえば、戦後の植え替えによる空白期間のあと、初めて瓶詰めされたヴィンテージだ。さすがのカムバックである。アレン・メドウズも、この年のDRCを激賞していて、ロマネ・コンティ(94点)、ラ・ターシュ(97点)、リシュブール(95点)と高得点が並ぶ。その他の赤の銘柄では、ヴォギュエのミュジニ(96点)、コント・リジェ・ベレールのラ・ロマネ(ルロワ瓶詰め/95点)、アルマン・ルソーのシャンベルタン(95点)、ジョゼフ・ドルーアンのミュジニ(95点)、ブシャール・ペール・エ・フィスのヴォルネ・カイユレ・アンシャン・キュヴェ・カルノ(95点)、ヴォギュエのボンヌ・マール(95点)が、95点のラインを超えている。白では、ルイ・ラトゥールのシュヴァリエ・モンラッシェ(95点)、ブシャール・ペール・エ・フィスのコルトン・シャルルマーニュ(95点)が、メドウズの推す最上級品である。
シャンパーニュで、ブロードベントが五つ星を献上した銘柄は、ボランジェ、ゴッセ、ヴーヴ・クリコ、クリュッグ、ポル・ロジェである。ロバート・パーカー引退後の『ワイン・アドヴォケイト』は、フィリポナが造る単一区画名表示のキュヴェ、クロ・デ・ゴワセに100点を献上した(評者はウィリアム・ケリー、2021年試飲)。
スペイン・リオハ地区で大傑作とされた1952年産ワインは、マルケス・デ・ムリエタのカスティーリョ・イガイ、ロペス・デ・エレディアのヴィーニャ・トンドニア、マルケス・デ・リスカルのレセルバ・メドックなどで、これらの老舗は今も、ピラミッドの頂点付近にいる。

マルケル・デ・リスカルは、リオハ・アラベサ地区にある1858年設立のワイナリー。2006年に開業した併設のホテルは、世界的な「ぐにゃぐにゃ」建築家、フランク・ゲイリーがデザインした
カリフォルニア州ナパ・ヴァレーでは、イングルヌックの1952カスクJ-9を、『ワイン・スペクテイター』でカリフォルニアを担当していたレヴュワー、ジェームズ・ローブが非常に高く評価している。
1952年産で、ロバート・パーカー自身が100点満点を与えたワインはない。
スティーヴン・スパリュアは、『死ぬ前に飲むべき100のワイン』の中に、1952シャトー・オーゾンヌを含めている。
さてここで、1952年のワイン・オブ・ザ・ヴィンテージ、伝説のボトルを選ぶとしよう。ボルドー、ブルゴーニュは最高とは言えなかったが、他のエリアでは、卓越の域に達した銘柄が多数生まれた。成功した産地には、候補作がいくつも並ぶ。しかし、あえてこの年はブロードベントに酷評された、ポルトガル北部ドウロ渓谷に光を当てようと思う。ポートの国で生まれた幻の辛口赤、バルカ・ヴェーリャのデビュー作だ。
繰り返すが、ドウロ渓谷といえばポートワインの伝統ある産地である。21世紀に入ってから、ドウロ渓谷では本格スティルワインの赤が、多数出現した。酒精強化ワインが売れなくなったからだ。それまでポートの生産に回していた、一番いい出来の果実を使い、スティルワインを仕込むようになった。
そんな時代の転換が起きるより半世紀も前に、同じトライアルを始めた造り手がいた。カーサ・フェレイリーニャである。オーナーのフェレイラ家は当時、家名を付けたポートワインのブランドで名声を築いていたが、少々遊んでみたくなったのだろう(1987年以降、カーサ・フェレイリーニャ、フェレイラ・ポートともに、ポルトガルの大手ワイン企業ソグラペの傘下に入った)。初の「スーパー・ドウロ」は、バルカ・ヴェーリャと名付けられた。ポルトガル語で「古い船」を意味し、ワインを運ぶためにドウロ川を往来した船という、ポートの伝統に捧げられた名前だ。
カーサ・フェレイニーリャで仕込みを担当したのは、当時の技術監督フェルナンド・ニコラウ・デ・アルメイダである。ブドウは、ドウロの中心地区シマ・コルゴではなく、夏の酷暑と乾燥が激しいドウロ・スペリオール地区で調達した。酸とフレッシュさが得られる高い標高の区画と、ボディと骨格が得られる低い標高の区画の両方を使い、混ぜて発酵させている。辺鄙なドウロ・スペリオール地区の醸造所には当時、電気が通っていなかった。だから、遠くの缶詰工場から氷を、片道12時間かけてトラックで運び、ポルトガル産オークの開放発酵タンクを冷やしたという。ボルドー大学の偉大な醸造学者、故エミール・ペイノー教授から、デ・アルメイダは助言を受けていた。
2025年現在の最新ヴィンテージが2015という事実から推定される通り、バルカ・ヴェーリャは長い瓶熟成を経てから発売される。収穫年から発売までは、平均で9年間の歳月を経ねばならない。瓶詰め時点では、まだバルカ・ヴェーリャのラベルを貼られるかどうか、決めずにおくらしい。月に2回、醸造チームで試飲を行なって、熟成の具合を見る。その過程で、バルカ・ヴェーリャにするか、セカンド・ワインであるレゼルヴァ・エスペシアルにするか、判断を下す。
ブドウ品種は、その歴史の中で大きく変わった。誕生当初は、ティンタ・ロリス(テンプラニーリョ)がブレンドの大半を占めていたが、21世紀に入ってからは、トゥリガ・ナシオナルとトゥリガ・フランカが主力となっている。熟成容器にも変遷があり、初ヴィンテージはポルトガル産オークの小樽で寝かせられたが、現在はフレンチオークの小樽になった。
バルカ・ヴェーリャは、1952年のデビューから、最新ヴィンテージの2015まで、たった21回しか発売されていない。全部並べると、1952、1953、1954、1955、1957、1964、1965、1966、1978、1981、1982、1983、1985、1991、1995, 1999、2000、2004、2008、2011、2015だ。当初は4ヴィンテージ連続で発売されたが、その後は散発的になり、1970年代は1ヴィンテージしかない。

バルカ・ヴェーリャ 2015のラベル ©Sogrape
似たような「寡作ワイン」としては、シャンパーニュのサロンがある。しかしサロンは、初ヴィンテージの1905から最新ヴィンテージの2015までで、合計45ヴィンテージ発売されているから、バルカ・ヴェーリャよりずっと高頻度だ。生産量を比べても、サロンが年産平均6万本なのに対し、バルカ・ヴェーリャは最も多くて4.5万本(1985)、少ないと1.6万本(2015)で、3万本を超えるのは希だ。バルカ・ヴェーリャは、本物の「ユニコーン・ワイン」であり、まず出会えない。一般のワイン愛好家はもちろん、プロでも知らない人のほうが多いだろう。最新ヴィンテージ2015の国際市場価格は、税別で12万円ほど。知っていても、おいそれと買えはしないワインでもある。
1952年のバルカ・ヴェーリャを、今日手に入れる術はあるのだろうか。どこかの愛好家のセラーに、ごくごく少量眠っている可能性は否定しないが、オンライン上には販売の痕跡すらない。ただし、ワイナリーにはまだ、少し残っていそうだ。現在のカーサ・フェレイリーニャで醸造チームを率いるルイス・ソットトマヨールは、2024年の時点で、1952がまだよい状態にあるとコメントしている。
3. 1952年ヴィンテージのまとめ
長寿の銘酒を仕込むワイン生産者は、流れる時間が並の人間と比べ、ずっとゆっくりなのだろうと思う。どの国でも、政治は緊張と弛緩を繰り返し、時には他国との戦争が起きる。それでも造り手たちは、はるか未来の飲み手の姿を考えつつ、黙々とブドウを育て、ワインに変え、瓶に詰め続ける。1952年のハンガリーは、鉄のカーテンの向こう側にあったし、ポルトガルの民は独裁者のもとで窮屈に暮していた。そんな年にも、トカイでは最高の甘口が出来たし、ドウロではバルカ・ヴェーリャが誕生している。これらのワインは、ポルトガルの独裁が終わり(1974年)、冷戦が終結しても(1989年)、まだ生き生きと命を保っていた。
【主要参考文献】
『世紀のワイン』 ミッシェル・ドヴァス著(柴田書店、2000)
『ブルゴーニュワイン100年のヴィンテージ 1900-2005』 ジャッキー・リゴー著(白水社、2006)
『ブルゴーニュワイン大全』 ジャスパー・モリス著(白水社、2012)
Jasper Morris, Inside Burgundy 2nd Edition, BB&R Press, 2021
Jane Anson, Inside Bordeaux, BB&R Press, 2020
Stephen Brook, Complete Bordeaux 4th Edition, Mitchell Beazley, 2022
Allen Meadows, Burgundy Vintages A History From 1845, BurghoundBooks, 2018
Michael Broadbent, Vintage Wine, Websters, 2006
Steven Spurrier, 100 Wines to Try before you Die, Deanter, 2010
Robert Parker’s 100-Point Wines, Wine-Searcher
—————————————-
参考文献
—————————————-
【主要参考文献】
『○○』 ○○○○著(○○社、○○○○年)
『○○』 ○○○○著(○○社、○○○○年)