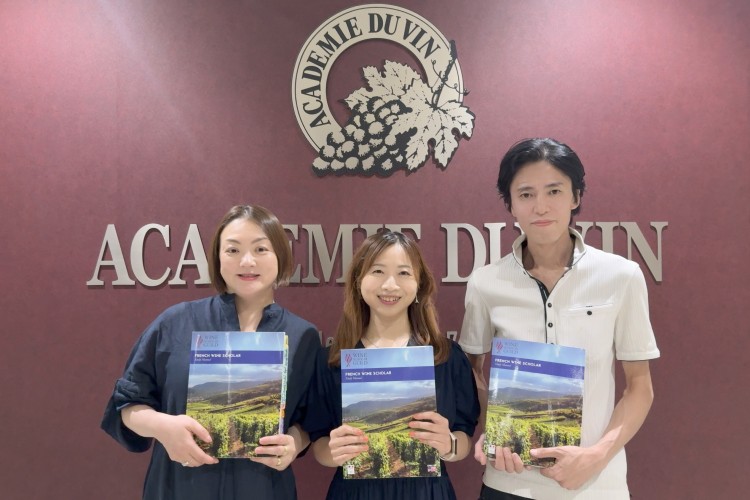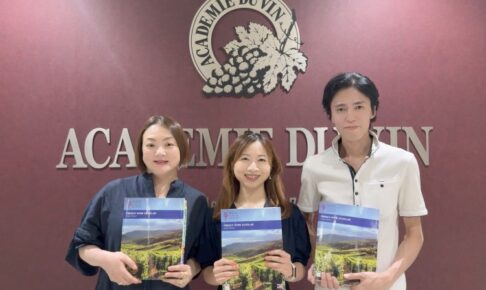French Wine Scholar(以下FWS)試験は、フランスワインの奥深さと真正面から向き合う、まさに「知識の冒険」。今回ご紹介するのは、そんなFWSに挑み、見事合格を果たした3名の方々の体験記です。勉強法の工夫、英語との格闘、そして試験当日のドキドキまで——すべてがリアルに語られています。これからFWSを目指す方にとって、きっと心強い「道しるべ」になるはずです。
【目次】
Q. 自己紹介とフランスワインとの関わりを教えてください。
Q. French Wine Essentials(以下Essentials)は受講されましたか?
Q. ワインの勉強はいつ頃から、どのように始めましたか?
Q. 使用した教材や、役立ったツール・アプリがあれば教えてください。
Q. 試験までのスケジュール管理はどのようにしていましたか?
Q. FWSならではの難しさや、苦労した点があれば教えてください。
Q. 英語力についてはどのようなレベルでしたか?
Q. 試験当日はどのような気持ちで臨まれましたか?当日の雰囲気は?
Q. 試験問題の印象はどうでしたか?内容や出題形式で、JSAやWSETとの違いを感じた点があれば教えてください。
Q. JSAやWSETなど他資格と比べて、FWSの良さ・特徴はどのような点だと感じましたか?
Q. 複数の資格を学ぶことで、ワイン知識がどう深まったと感じますか?
Q. FWSの学習を通して、自分が一番成長したと感じるのはどの部分ですか?
Q. これからFWSを目指す方に、アドバイスやエールをお願いします。
Q. FWSを通じて得た学びや経験は、今後どのように活かしていきたいですか?
Q. 自己紹介とフランスワインとの関わりを教えてください。
入部 隆孝さん(JSAワインエキスパート・WSET® Level3・French Wine Essentials)
飲食店経営。お店で扱うワインは、ほとんどがフランス産。スタッフにはフランス人もいて、フランスはとても身近な存在です。ツール・ド・フランスの熱烈なファンでもあり、仕事も趣味もフランスづくし!
遠山 佳子さん(JSAワインエキスパート&エクセレンス・WSET® Level3・French Wine Essentials)
IT企業広報。とにかくフランスが大好き。これまでに10回以上も渡仏し、毎年1つはワイン資格を取るのがモットー。2018年からずっと、自分の“ワインスキル”をアップデートし続けています。
べニット淳子さん(JSAワインエキスパート受験生・French Wine Essentials・Italian Wine Essentials)
グラフィックデザイナー。17年にわたるフランス生活、そしてフランス人のパートナー。自宅はまるで“小さなフランス”。ワインの勉強を始めたのは昨年ですが、その情熱は人一倍。試験への挑戦も、すでに本気です!
Q. French Wine Essentials(以下Essentials)は受講されましたか?
全員:はい!しっかり受講しました。
遠山:私はEssentialsのおかげで、英語に少しずつ慣れることができました。いきなりFWSに行くよりも、いいステップだったと思います。
べニット:それ、わかります。私も「Shist(片麻岩)」とか「Granite(花崗岩)」とか、ふだん英語で土壌を話す機会なんてないので(笑)、Essentialsでやっておいて本当によかったです。
遠山:もし「英語がちょっと不安…」という方がいたら、まずはエッセンシャルから始めるのが絶対おすすめです!
入部:あと、私はEssentialsを通じて「WSGの世界観」に惹き込まれましたね。単にワインの知識だけじゃなくて、歴史や文化、観光の話題まで織り交ぜながら、産地を物語のように紹介してくれる。それがすごく面白かったです。
Q. ワインの勉強はいつ頃から、どのように始めましたか?
 べニット:本格的にエンジンがかかったのは、試験の1か月前くらいからです。
べニット:本格的にエンジンがかかったのは、試験の1か月前くらいからです。
入部:私は逆に、最初から淡々と。ギアの強弱はなくて、毎回の授業でしっかり予習・復習を重ねていくスタイルでした。
遠山:私も授業の前後に予習・復習はしっかりやっていました。でも、集中して取り組み始めたのは試験の1か月前くらいですね。授業前にテキストを読んで、授業を受けて、終わったら付録のモジュールで問題を解いて、理解を深めていきました。
入部:おもしろいですね!私は逆で、授業の前にモジュールを使って先に問題を解いてから授業、そのあとにテキストを読むという順番でした。
Q. 使用した教材や、役立ったツール・アプリがあれば教えてください。
べニット:私はChatGPTで自分専用の練習問題を作って解いたりしていました。
入部:クラスでChat GPTを使った問題作成、流行っていましたよね。
遠山:私はGoogleドライブに教材やメモをまとめて、どこからでもアクセスできるようにしていました。基本はテキストとモジュールですが、実は「Googleレンズ」にはめちゃくちゃ助けられました。英語はWSETよりは平易に感じたんですが、読むスピードが遅いので、まずGoogleレンズでざっと内容をつかんでから、繰り返し読むようにしていました。
べニット:わかります!私はDeepL翻訳を使って、文のニュアンスを確認しながら進めていました。
Q. 試験までのスケジュール管理はどのようにしていましたか?
遠山:エクセルでTODOリストを作って管理していました。
入部・べニット:おお~。我々だったらエクセルつくるだけで1日かかりそう(笑)。
入部:正直、仕事が忙しすぎて、立てた計画はすべて総崩れでした…。
でもその分、どんなに忙しくても“5分あればテキストを開く”くらいの環境は常に整えていました。そんな中でオンラインモジュールが大活躍!スマホからいつでも開けるので、スキマ時間にとても助けられました。
Q. FWSならではの難しさや、苦労した点があれば教えてください。
べニット:やっぱり暗記量の多さですね…(笑)。
入部:それに加えて、JSA試験と比べると「歴史」や「自然環境」までしっかり覚える必要があります。でもそのおかげで、単なる知識だけじゃなくて、ワイン産地の“背景”が見えてくるようになったと感じます。
遠山:正直、暗記の量だけで言えば、エクセレンスのほうがずっと大変だったと思います。でも内容の深さはFWSの方がすごい。たぶん、エクセレンスを合格してからFWSを受けても、ちゃんと準備しないと受からないと思いますよ。
べニット:そうそう、ひとつの原産地呼称に対して「なぜこの環境でこの品種?」っていう理由づけまで掘り下げるんですよね。
遠山:特にプロヴァンスではそれを実感しました。周辺の山や地形、土壌がどう関係しているかまで、しっかり学びます。
べニット:たしかに!プロヴァンスでは、原産地呼称ごとの樽熟成規定まで出てきましたよね。
遠山:JSAではプロヴァンスって“捨て範囲”だったけど、今回はちゃんとやりました(笑)。でもそのおかげで、苦手意識がなくなって、むしろ「好き!飲みたい!」って思うようになりました。
入部:JSAのときは主要産地だけピックアップして勉強していましたけど、FWSではどの産地も“同じレンズ”で見ていく感じでしたね。私は南西地方、プロヴァンス、ラングドック、ジュラ・サヴォワが特に面白かったです。
遠山:わかる!今までは気にしてなかった産地のワインも、見かけたらつい買ってしまいました。

FWSは知識の深堀りが必要!
Q. 英語力についてはどのようなレベルでしたか?
遠山:WSET® Level3を英語で受けていたので、英語で学ぶのは初めてではありませんでした。でも、実は英語が得意というわけではないんです。ただ、「英語でワインをもう一度しっかり勉強したい!」という気持ちで取り組みました。正直、英語の興味がない本だったら読みたくないけれど、ワインの本なら読みたい……そんな気持ちです(笑)。
べニット:私はちょうど「英語でワインを学んでみたいな」と思っていたタイミングで、まずはEssentialsから始めました。そこで英語のワイン用語に触れて、「私にもできるかも」と自信がついたんです。
入部:私も、べニットさんと同じです。FWSでは、設問の英語が完全に理解できなくても、それまでの知識やロジックを使えば答えられる問題も結構ありました。

授業は日本語で行われるが、テキストは英語
Q. 試験当日はどのような気持ちで臨まれましたか?当日の雰囲気は?
べニット:実は、有休を取るという“裏技”を使って、心と時間の余裕を確保しました!(笑)これだけやったんだから大丈夫、という気持ちで臨めたのがよかったです。
遠山:私は前日に「ラストスパートで詰め込もう!」と思ってたんですが、思ったように頭に入らず……そのまま試験当日を迎えました(笑)。でも、ネイティブでない受験者には試験時間が30分延長されるので、それもあって時間が実は余りました。英語はあまり得意じゃないんですが、「読めない!意味わからない!」という単語は、意外とありませんでしたよ。
入部:私は、マークシートのズレがないか心配で、何度も見直しました。実際にズレていたので、本当に見直してよかったです。30分延長制度、ありがたかった〜!
遠山さん・べニット:それ、大事!!(笑)
Q. 試験問題の印象はどうでしたか?内容や出題形式で、JSAやWSETとの違いを感じた点があれば教えてください。
遠山:まず、エクセレンスとは“深さの質”が違いました。この勉強を通じて「初めて知った!」という内容も多かったですし…。あらためて「深掘り」する勉強が求められる試験だなと実感しました。FWSは選択式ではありますが、ちゃんと覚えていないと正解できない設問ばかり。選択肢も似たような単語が並んでいて、うっかりミスを誘ってきます(笑)。
べニット:確かに、JSA試験って、知識があればパッと答えられる問題が多いですよね。でもFWSの問題は、ちゃんと読んで、しっかり理解して、じっくり考えて答えるタイプ。
“瞬発力”より“読解と判断”が問われる、奥が深いマルチプルチョイスでした。
入部:そうそう、英語で書かれた設問をしっかり読まないと、うっかり引っかかりそうな問題が多く、慎重に読む必要がありました。
べニット:たしか、二重否定のようなひねった聞き方の問題もありましたよね!
Q. JSAやWSETなど他資格と比べて、FWSの良さ・特徴はどのような点だと感じましたか?
入部:FWSは全体的に“ビジュアルで学ばせてくれる”ところが本当に魅力です。テキストもオンラインモジュールも、すべてが視覚的に訴えかけてくるような構成で、自然と理解が深まるんですよね。
べニット:ほんとそれ!“行った気になる”んですよ(笑)。
遠山:私もカリキュラムの途中から、本気で「フランス行きたい欲」が止まらなくなりました。
入部:私はJSA試験のとき、ボージョレのクリュがなかなか頭に入らなかったんですが、FWSの3Dマップを見たら、すっと理解できました。視覚の力ってすごいですね。
遠山:JSAだと、出題が多いブルゴーニュやボルドーから“効率的に”攻めていく勉強になりがちですが、FWSではまずフランス全体のランドマークや地形をしっかり学んでから、産地を北から南へつなげていく流れなので、とてもスムーズに理解できました。JSAやWSETのときは、南西地方とラングドックが地続きでつながっているなんて、正直あまり意識してなかったです(笑)。
べニット:FWSで学んだことで、フランスの地図が頭の中で“パズルのように完成していく”感覚がありましたね。

AOCを掘り下げて学ぶ
Q. 複数の資格を学ぶことで、ワイン知識がどう深まったと感じますか?
遠山:ワインって、放っておくと情報がどんどん古くなっていきます。でもFWSを通じて、フランスの最新事情も知り、今では「フランスワインなら任せて!」と胸を張れるくらいの知識が身につきました。
入部:JSAのエキスパートに合格したとき、「なんとなくわかったような…でも腑に落ちない」と感じていた部分がありました。それがWSETで視界が開け、WSGでまるで“霧が晴れた”ようにすっきりしました。学べば学ぶほど、ワインの景色がくっきり見えてくる。それが本当に楽しいですね。
べニット:そうそう、JSA、WSETとも結局同じことを言っているのだけど、また異なるアプロ―チで講師が話してくれるので、どんどんワインの理解が深まっています
Q. FWSの学習を通して、自分が一番成長したと感じるのはどの部分ですか?
 入部:WSGのカリキュラムでは、歴史だけでなく気候変動など、未来に向けた視点も学べるのが魅力的でした。今ではフランスのことを、より深く語れるようになったと感じています。
入部:WSGのカリキュラムでは、歴史だけでなく気候変動など、未来に向けた視点も学べるのが魅力的でした。今ではフランスのことを、より深く語れるようになったと感じています。
遠山:「フレンチワインのスペシャリストです」と胸を張って言えるようになったことが大きいです。もともとワインに興味をもったきっかけがフランスだったので、そこに自信が持てるようになったのはとても嬉しいですね。
Q. これからFWSを目指す方に、アドバイスやエールをお願いします。
遠山:試験は決してラクではありません。でも、楽しむ気持ちを忘れないことが大切です。授業前にしっかり予習しておくと、内容の理解がまったく違ってきます。しかも、テイスティングのワインもより美味しく感じられるんですよ!1回1回の授業を大切にしてください。
入部:FWSのカリキュラムは、とても奥深く、幅広く設計されています。やればやるほど、自分の視野が広がっていくのを感じられるはずです。どれだけ熱量を持って取り組むかで、得られるものがまったく違ってきます。本気で学びたい人には、強くおすすめしたい資格です。
べニット:やる気さえあれば、FWSは本当に楽しいプログラムです!例えるなら、入門クラスの講師のスピードが0.7倍だとすると、Step-Iは1.25倍、FWSは1.5倍くらいの濃度に感じました(笑)。でも、その密度が心地よくて、気づけば毎回の授業があっという間に2時間半経っていました。
Q. FWSを通じて得た学びや経験は、今後どのように活かしていきたいですか?
 遠山:フランスの産地にもっと行って、生産者の声を直接聞きたいですね。今年はボージョレに行って、なんとマラソンにも参加します!今はモジュールの3Dマップで、現地の地形をしっかり予習中です(笑)。
遠山:フランスの産地にもっと行って、生産者の声を直接聞きたいですね。今年はボージョレに行って、なんとマラソンにも参加します!今はモジュールの3Dマップで、現地の地形をしっかり予習中です(笑)。
べニット:私も、まだ行ったことのないAOCに足を運んで、現地でしか飲めないワインを味わってみたいです。
遠山:あっ、そういえば最近、ワインリストを見るのがすごく楽しくなりましたよね。
入部:その通り!そして、ここで終わりじゃなくて、もっと学びを続けたいなと思っています。おふたりと同じで、久しぶりにフランスに行きたくなりました。“大陸性気候”を肌で感じて、改めて日較差や大陸度を体験したいです!
ワインの勉強というと、つい「暗記」や「試験」が頭に浮かびがちです。でも、FWSで得られるのは、そんな一過性の記憶ではありません。気候、地形、歴史、文化、そして土地の味わい。すべてが繋がって初めて見えてくる“フランスワインの立体地図”。
今回インタビューに答えてくれた3人は、その地図を手に、これからも旅を続けていきます。あなたも、自分だけの「フランスワイン地図」を描いてみませんか?
プロフィール
 入部隆孝(いりべりゅうこう)
入部隆孝(いりべりゅうこう)
飲食店経営。元々はワインの小難しいイメージが嫌だったが、仕事の流れで勉強してみたら想像以上に身体に馴染むことにビックリ。WSET Diplomaを遠目に見据えつつ、仕事ではワインをカジュアルに噛み砕くことを、勉強ではとにかく楽しむことを心掛けています。
 遠山佳子(とおやまよしこ)
遠山佳子(とおやまよしこ)
都内IT企業で広報として働くかたわら、社内ワインサークルを主催。初心者でも気軽に楽しめる場づくりを通じて、ワインの魅力を広めている。副業ではドイツワインインポーター「ワインパラディース」のSNS運用も担当。保有資格はJSA認定ワインエキスパート・エクセレンス/ドイツワインケナー/WSET Level 3など
 ベニット淳子(ベニットじゅんこ)
ベニット淳子(ベニットじゅんこ)
グラフィックデザイナー。17年間のフランス生活後、日本に帰国。「自分のスキルと好きなことを仕事に」とワインの勉強に夢中。資格取得に励みながら“自分らしく”人生をデザイン。IWE, FWE&FWS取得。WSET2、JSAワインエキスパート準備中。