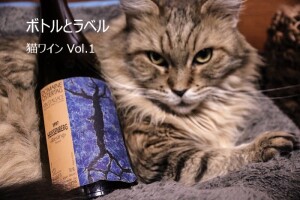長年グラフィックデザイナーとして活躍してきた木村雄太さんが、40代後半に出会った新しい世界―それが「ワイン」でした。最初は趣味として始めた学びが、やがて自作の白地図やまとめシートを通じて、受験生を支える活動へと広がっていきます。今では「note」で “白地地図”やドリル形式の“まとめ資料”などの学習資料を配信中。デザインとワインの知識、その両方を活かしてきた木村さんの歩みを伺いました。
【目次】
1. 好きなことを選んだら、天職になっていた
2. ワインとの出会いは、一軒のワインバーから
3. Step-1から始まる、大人の青春
4. 苦手な産地も、お手製の「白地図」「まとめシート」で克服
5. 白地図とまとめシート─「自分のため」から第三者に
6. “見やすさ”は、愛。美しい資料づくりの舞台裏
7. 一枚の資料にこめる、静かな情熱
8. 何年たっても、ワインの変化についていきたい
1. 好きなことを選んだら、天職になっていた
子どものころから、絵を描くのは好きでした。家業の工場を継ぐはずでしたが、近隣に江戸東京博物館の建設が決まり、目の前の通りに歩道が整備されたことで工場の運営が難しくなりました。大学受験直前に、父から「工場は畳もう。手に職付ける方向で頑張れ」と告げられたことをきっかけに、デザインの道へ方向転換しました。
最初は幼児向け教育の教材イラスト制作からスタート。その後に入社した「DESIGN MATE」では、アニメーションの企画、トランスフォーマーやポケモンといったマスキャラクター商品からお菓子のパッケージまで幅広く手がけました。「これは天職かもしれない」と実感するようになり、気づけばそのまま定年まで勤めていました。

2. ワインとの出会いは、一軒のワインバーから
ワインとの本格的な出会いは、一軒のワインバーから始まりました。
40代後半、19年間続いた結婚生活にひと区切りをつけたあと、夕飯づくりも面倒で、近所のワインバーに通うようになりました。そこは、小学校から高校までの同級生でもありワイン講師の遠藤利三郎さんが営む「遠藤利三郎商店」。
ある日、遠藤さんが言ました。「ただ飲むより、ワインの歴史や文化がわかっていた方が、もっと楽しくなる!」と。さらに「どうせ暇なんだろ、アカデミー・デュ・ヴァンにおいでよ」と、同級生らしい遠慮のない勧誘まで。
そのときは冗談半分に聞いていましたが、気づけば本当に通うことになっていました。人生、どこでスイッチが入るかわからないものです。

アカデミー・デュ・ヴァン講師の遠藤利三郎氏と
3. Step-1から始まる、大人の青春
遠藤講師のStep-ⅠやStep-Ⅱの授業では、テキストの講義になかなか入らないんです(笑)。そのぶん、産地の歴史や文化、周辺の豆知識がとにかく豊富で、それがまた妙に面白いんです。気がつけば、「へえ、そんな背景があるのか」と引き込まれていて、どんどん興味が深まっていく感じでした。
そして、何よりも楽しかったのはクラスメイトとの出会いです。普段の生活ではなかなか接点のないような、さまざまな業界の人たちと知り合えるのが新鮮で、それがまた刺激的でした。
毎週のように、有志でワインを持ち寄って飲みに行く“クラス会”も開かれていて、最初の頃はクラスメイトの飲みっぷりに正直びっくりしました。なにしろ、うちのクラスでは一人一本が“普通”という世界だったんですから。
そんな仲間と一緒に山梨のワイナリーを訪れりしたことも、今では大切な思い出です。実は通学中、クラスメイトと少しお付き合いしていたこともありました。ワインを通じて人との関係性を構築できる経験は新鮮でした。
4. 苦手な産地も、お手製の「白地図」「まとめシート」で克服
Step-1、Step-2と講座を受けていくうちに、自然と「次はワインエキスパート試験を目指してみようか」という流れになりました。でも、いざ試験勉強を始めてみると、テキストの分厚さに圧倒されて…。「本当にこんな量を覚えきれるのか」と、焦りばかりの日々が続きました。
中でも大変だったのが、ギリシャや東欧など、聞き慣れない地名やブドウ品種の名前。教本を読んでも、頭の中でまったく整理されず混乱状態…これはもう、自分なりにやるしかないと覚悟を決めました。
自作の単語帳を作りスキマ時間に反復。さらに、“白地図”を自分でデザインして、産地や情報を書き込む“まとめシート”を作成しました。昭和世代なので手で書いていくうちに、少しずつ頭に定着していくのが不思議としっくりきました。
もうひとつは、「もしかして他の受験生の勉強に使えるかもしれない」という気づきでした。自分が受験のとき、「あれはどこに書いてあったっけ?」と地図帳や教本、用語集や参考書を行ったり来たりして、けっこう時間をとられていたんですね。それならいっそ、全部を一枚にまとめてしまえばいいんじゃないかと。
そんな発想から、“一目でわかる”「まとめシート」スタイルにたどり着きました。
地道な作業でしたが、気がつくと全単元でかなりの量をまとめられていたので、その後に役立てられないかと考え始めました。
5. 白地図とまとめシート─「自分のため」から第三者に
自分の勉強のために書き始めた“白地図”や“まとめシート”ですが、試験が終わったあと、ふと「このまましまい込んでしまうのは、もったいないな」と思いました。毎年教本で更新される箇所を中心に作り直し、その過程で自分も情報をアップデートできるように、もう少しきちんと整理しておこうと思ったのが始まりです。
2012年から、SNSグループで知り合いに資料をお渡しするようになりましたが、図々しくマネタイズしようと考え、2018年には「まぐまぐ」に登録し、有料配信というかたちに変えました。ありがたいことに想像していた以上に多くの方から反響があり、同時に「がんばって続けてきてよかったな」と、じんわり嬉しくなりました。
この資料も年を重ねるごとにスタイルを変えるなどして、“まとめシート”はドリルを解くように書き込み形式に、そして今は「note」を使って配信し続けています。


6. “見やすさ”は、愛。美しい資料づくりの舞台裏
もともとグラフィックの仕事をしていたこともあり、情報を視覚的にどう整理するかには、こだわりがあります。資料を見る人には、紙に出力し、書き込んでじっくり覚えたいタイプと、スマートフォンなどのデバイスでスキマ時間にも確認したいタイプ、2つのスタイルに分かれるように思います。そのどちらの方にも「コンパクトで情報密度を高く」と思っていただける資料を目指しています。
手前味噌ですが人気なのは、ボルドーやブルゴーニュのまとめ資料で、A2サイズで出力できるタイプ。壁に貼って、毎日眺めながら覚えたいという方からご好評をいただいています。個人的にも「勉強が終わってもアクセントになるビジュアル資料であること」をひとつの目標にしています。

ブルゴーニュのポイントを1枚にしたまとめシート
一方で、スマートフォン派の方からは、「通勤中などの隙間時間にさっと見られて助かります」という声も多く届いています。画面が小さいと文字がつぶれやすいので、そのあたりのバランスにも注意を払っていますが、タブレットサイズが実は最適です。
そして、もうひとつ大切にしているのが「最新情報の最速での反映」です。たとえば2024年、教本の執筆陣が変わったことで「日本」のチャプターがガラリと刷新されました。そのときは、週末をまるごと使って更新。おかげで変更内容はほぼ頭に入りました。
7. 一枚の資料にこめる、静かな情熱
資料をお渡しする以上、タイポや表記のゆれは絶対に見逃せない――そう思っているのですが、noteを公開した後でミスに気づき「やっちまった!」とファイルを差し替えすることも多いのです。
私の資料を使って勉強してくださっている様子を、SNSなどで見かけたとき。ご自身のノートと一緒に写真が投稿されていたりすると「使ってくださってるんだな」と嬉しくなります。同時に、「これはもっと丁寧につくらなければ」という責任感も湧いてきます。
8. 何年たっても、ワインの変化についていきたい
ワインエキスパート試験に合格して、もう14年になります。今なお、教本を読み返し、資料を作り続け、配信を続けているのには理由があります。
ひとつは自分がワインエキスパートを受験しても受かれるように知識をアップデートすること。これは受験生だった立場で文字だけの味気ない教本や、他の参考書の中途半端さを補完したいとの思いもあります。そしてもうひとつ――実は、これがけっこう大きいのですが、「おいしくワインを飲みたいから」なんです。
ワインの世界は本当に目まぐるしく変わっていると思います。気がつけば、新しい産地、新しいつくり手、知らなかった品種の名前が次々と登場してくる。アカデミー・デュ・ヴァンに通い始めてワインに触れ始めた頃のようなワクワクを毎年味わえるんです。
実は一番楽しんでいるのは私自身かもしれません。学び続けることは、やっぱりワインと同じで、“飲めば飲むほど”楽しいものです。

ワインバーでのテイスティングセミナー。合格後もワインの学びは続く
「好きだから続けているだけですよ」と笑う木村さんですが、その姿勢からは、細やかな工夫とたしかな熱量が伝わってきます。
ワインに出会ってからの学びが、新たなつながりや楽しみを生み、いまも誰かの背中を押し続けている。そんな“無理のない情熱”こそが、木村さんの魅力なのかもしれません。
プロフィール
木村雄太(きむらゆうた)
note
- 星座:魚座
- 血液型:A型
- ワイン以外の趣味:娘との外食
- 好きな食べ物:食中酒と一緒にいただけるお料理全般
- もし生まれ変わったら何になりたい?:ブラッシュアップライフ的にもう一度自分に。
- 酔っぱらったらどうなる?:酔ってないふりしながら、突然寝てしまいます。
- 人生を変えたワイン:Protos GRAN RESERVA