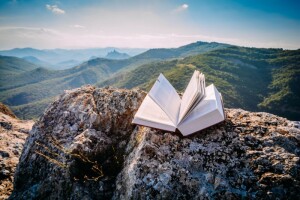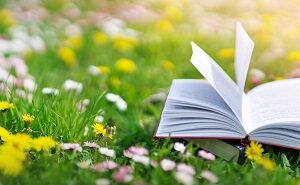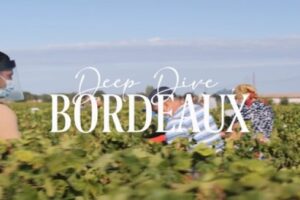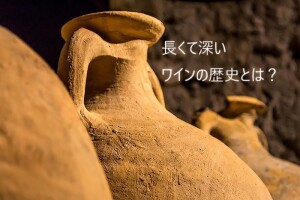生成AIに、「シャンパーニュという語から、連想される言葉を並べろ」と指示してみる。「贅沢」、「エレガント」、「きらめき」、「乾杯」、「特別な日」といった、まぶしく光るコンセプトが並ぶ。何世紀にもわたって生産者が重ねてきた、ブランド・マーケティングの勝利だ。そこに嘘はない。しかし、見えないように隠されている部分、あるいは裏側が、この産地・酒にも当然ある。本記事では、キラキラしていないシャンパーニュの姿を、経済・政治・法律それぞれの角度から素描してみたい。
【目次】
1. 裕福なお百姓さんたち
● シャンパーニュ地方の現在地
● シャンパーニュのブドウ価格と地価
2. 1911年、ふたつの農民蜂起
● 農家とメゾンの不均衡
● オーブの農民蜂起
● マルヌの農民蜂起
3. ノロノロとした法整備
● 贋物との闘い
● シャンパーニュにまつわる法の歩み
● 境界線拡大の試み
4. おわりに
1. 裕福なお百姓さんたち
まず、今日のシャンパーニュがどんなふうだか、ざっと見ておこう。フランス北東部に位置し、5つの県にまたがっている。マルヌ県(全作付け面積の66%)と、オーブ県(同23%)で大部分を占めていて、エーヌ県にも少々(10%)、残るオート・マルヌ県とセーヌ・エ・マルヌ県は、あわせて1%にも満たない。この5県にある多数の村(コミューン)のうち、合計で319だけが、AOCシャンパーニュを造れる(正確に言うと、その原料となるブドウを産出でき、ワインの生産が可能な醸造所を建てられる)。行政上は、マルヌ県には619、オーブ県には433も村があるので、シャンパーニュを生産できる村はいわば少数のエリート、選ればれし存在だ。

AOCシャンパーニュ 県別ブドウ畑面積比率(CIVC発表)
シャンパーニュ地方の現在地
シャンパーニュの造り手というと、きらびやかなイメージな大手メゾン(ネゴシアン・マニピュラン=NM)がまずは頭に浮かぶ。最大手モエ・エ・シャンドンを筆頭に、「グラン・マルク」と呼ばれるネゴシアンのトップ・ブループが24社あり、全生産量の3分の2を占めている。輸出量だと、その占有率は9割に達するから、いかにグラン・マルクが幅を利かせているかがわかる。ただし、その他の中小規模ネゴシアンも、数としては意外に多くて、280社ほどある。協同組合(小規模栽培家がブドウを持ち寄って、共同でワインを生産する施設)も、シャンパーニュ地方にはずまずあって、70社ほど(コーペラティヴ・ド・マニピュラシオン=CMと呼ばれる)。ここまでで、全生産量の約9割になる。
残りの1割を生産しているのが、21世紀になってから急速に増え続けている、「グロワー・シャンパーニュ」である。これは、小さな畑を所有するレコルタン(ブドウ栽培農家)が自ら、ワインを醸造・熟成・瓶詰めして販売する生産形態で、レコルタン・マニピュラン=RMと呼ばれる。ジャック・セロス、エグリ・ウーリエなど、カルト的な人気を博し、経済的にも大成功したRMは増え続けているが、量の面では足し合わせてもわずかしかない。
AOCシャンパーニュを名乗れる319の村には、合計で約3.4万ヘクタールのブドウ畑があり、それが28万に近い数の区画に分かれる。つまり、1区画あたりの平均面積は、わずか0.12ヘクタールしかない。畑の総面積のうち、約300社のネゴシアンが保有するのは10%ほどでしかなく、残りの90%を、1.6万人もいるレコルタンが分け合っている構図だ。ヴィニュロンの規模はさまざまながら、1ヘクタール以下の畑しか所有していない農家が、数の上ではほとんどである。この栽培農家たちのうち、自分でワインを詰めているレコルタン・マニピュランは、まだほんの一握り。残りの農家は皆、ブドウをネゴシアンか協同組合に売って生計を立てている。
シャンパーニュのブドウ価格と地価
ブドウを売る側と買う側では、利害の対立があって当たり前だ。売る側は高く売りたいし、買う側は安く仕入れたい。シャンパーニュ生産の歴史においても、栽培農家(レコルタン)と大手メゾン(グラン・マルク)の関係に、緊張や紛争が生じた瞬間は何度もあった。しかし、ここのところは平和な取引が続いていて、それはブドウの買取り価格が高値で安定しているからだ。2021年収穫のブドウについて、栽培農家がメゾンに売った最低価格は、キロあたり5.76ユーロだった(2025年8月現在の為替レートで990円)。優れた条件の畑だと、プレミアがついて7ユーロまで値段が上がる。ワイン用ブドウの価格としては、世界的に見ても破格の高値である。

シャンパーニュ地方では毎年、1ヘクタールあたりで農家が収穫してよいブドウの上限値(重量)が、生産者団体であるシャンパーニュ委員会によって決められる。年によって2割程度までの上振れ、下振れがあるのだが、平均すれば1万キログラム程度だ。上述したブドウの平均キロ単価と掛け合わせると、ヘクタールあたり57,600ユーロ(約990万円)の売上になる。そこから、トラクターの減価償却費だの農薬代だのあれこれ経費が差し引かれるが、悪くはない収入である。3、4ヘクタールの畑を所有している農家なら、スケールメリットが生じて経費の比率が劇的に下がるから、けっこういい暮らしができそうだ。
ブドウの売値の高低は、農地の価格に反映される。2019年のデータを見ると、マルヌ県のふつうの畑で、1ヘクタールあたり102万ユーロ(1.75億円)、オーブ県で96万ユーロ(1.65億円)が、平均の売買価格だ。マルヌ県内のコート・デ・ブラン地区(シャルドネが有名な銘醸地)だと、168万ユーロ(2.89億円)にもなる。地方全体のアベレージがこれほど高いワイン産地は、地球広しといえど他のどこにもない。ボルドー、ブルゴーニュの両地方では、格付けされている畑に限り、1ヘクタールあたり1000万ユーロを超える天文学的数字にはなる。しかし、地方全体を眺めれば、たいした値が付かないマイナーな地区のほうが圧倒的に広い。カリフォルニア州ナパ・ヴァレーも、中心地域だと1ヘクタールあたりの平均価格が130万ドル(2.24億円)を超えるが、周辺になると10分の1以下まで急落してしまう。フランス全体の平均値とも比べてみよう。同国には今、380ほどのAOC(統計原産地呼称)認定地域が存在する。そのブドウ畑の平均取引価格は、15.1万ユーロ(2600万円)である(2022年統計)。シャンパーニュの地価が、飛び抜けて高いのがわかってもらえるだろう。
2. 1911年、ふたつの農民蜂起
農家とメゾンの不均衡
しかし、100年少々時代をさかのぼると、まったく違って光景が見えてくる。富も、生産資源も、大手メゾンたちだけが握っていて、栽培農家たちは資本家たるメゾンに搾取されていた。シャンパーニュ生産は、仕込みから出荷までのタイムスパンが長いビジネスで、ふつうのワインと比べてキャッシュフローが著しく悪い。大雑把に言うと、何年も無収入で耐えられる者だけが、始められる商売だ。当然のなりゆきとして、零細農家はワインを造っての独立はできず、大手メゾンへの隷従を強いられていた。
そもそも、19世紀の末以降、シャンパーニュ地方の農家たちには厳しい風が吹いていた。1890年頃からメゾンたちが、シャンパーニュの地方外で原料を買い付け始めたのだ。鉄道網の発達によって、遠方から物を運ぶインフラが整いつつあった。主にロワール渓谷と南フランスから、ブドウの入った籠やワインの入った樽が駅に到来し、シャンパーニュ地方産のブドウ価格は半値にまで落ちてしまう。ワインにまつわる法律が一切なかったこの時代、ワイン全体の半分以下(49%まで)なら他地方産の原料を使っていても、ラベルには「Champagne」と書いて売れた。「残りの49%」は、ブドウですらないときもあり、洋梨やリンゴ、ビーツやルバーブなどを使うメゾンもあった。
1890年代から1900年代にかけての20年間、シャンパーニュ地方は天気に恵まれず、みじめなヴィンテージばかりだった。1890年には、南から北にじわじわと上がってきたフィロキセラが、とうとうシャンパーニュ地方に到達してもいた。枯死したブドウ樹を、接ぎ木苗に植え替える労力とコストで、農家たちはいっそう追い詰められた。そんな状況を尻目に、大手メゾンたちは他産地の原料をどんどん仕入れ続け、シャンパーニュ地方から出荷されるスパークリングワインの量は倍増していた。
オーブの農民蜂起
1908年にフランス政府は、シャンパーニュ地方における農家とメゾンの緊張を緩和しようと乗り出した。具体的に言うと、「シャンパーニュを名乗れるワインは、どこのエリアで造れるのか?」を定める最初の政令を出したのだ。「マルヌ県全体と、となりのエーヌ県にある数カ村のブドウ畑」というのがこの時の線引きで、伝統的にシャンパーニュの産地だったオーブ県が除外された。以前から地元では、マルヌ県の人々によるオーブの蔑視、ブドウ産地して劣っているという見方があり、当局の見解はその差別を裏付けた。もちろん、オーブ県の栽培農家は激怒した。
2年あとの1910年は、これまでの20年のどの年にも増して、救いようのないヴィンテージだった。春の霜、雹、洪水を引き起こすほどの大雨と、悪天候のオンパレードで、最終的に収穫できた果実の量は前年の1割だった。冬になると大勢の農家が、北アフリカのアルジェリア(当時はフランスの植民地)のブドウ畑へと、出稼ぎにいった。破産寸前のところばかりだった。そんなさなかの1911年2月、フランス政府は、オーブを除外するという1908年の政令を正式な法律にしてしまう。
これ以上の我慢は、オーブの民にとって不可能だった。ガストン・シュックという名の陶工が先導者となり、オーブのブドウ栽培農家は蜂起した。つるはしで武装した示威行進の参加者たちは、めいめい次のように書かれたワッペンを胸につけていた。
- われわれはシャンパーニュ人だった
- われわれはシャンパーニュ人である
- われわれはシャンパーニュ人で有り続けるだろう
一部の地方自治体は農民に味方し、村役場を封鎖したり、町議会が集団辞職したりで、オーブ県の行政は麻痺した。パリでは、オーブ県選出の議員が政府予算案を承認せず、結果として内閣が総辞職した。
同年4月、オーブ県の中心都市トロワで行なわれたデモは、県全体から4万人が集まった。県庁へ向けてデモ行進がなされ、その脇では数百名の武装兵が警戒に当たっていた。トロワ市長は、全面支持の演説を群衆に向けて行ない、主導者シュックも、「われわれの本当の敵」はマルヌの農家ではなく、「インチキなシャンパーニュを造り、カネが一番大事だと信じている連中」だとぶち上げた。

トロワの市庁舎広場で、群衆に演説するガストン・シェク
マルヌの農民蜂起
1908年の声明、最初の境界策定において、当局からお墨付きをもらえたマルヌ県でも、農民たちの間には不満がくすぶっていた。オーブ県は、シャンパーニュの「産地=醸造所所在地」としては除外されたものの、マルヌ県内にあるメゾンが、オーブ県産のブドウをシャンパーニュの生産に使用するのは構わなかったからだ。加えて、1908年の声明が出されたあとも、シャンパーニュ地方外からのブドウやワインは、大手メゾンの倉庫へと運び込まれ続けていた。違法を承知で、悪しき慣行が続けられたのだ。
1911年1月、ダムリーとオーヴィリエの村で、最初の暴動が発生する。怒り狂った農民たちは、ロワール渓谷からの原料を積んだトラックを無理矢理止めて、マルヌ川に放り込んだ。不誠実と考えられていたメゾンの倉庫を襲撃し、在庫の瓶を破壊し、川に捨てもした。マルヌでも1910ヴィンテージは悲劇的で、多くの栽培農家が経済破綻に瀕していたから、野火はまたたく間に広がっていく。暴徒が襲撃する村は、どんどん増えていった。

マルヌ県で最初に暴動が起きた村のひとつ、ダムリー
同時期に起きていたオーブの反乱を受けて、ひとたび定められた境界線の引き直しがなされそうな雲行きも、マルヌの民の怒りを燃え上がらせた。同県の知事は、パリに向けて「こちらは内戦状態にある」という電報を打ち、3.5万人の兵が派遣された。1万人を超す凶暴な民衆が、シャンパーニュ生産の中心都市エペルネへと向かった。しかし、軍隊によって行く手を阻まれたため、エペルネの北東5キロほどの距離にあるアイ村へと、暴徒たちは行き先を変える。アイでは不幸にも、正直な商売をしていたメゾンまで襲撃された。ワイン造りと無関係な民家も略奪された。車や建物に火が放たれ、町中が燃えた。ブドウ畑も暴力の矛先となった。アイの村では一日のうちに、6軒のメゾンが廃墟になり、数千本のブドウ樹が燃え、600万本近いシャンパーニュのボトルが割られたという。

焼き討ちにあったアイ村のシャンパーニュ・メゾン
3. ノロノロとした法整備
贋物との闘い
今でこそ、シャンパーニュを含むフランスのAOCワインは、強固な規制の数々によって、手厚く守られている。原料ブドウを栽培可能なエリアはもちろんのこと、使用できるブドウ品種、栽培・醸造方法、出来上がったワインの官能特性まで、悪くいえばガチガチに固められた状態だ。これらのルールの束は、一夜にして出来上がったのではない。さまざまなタイプの「贋物」に対し、いつも割を食う農民たちが怒りの声を上げ、勝ち取ってきた権利の集積なのである。
贋物その1は、ブドウ以外を原料とするワインだ。上述した、洋梨やルバーブを原料とするシャンパーニュがその例になる。19世紀後半、フィロキセラ禍で生産量が激減した南フランスでは、ブドウの搾りかすに砂糖を足して発酵させた液体も、ワインとして販売されていた。これも、広義での「ブドウ以外を原料とするワイン」に入るだろう。贋物その2は、ラベルに書かれている産地以外の原料(ブドウやバルクワイン)を含む銘柄だ。いわゆる産地偽装になる。フランスやイタリアの一部地域では、けっこう最近までこの悪習は続けられてきた。たとえばブルゴーニュ地方では、1970年代まで、南仏産の赤ワインをピノ・ノワールにブレンドするのが公然の秘密だった。
シャンパーニュにまつわる法の歩み
ワインとは何かについて、原料の面から最初に規定したフランスの法律が、1889年のグリフ法だ。「新鮮なブドウを発酵させて造った産品」しか、ワインではない(ワインとして販売できない)と定めた。この原則は今日まで、EUのワイン法や、OIV(国際ブドウ・ワイン機構)の基準に受け継がれてきている。5年後の1894年には、ワインに水やアルコールを添加するのも禁止された。
その一方で、上述したように1890年代のシャンパーニュ地方には、「51%以上、同地方産のブドウを原料にすれば、シャンパーニュとして販売可能」というルールがあった。これは強制力のある法律や条令の類いではなく、生産者間での自主的な取り決め、あるいは単なる商習慣だったようだ。シャンパーニュ産ブドウ以外でもよい残りの49%には、ブドウとは違う原料(ルバーブ、洋梨など)も使われていた(グリフ法の成立以降、ブドウ以外の使用は違法になるが、抜け道はあった)。

その後、ワイン原産地の境界線を策定し、産地偽装を追放する法律が、いくつかのステップを踏んで固められていった。最初の産地偽装禁止法は、1905年に制定された「商品販売における不正行為と、食料品と農産物の偽造の防止のための法律」である。これは、ワインを含む食品・農作物について、原産地の虚偽表示をし、消費者を騙そうとする行為に刑罰を科すという法規だ。ただ、肝心の「原産地」の定義、境界線が示されていないので、実効力のないザル法だった。そこで、3年後の1908年にこの法律は改正され(カズヌーヴ法)、ワインの原産地について、「従来からの地元の慣習に基づいて」境界策定をすべし、という規定が追加された。
シャンパーニュ地方でも、この1908年のカズヌーヴ法にのっとり、「地元の慣習に基づいて」境界線が引かれた。「マルヌ県全体と、となりのエーヌ県の数カ村のブドウ畑」に、シャンパーニュを製造できる土地を絞ったのだ(1908年に政令として出され、1911年に法律となった)。オーブ県はワインの製造地としては除外されたが、ブドウの原産地としては認められた。オーブ県、マルヌ県のどちらでも、農家たちが不満を爆発させ、反乱・暴動につながったのは先に見た通りである。

1911年2月、政府はマルヌ県の農家たちの要求を受け入れ、シャンパーニュの生産地域内(この時点では、マルヌ県全域+エーヌ県のごく一部のみ)で収穫されたブドウを使ったワインのみが、シャンパーニュを名乗れるという声明を出す。ワイン製造地だけでなくブドウ産地としても、オーブを除外したのだ。当然ながら、オーブ県の農家がこの裁定に猛反発し、事態はもつれにもつれる。6月になって政府は、オーブ県を「第2シャンパーニュ区域」として認定するという、実に中途半端な決定をした。両陣営ともに、すんなり納得できない内容だったが、反乱はいったん沈静化する。
ほどなく、シャンパーニュ地方は第一次世界大戦の激戦地となり、畑も村落も荒廃した。現在と同じ5県319村を、分け隔てなく産地認定したのは、シャンパーニュが戦後の荒廃から復興を果たしたあと、1927年に出された法令である。それから9年後の1936年には、シャンパーニュ地方産のスパークリングワインがAOCに認定され、品種、製法などの諸規定が追加された。
境界線拡大の試み
シャンパーニュ用のブドウを生産できる村の数は、1927年以来、319のまま変わっていない。しかしながら、21世紀に入って以降、この村の数を増やそうという動きがあって、一旦停止中ながらも現在進行形である。
推進主体となっているのは、シャンパーニュ地方の栽培農家による組合、SGV(Syndicat général des vignerons de la Champagne)だ。SGVからINAO(国立原産地呼称研究所)への提案は、新たに40の村をAOC対象として認定し、代わりに2つの村を除外するという内容だから、いろいろ穏やかではない。40もいっぺんに増やすのは急激すぎるように見えるし、既得権益を失う2つの村では、住民が黙っているはずがない。そもそも、栽培農家の組合がこんな構想を立ち上げるのが、かなり不可思議だ。組合員は、「シャンパーニュを名乗れる」という特権の持ち主ばかりだから、よそ者にその権利を気前よく分け与え、一部の身内から取上げる合理的な理由を思いつかない。旺盛な需要に応えるべく、もっと多くの原料を確保したいのだと、大手メゾンが考えるのなら筋が通る。しかし、それは栽培農家の直接的利益ではない。にも関わらず、2003年に開かれたSGVの総会において、この提案は圧倒的多数により可決されているのだ(賛成票393、反対票25)。

SGVの要望は、2008年にINAOによって一次承認される。2015年から新しい村へのブドウの植え付けが開始され、2021年以降には市場にそのワインが出ると、当時の発表にはあった。ところが、その後このプロセスは進まなくなる。最初の提案から20年以上が経過した2025年2月、SGVは、計画を一時中断すると発表した。今回も、SGVの役員の9割が賛成しての意志決定だという。声明では、「シャンパーニュのAOC生産地域内に存在する、VSIG用ブドウ畑への新植が止まる政治的保証が得られるまで、計画の中断が続く」としている。VSIGとは「原産地表示のないワイン」、つまりフランスワインの等級では最下級に位置する、非常に安価な銘柄のグループを指す(昔の呼び名は「ヴァン・ド・ターブル」)。
AOCシャンパーニュが認定する319の村は、5つの県に広がっているが、その権利がない村の数のほうが多い。シャンパーニュを名乗れない村では、スティルワインであれスパークリングであれ、VSIGしか造れない。昔とは違い、実態がVSIGのラベルに「Champagne」などと大書できる時代ではないので、消費者がAOC Champagneの泡と、VSIGのワインを混同するとは考えにくい。それでも、SGVの組合は、シャンパーニュ地方内にVSIGのブドウ畑があり、そこからワインが生産されているのが気に入らないらしい。100年前のように、不正や詐欺まがいの種になるのではと、今も疑っている。すでにあるVSIGの畑は仕方がないとしても、新しく植えるのを阻止し、先細りになるのを待つ作戦のようだ。
ハテナがたくさん並ぶこの境界再策定の動きだが、いろんな人の生臭い利権が、複雑に絡み合っているのだろう。AOCシャンパーニュのブドウ畑と、VSIGのブドウ畑では、仰天するほど地価が違う。少し古い情報になるが、2009年にトム・スティーヴンソンが発表した記事には、次のような数字が掲載されている。「同地方における最も安い農地は、オート・マルヌ県でヘクタール1800ユーロから、マルヌ県で4000ユーロからである。一方、グラン・クリュ格付けではない、ほどほどの格のAOCシャンパーニュの畑(マルヌ県ベトン村)は、直近の取引で120万ユーロの値が付いた」。4000ユーロと120万ユーロでは、300倍の差がある。新しく認定される村では、ブドウを売る者でも、ワインを売る者でも、桁違いの値上げができる計算になるし、土地を手放せばたちまち億万長者になれる。
4. おわりに
英語圏には、「シャンパン社会主義者 Champagne Socialist」というイディオムがある。20世紀初頭のイギリスで誕生した言葉で、そのものに相当する、直訳されたフランス語は何故だかない(フランスでは、「キャビア左翼 Gauche Caviar」というのが、ほぼ同じ意味になる)。シャンパンであれキャビアであれ、贅沢の象徴である飲食物で、要するに「左翼的政治信条を持つ裕福な人間」に対する侮蔑語である。口では富の公正な分配を説きながら、日々豪華なライフスタイルを享受する――決して珍しくはない、かような人物像に内在する矛盾を刺している。

この言葉の皮肉は、19世紀末から第二次大戦が終わるまで、シャンパーニュ地方が政治的に左傾していたという事実だろう。ワイン製造業界においても、豊かな暮らしができたのは、大手メゾンを経営する限られた数の一族のみ。猫の額のようなブドウ畑を耕す農民たちは、ひどく貧しかったから、団結し、時には戦闘的になった。社会主義、共産主義を信奉する者も少なくなかった。
今日では、零細農家もAOCシャンパーニュの畑を所有する限りにおいて、豊かな暮らしを手に入れた。政治的には、中道右派が主流になった。ブドウは高く売れ、メゾンとの関係も安定し、大きな運命共同体を形成するに至っている。ただ、現在地に到達するまでは、長く曲がりくねった、凸凹の多い道のりがあった。今でもきっと、穏やかな水面の下をのぞき込めば、なにやら姿形のわからぬ物がうごめいているだろう。
ワインは生き物だとよく言われるが、ワイン産地も生き物だ。毎年の作柄、中長期での気候変動といった「お天気」だけが、その生きざまを決めるのではない。政治、法律といった上部構造と、経済という下部構造が、複雑に絡み合いつつ、重層的決定がなされていく。きらびやかなイメージしかない今日のシャンパーニュでも、100年と少し前には、内戦寸前の暴動が起き、町が燃えていた。蓋然性の高い未来予測が不可能なのは、これからも同じだろう。100年後のシャンパーニュを見透す、水晶の玉はない。