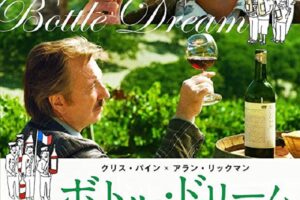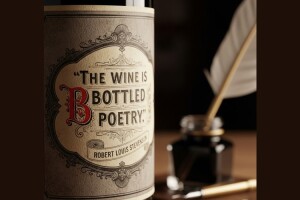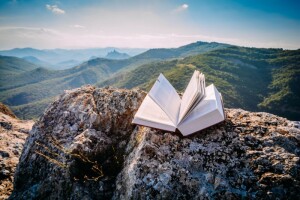ワインは毎年、秋が来れば仕込まれる。偉大と称されるワインは皆、ブドウが摘まれ、酵母の力で酒に変わった年――ヴィンテージをラベルに記している(シャンパーニュなどで一部例外はあるが)。好天続きで、労せずして優品が量産されたような年もあれば、雨、霜、雹、熱波といった天候イベントによって、造り手が唇を噛んだ年もある。ただ、どれひとつとして同じ年はなく、優れたワインはどこの地域の産であれ、ヴィンテージの個性が刻印されている。
本連載では、第二次世界大戦が終わった年から現在に至るまでのヴィンテージを、世相や文化とともに、ひとつずつ解説していく。ワイン産地の解説としては、フランスの二大銘醸地であるボルドー、ブルゴーニュを中心とするが、折にふれて他国、他産地の状況も紹介していく。
本記事では、1950年を紹介しよう。全般に、天候不順のために結果が出なかったヴィンテージだが、奇跡の一本は生まれた。
【目次】
1. 1950年はどんな年だったか?
● 世界の出来事
● 日本の出来事
● カルチャー(本、映画など)
2. 1950年にはどんなワインが造られたか?
● ボルドーワインの1950年ヴィンテージ
● ブルゴーニュワインの1950年ヴィンテージ
● その他の産地
● 伝説のワインは生まれたか
3. 1950年ヴィンテージのまとめ
1. 1950年はどんな年だったか?
世界の出来事
1950年は、東西冷戦がアジアにおける代理戦争、すなわち朝鮮戦争という「熱い戦い」につながった年だと記憶されている。
朝鮮戦争が始まったのは6月25日。金日成率いる北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)が、事実上の国境であった38度線を越え、韓国に侵攻した。北朝鮮の後ろ盾は、ソ連のヨシフ・スターリンならびに、中華人民共和国(中国)の毛沢東である。韓国をバックアップしたのは、日本に駐留していたアメリカ合衆国軍が、その大半を占める国連軍だった。3年間続いたこの戦争で、朝鮮半島全土が戦場となったが、結着は付かずに休戦に至ったのみ、今も両国間に平和条約は結ばれていない(つまり、いまだ戦時中の状態にある)。

朝鮮戦争のさなか、避難する韓国の難民
イデオロギー対立により、南北に分かれたのは朝鮮半島だけではなかった。共産主義を掲げる北ベトナム(ベトナム民主共和国)と、資本主義陣営の南ベトナム(ベトナム国)の対立も、まったく同じ構図だ。1950年、ソ連と中国が北ベトナムを正統な国家として承認し、アメリカ合衆国とイギリスは、フランスの傀儡国家であったベトナム国を承認した。かくして、ベトナム戦争(1955~1975年)へのカウントダウンが始まる。
東西冷戦はこの年、アメリカ合衆国内の経済や政治にも、大きな影響を及ぼしている。とりわけ朝鮮戦争の勃発が、1950年代のアメリカ合衆国の経済に与えたインパクトは大きかった。軍需品の大量需要は、さまざまな産業、とりわけ自動車産業に大きな直接的利益をもたらしている。一方、国内政治においては、戦後徐々に強まっていたアンチ共産主義の思想統制に、「マッカーシズム」という名がついた年でもある。この名は、当政策を強く推進したウィスコンシン州選出の共和党上院議員、ジョセフ・マッカーシーにちなむ。政府職員、軍、マスコミ関係者、ハリウッドの映画関係者、アカデミアの住人など、幅広い領域で「赤狩り」が行なわれ、告発された者は職を失うばかりか、有罪判決を言い渡されもした。

共和党上院議員のジョセフ・マッカーシー
フランスでは、外務大臣ロベール・シューマンが提唱した通称「シューマン・プラン」(ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体=ECSC)を、1950という年号とともに記憶に刻むべきだろう。独仏間が諍いを起こすたびに戦場となり、両国の間を行き来するロレーヌ地方の出身だったシューマンは、ヨーロッパの統合を夢見ていた。シューマンは、不倶戴天の敵同士だったフランスと西ドイツが、石炭と鉄鋼を共同管理する提案を行い、西ドイツが受け入れた結果、ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体が設立された。これは、現在の欧州連合(EU)の種になった、いくつかの連盟のひとつである。統合の動きは長期的に見て、フランスの経済成長と安定に寄与した。
東西分割後の西ドイツは、資本主義体制の下で急速な復興が進み始め、1950年代末には、ミラクルと呼ばれるほどの経済成長を遂げる。1950年時点では、いまだ失業率が10%程度と非常に高い水準だったが、物価統制の撤廃や、1948年に行われた通貨改革(ライヒスマルクからドイツマルクへの切り替え)の成果が出始めたため、経済は上を向き始めていた。一方、東ドイツでは、社会主義の下で経済が悪化し、西ドイツとの格差が開いていく。
ドイツと同じく敗戦国となったイタリアにも、経済復興の波が押し寄せる。1950年からの7年間で、鉱工業生産が75%も上昇し、その間、国民総生産の増加も年平均5.6%と高い成長率を記録した。かねてから同国は、豊かな北部と貧しい南部の格差が問題だったが、1950年には南部開発公庫(Cassa per il Mezzogiorno)が設立され、南部地域の産業基盤整備のための政府出資が行われるなど、格差是正に向けた取組みが本格化した。
日本の出来事
前年に施行された政策、通称「ドッジ・ライン」は、戦後に生じた激しいインフレの抑制をその目的としていたが、結果として労使対立の激化やストライキの頻発を招き、失業者が増加、企業倒産も相次いだ。しかし、1950年6月の朝鮮戦争勃発が、日本でも大きな転機になる。駐日アメリカ軍からの「朝鮮特需」で、一気に経済は上を向いた。土嚢用麻袋、軍服、軍用毛布、テントなどに使用される繊維製品が大量に発注されたため、繊維産業は大きな利益を出し、「糸へん景気」と呼ばれた。このほか、米陸軍から日本国内自動車メーカーへの発注は、現在の「自動車王国ニッポン」の礎になっている。民間貿易についても、1947年に解禁になった輸出に続き、1950年には輸入が再開され、商社による自由貿易が活発化した。
朝鮮戦争によって変わったのは、経済だけではない。政治的にも、アメリカ合衆国の極東地域戦略において、日本が極めて重要な拠点になった。この日本の位置づけの変化は、翌年に調印される日米安全保障条約へとつながっていく。
社会面の事件では、金閣寺の焼失が大騒ぎになった。誰もが知る京都の象徴建築のひとつ、金閣寺(鹿苑寺)の舎利殿が、放火によって全焼したのだ(1955年に再建)。舎利殿を建てた室町幕府の将軍である、足利義満の像(国宝)も同時に焼失した。犯人は、同寺の徒弟僧であった林承賢(犯行当時21歳)で、1950年末に懲役7年の刑が確定している(刑務所内で心身の調子を崩し、釈放後の1956年に病死)。林は、犯行直後にも自殺を図ったが、未遂に終わり逮捕された。犯行動機は謎めいており、事件後に多くの識者が推理、分析を試みている。小説家の三島由紀夫は、この事件をモデルに、代表作となった『金閣寺』を著わした(1956年刊行)。

焼失直後の金閣寺舎利殿
国内政治のニュースとして今も語られるのは、池田勇人大蔵大臣による『貧乏人は麦飯を食え』発言である。12月7日、参議院の予算委員会において行なった、高騰する米価についての答弁中に発せられた。正確な発言は、「私は所得に応じて、所得の少ない人は麦を多く食う、所得の多い人は米を食うというような、経済の原則にそったほうへ持って行きたい」だったが、マスコミが誇張されたワンフレーズで報道したため、翌日の大臣更迭となった。
穏やかなニュースだとこの年、プロ野球初の日本シリーズ(当時の名称は日本選手権試合)が開催された。パ・リーグを制した毎日オリオンズ(現在の千葉ロッテマリーンズ)が、セ・リーグの松竹ロビンス(現在の横浜DeNAベイスターズ)を下し、日本一に輝いた。
カルチャー(本、映画など)
芥川賞の受賞作は、辻亮一の 『異邦人』。直木賞の受賞作は、今日出海 『天皇の帽子』、小山いと子『執行猶予』、檀一雄『真説石川五右衛門』および『長恨歌』である。この年の日本におけるベストセラー1位は、昨年もランクインしていた谷崎潤一郎の『細雪』。海外文学で世間を騒がせたベストセラーは、D.H. ロレンスによる『チャタレイ夫人の恋人』の邦訳だ。警視庁が同作を、刑法第175条のわいせつ物頒布罪で摘発し、翻訳者と版元社長が翌年に逮捕された。わいせつか、表現の自由かは、いまもくすぶる問題だが、その基準は時代とともに変わっていく。
海外文学に目を向けると、アメリカで「ビート・ジェネレーション」と呼ばれるグループの作家たちが活動を始めている。代表作家のひとり、ジャック・ケルアックは、長編第一作である『ザ・タウン・アンド・ザ・シティ』をこの年に発表した。これまでの社会規範や価値観を否定する同グループの作家たちは、のちにヒッピーたちから熱狂的な支持を受け、アメリカを震源とする世界的カルチャーのうねりを生んでいく。対象的に、平和な英米児童文学の世界も、1950年代に第三黄金期を迎えた。今も読み継がれるC.S. ルイスの『ナルニア国物語』は、この年に第一巻が発売され、ベストセラーになっている。SFでは、有名な三原則を唱えたアイザック・アシモフの古典、『われはロボット/アイ・ロボット』がこの年の発表だ。ノーベル文学賞を贈られた人物は、イギリス人哲学者のバートランド・ラッセルで、創作の世界の住人以外がこの賞を授かるのは珍しい。
日本映画については、映画雑誌『キネマ旬報』が年間第1位に選んだのが、今井正監督による代表作のひとつ、『また逢う日まで』 だ。戦争によって引き裂かれたカップルの姿に、反戦のメッセージを込めた、モノクロームの名作である。主人公たちのガラス越しのキスシーンが、話題を呼んだ。翌年に、ヴェネツィアで金獅子賞を獲得する黒澤明監督の大傑作、『羅生門』もこの年の公開だ。

『また逢う日まで』のガラス越しのキスシーン(久我美子と岡田英次)
アメリカ映画の世界だと、この年のアカデミー賞作品賞は、ロバート・ロッセン監督・脚本・製作の『オール・ザ・キングスメン』である(公開は前年の1949年)。興行的成功を収め、批評家からも評価された同作だったが、赤狩りの嵐に巻き込まれ、ロッセンは監督賞、脚本賞を逃してしまう。アカデミー賞授賞式の直前に、ロッセンが共産党員だった過去が、下院非米活動委員会の召還によって明らかになったためだ。当局からの圧力で映画作りがままならなくなったロッセンは、転向して同胞だった共産党員の名を多数証言し、ハリウッドを去っている。
ヨーロッパの国際映画祭の筆頭であるカンヌはこの年、予算不足で開催されなかった。ヴェネツィア国際映画祭で最高の作品に贈られる金獅子賞は、アンドレ・ガイヤック監督のフランス映画 『裁きは終わりぬ』 に授けられた。
ポピュラー音楽の界隈では、アメリカのフォーク・バンド、ザ・ウィーヴァーズによる『おやすみアイリーン Goodnight, Irene』が、年の瀬に発表されるビルボード年間チャートで最高位に輝いた。カバー曲で、オリジナルは1933年、ブルース・ミュージシャンのレッドベリーによる。ザ・ウィーヴァーズによる成功のあと、フランク・シナトラからキース・リチャーズ、トム・ウェイツ、エリック・クラプトンなど、多くの著名ミュージシャンがカバーしている。
この年に生を受けた著名人について、手短に紹介しよう。スポーツ界では、ポーランド人サッカー選手のグジェゴシ・ラトー、プロレスラーの天龍源一郎、野球選手の東尾修ら。映画界では監督の森田芳光、文学界では伊集院静、矢作俊彦、漫画では庄司陽子、竹宮恵子、いがらしゆみこ、音楽の分野では作曲家の久石譲、歌手のカレン・カーペンター、スージー・クワトロ、ナタリー・コール、ヒューイ・ルイス、スティーヴィー・ワンダー、イルカ、山本譲二、細川たかし、八代亜紀、和田アキ子ら。俳優では、市毛良枝、舘ひろし、鹿賀丈史、神田正輝らが、料理界ではピエール・ガニェールが、それぞれこの年の生まれである。なぜだか、日本でも知名度の高い外国人が少なかった。
一方、この年の死没者としては、『動物農場』、『1984』などの作品で知られるイギリス人作家のジョージ・オーウェル、フランス人の文化人類学者マルセル・モースらがいる。
2. 1950年にはどんなワインが造られたか?
ボルドーワインの1950年ヴィンテージ
赤は、エリアによって評価の分かれるヴィンテージである。左岸はぱっとしないが、右岸では成功を収めたシャトーが、数多くはないがある。秋雨の前に摘み取りを終えたかが、成否をわけた。早熟のメルロやカベルネ・フランが主に植わる右岸では、降り出す前にブドウを収穫するチャンスがあったのだ。全体に、骨格の強さよりも、優雅さと香り高さがウリの年となった。マイケル・ブロードベントによるヴィンテージ評価は、赤、甘口白ともにふたつ星(満点は5つ星)。

サンテミリオンのブドウ畑
萌芽は3月末。4月は雨が多かった。5月にも嵐があったが、気温は高く、開花がピークに達した6月8日まで高温は続いた。開花がうまく運んだので、高収量が予想されたが、6月15日に左岸のサン・ジュリアンとポイヤック南部に雹が降り、一部のシャトーでは果実の大部分が失われてしまっている。それでも全体としては収量が多い年で、1949年の2倍近かった。6月下旬から7月には、40℃近い酷暑の日があり、8月はおおむね好天で、気温が上がりすぎもしなかった。品質面でもよい作柄になると予測されていたのだが、そののちの収穫期に大雨が降り、目算は大きく狂ってしまう。それでも、右岸については9月前半の天候がまずまずで、早熟のメルロの摘み取りまでもってくれた。
甘口白については、6月13日、22日にソーテルヌ地区に雹が降り、大幅な収量減につながった。しかしながら、軽い雨によって貴腐菌の繁殖が進み、インディアン・サマーの到来もあって、そう悪くないヴィンテージになっている。
ブルゴーニュワインの1950年ヴィンテージ
残念な不作年である。マイケル・ブロードベントによるヴィンテージ評価は、赤は星ひとつ、白は星3つ。白のほうが評価は高いものの、平均寿命を考えると、今日飲める状態のボトルは残っていまい。アレン・メドウズも、赤白合わせて星ひとつの評価だ。とにかく、天候に恵まれなかった。
春の霜害はなく、開花時期の天候も良かったので、大量のブドウが樹についた。しかし、7月、8月、9月と3ヶ月にわたって、コート・ドールの広範囲で雹が降った。8月、9月は雨ばかりで、果実の成熟が遅れただけでなく、雹の被害とも相まって、カビ系の病気が蔓延した。9月下旬に収穫が許可されたが、未熟なブドウが熟するのを待ちたい、しかし待てばカビが広がるという、板挟みの場所に造り手たちは立たされた。雨が多く日照が不足していたのに、収量だけは多かったため、果実は熟さなかった。生まれたのは、青臭く、味の薄いワインだった。

入道雲から降ってくる、直径5mm以上の氷塊を雹と呼ぶ(5mm未満はアラレ)。大きい雹だとゴルフボール大になり、落ちてくる時速は100km以上、自動車のフロントガラスが割れる
その他の産地
ボルドー、ブルゴーニュに限らず、フランスはおおむねどこも厳しかった。ローヌ、ロワール、アルザス、シャンパーニュ、すべての産地で評価は低い。
ドイツも、ブロードベント2つ星と厳しい。早飲みだったせいだろう、ワインのほとんどが、1950年代半ばまでに跡形もなく消えてしまったと、ブロードベントは記している。
イタリアもいまひとつ。「平均的、あるいはやや良好」ぐらいの評価で、まったくの不作年ではなかったものの、後世に語り継がれるような、あるいは今日まで未開封で残されているようなワインは生まれなかった。
ポートワインの産地であるドウロ渓谷は、恵まれない年にそれなりの成功を収めた、数少ない産地のひとつだ。この年、ヴィンテージ宣言をしたシッパーは多い。そのうちのいくつかは、最高とまではいかないまでも、かなり高く評価されている。マデイラ島で生まれる酒精強化ワインも、ポートと同様だった。
1950年のカリフォルニアは、凡庸な作柄だった。
伝説のワインは生まれたか
この年のボルドー赤について、古酒の神様マイケル・ブロードベントが満点の5つ星を献上したのは、ポムロール地区のシャトー・ラフルールのみである(ただし、後述の留保付き)。右岸の4つ星は、同じくポムロール地区のペトリュス、ル・ゲイだけで、サンテミリオン地区からはひとつも出なかった。左岸の4つ星も、シャトー・マルゴー、ラ・ミッション・オー・ブリオンしかない。甘口白で5つ星を獲得した銘柄はゼロだが、クーテ、ドワジ・ヴェドリーヌ、ジレット・「クレーム・ド・テット」、ルーミューは4つ星だ。
ニール・マーティンが高く評価するのも、ほとんどが右岸の赤だが、ブロードベントより評価は肯定的だ。筆頭に上げたのは、ポムロール地区のペトリュスとラフルールで、「ともに魔法のよう」だと評している。ポムロール地区ではほかに、ヴュー・シャトー・セルタン、ラ・フルール・ペトリュスを優良銘柄として挙げた。サンテミリオン地区では、シュヴァル・ブランとフィジェックについて言及し、オーゾンヌよりも勝るとしている。左岸についても、ラトゥールは「驚くほど元気」だと評したが、この蔵が左岸のトップシャトーの中で、決まって一番に摘み取りを始まるという事実と無関係ではあるまい。1950年の甘口白についてマーティンは、イケムを誉めたほか、サン・タマン(Saint-Amand)という、1990年代までは存在していた無名シャトーが、2015年の時点でまだ輝いていたと述べている。
ロバート・パーカーは、1950年産のワインにただひとつだけ、100点満点を与えた。シャトー・ラフルールである。
ブロードベントがこの年のブルゴーニュ赤について、4つ星以上を与えている銘柄はない。白では、マルキ・ド・ラギッシュのモンラッシェ(現在の瓶詰め元はジョゼフ・ドルーアン)に、4つ星が与えられている。ただ、1978年時の試飲評価だから、とうに昇天してしまっているだろう。アレン・メドウズが90点以上を与えた赤の銘柄は、コント・リジェ・ベレールのラ・ロマネ(ルロワ瓶詰め/91点)のみ、白についてはひとつもない。
1950のワイン・オブ・ザ・ヴィンテージを選ぶなら、やはりシャトー・ラフルールになるだろう。ブロードベント、マーティン、そしてロバート・パーカーの評価が一致している。ただし、ブロードベントにとって、このワインは甘く濃すぎたようで、「料理に合わない」とした上で、「記念碑的な巨大さにおいては5つ星、飲み物としては1つ星」という皮肉を効かせた判決を言い渡した。興味深いのは、マーティンが同じワインについて、「数十年の時を経て、優雅で洗練されている」というコメントをしている点だ。マーティンは、一時期パーカーの元で働いていたが、味の好みにおいては、師匠ほど明からさまに濃厚な風味を支持しない。

シャトー・ラフルールのラベル。1950年当時から基本デザインは変わっていない。ⒸChâteau Lafleur
比較的歴史の浅いル・パン(1979年が初ヴィンテージ)を除けば、ラフルールは長年にわたり、ポムロール地区でペトリュスに次ぐワインとして、極めて高い評価を受けてきた。1950のように濃厚になるのは希で、通常は果実味のピュアさとフィネスが、このワインのアイデンティティだと見なされている。ペトリュスが、ほぼメルロ100%なのに対し、ラフルールはカベルネ・フランが過半で、それがこの個性につながっているようだ。所有畑の面積は、たった4.5ヘクタールしかなく、セカンドワインをも含めた全生産本数は、2万本に届かない。近年のヴィンテージでも、滅多に目にしないのだから、古酒になると入手は絶望的に困難だ。パーカー100点という勲章のせいで、贋作も多く出回っている。それでも、死ぬまでに本物を一度は飲んでみたい。
3. 1950年ヴィンテージのまとめ
荒野に咲く、一輪の花。それがラフルールという、「秘すれば花」を地で行くシャトーだったのは、とてもドラマチックだ。そもそもフランス語の「フルール fleur」は、「花」の意味であるし。カッコいい、とても。
【主要参考文献】
『世紀のワイン』 ミッシェル・ドヴァス著(柴田書店、2000)
『ブルゴーニュワイン100年のヴィンテージ 1900-2005』 ジャッキー・リゴー著(白水社、2006)
『ブルゴーニュワイン大全』 ジャスパー・モリス著(白水社、2012)
Jasper Morris, Inside Burgundy 2nd Edition, BB&R Press, 2021
Jane Anson, Inside Bordeaux, BB&R Press, 2020
Stephen Brook, Complete Bordeaux 4th Edition, Mitchell Beazley, 2022
Allen Meadows, Burgundy Vintages A History From 1845, BurghoundBooks, 2018
Michael Broadbent, Vintage Wine, Websters, 2006
Steven Spurrier, 100 Wines to Try before you Die, Deanter, 2010
Robert Parker’s 100-Point Wines, Wine-Searcher