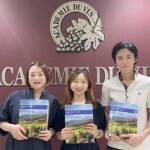近年、めきめきと進歩・進化し、かつての栄光を取り戻しつつあるドイツワイン。白だけでなく赤も、甘口だけでなく辛口も、再び賞賛されるようになってから久しいです。先頭を駆けるのが、白はリースリング、赤はピノ・ノワールなのは、皆様もうご存じでしょう(ドイツでピノ・ノワールは、シュペートブルグンダーと呼ばれます)。産地については、ラインガウ、モーゼル、ファルツという従前からのエリートたちに、かつては冴えなかったラインヘッセンやバーデンらの新興勢力が迫ってきました。しかしながら、この卓越したドイツワインのグループに、独自の道を行く第三極があるのはあまり知られていません。その名はフランケン。バイエルン州にあるワイン産地で、ドイツに全部で13個存在する、公的な指定栽培地域のひとつです。フランケンは、ジルヴァーナーという白品種の辛口ワインを、ボックスボイテルと呼ばれる特殊な瓶に詰めるので有名なのですが、長い歴史の中で育まれてきた独自の文化は、すべてのワイン愛好家にとって知る価値があります。本記事を通じ、その全体像と重要な細部を学びましょう。
【目次】
1. フランケンワインの概要: 土地柄、歴史、栽培品種など
2. ジルヴァーナー:フランケンワインの主要品種
3. ボックスボイテル:愛されつづけるフランケンワインの伝統的な瓶
4. フランケンワインの主要な村と特級畑
5. フランケンワインの主要な生産者
6. フランケンワインのまとめ
1. フランケンワインの概要: 土地柄、歴史、栽培品種など
フランケン(Franken)、英語圏でしばしばフランコニア(Franconia)と呼ばれるこの産地は、ドイツ中南部から南ドイツの北部に位置します。行政上は、ミュンヘンの街を州都とするバイエルン州に属していて、ドイツの主要なワイン産地群(モーゼル、ラインガウなど)より、かなり東に位置します(旧西ドイツ内にある11の産地の中では、最も東)。前者が、ライン川の流域に広がるブドウ畑なのに対し、フランケン地方を流れるのはマイン川です。

フランケン地方が含まれるバイエルン地方の位置
フランケンの名は昔々、ドイツからベルギー、オダンダにかけての土地を支配していたゲルマン民族の一部族、フランク族にちなみます。ホラー小説の古典、『フランケンシュタイン』とも軽い関係があって、イギリス人作者メアリー・シェリーが作品執筆前の1814年に訪れた、同地方のフランケンシュタイン城からその名を拝借したようです。
フランク族が、現在のフランケン地方にやってきて定住したのは、6世紀頃。ワイン造りの歴史は、文献の上では8世紀末まで遡れ、フランク王国の国王カール大帝(仏名:シャルルマーニュ)が、当地の修道院にブドウ畑を寄進した記録が残っています。文字としては残っていないものの、7世紀にこの土地に渡ってきた、アイルランド人の宣教師が、どうやらキリスト教とともにワイン造りを伝えたようです。
現在のブドウ栽培面積は、6000ヘクタールを少し超えるほどで、13指定栽培地域のランキングで真ん中ぐらい。過去60年間で、面積が3倍に成長しましたが、昔はもっと大きな産地でした。1500年の時点で、4万ヘクタールもの畑があったのが、17世紀以降は縮小フェーズに入り、30年戦争(1618-1648)、19世紀末のフィロキセラ禍といった災難のたびに、ぐっと減っていってしまったのです。近年の栽培面積急増は、後に述べる辛口スタイルの堅持が原因のひとつでしょう。
地方(指定栽培地域)内の、公的な地区(ベライヒ)は12ありますが、大きく3つのエリア、西から東へと、マインフィアエック Mainviereck(ベライヒ数3)、マインドライエック Maindreieck(ベライヒ数4)、シュタイガーヴァルト Steigerwald(ベライヒ数5)に分けられます。土壌に明白な違いがあり、東にいくほど地層の年代が新しいです。気候の面では、降水量が比較的少なく(年間600mm程度)、西にある「リースリング王国」諸産地と比べて冷涼になります。産地内で最も高名なエリアは、世界遺産の町ヴュルツブルクを中心に広がるマインドライエックで、象徴品種ジルヴァーナーからの辛口は、ここが本拠と言ってよいでしょう。西側のマインフィアエックでは、1990年代からピノ・ノワール(シュペートブルグンダー)の赤が高く評価され始めました。東側のシュタイガーヴァルトは、標高が高く冷涼であるため、ジルヴァーナーに加えて、近年リースリングも注目を集めています。

ヴュルツブルクの旧マイン橋とマリエンベルク要塞
ブドウ品種の内訳を見ると、白ワイン用品種が全体の8割を占めていて、ジルヴァーナーが25%ほど、僅差でミューラー・トゥルガウが続きます。リースリングは5%強と、数字の上では存在感がありません。全体の2割を占める赤・ロゼワイン用品種では、交配種のドミナ、ピノ・ノワール(シュペートブルグンダー)が、おのおの全体の5%弱です。
生産されるワインのスタイルにおいて、フランケンはドイツで独自の位置を占めていました。第二次大戦後から1980年代まで、他産地は廉価で味の薄い中甘口を量産していましたが、フランケンは辛口一筋だったのです。今でこそ、辛口のドイツワインは当たり前になりましたが、一世代、二世代前まで、トロッケン Trocken (辛口)とラベルに書かれたフランケンは孤狼でした。
そんなフランケンのワインを、心から愛した人物のひとりが、ドイツの誇る文豪ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ(1749-1832)です。生涯を通じ、熱心かつ大量にドイツワインを飲んだこの文筆家は、フランケン産を、とりわけヴュルツブルガー・シュタインのワインを、ほかのどの産地や銘柄よりも好んだと言います。
2. Silvaner(ジルヴァーナー):フランケンワインの主要品種
もともとは、ドイツの隣国オーストリアで、500年以上前に自然交配で誕生した白ブドウです。現在は、ドイツと、フランスのアルザス地方(ライン川を挟んでドイツのバーデン地方と接するエリア)で、主に栽培されています。なぜだかよくわかりませんが、母国オーストリアでは、今日ごくわずかしか植えられていません。フランスでは、同じ Silvanerのスペルを「シルヴァネール」と発音し、ドイツでも、グリューナー・ジルヴァーナーと呼ばれることがあります。20世紀の初頭、ジルヴァーナーは、ドイツで最も広く栽培されていた白ブドウ品種でしたが、現在は第5位と、大きく順位を下げました。

完熟したジルヴァーナーの房
品種自体の評判は、あまり芳しいとは言えません。香りに華やかさが乏しく、味わいにコクもない、ニュートラルなブドウ、面白みのない品種というのが、一般的な査定です(アルザス地方や、フランケン以外のドイツの産地において、ジルヴァーナーはそう見られています)。リースリングよりも栽培サイクルが早いので、より冷涼な土地向きで、フランケンでジルヴァーナーがリースリングより好まれるのは、主にこの理由からです。酸味は取り立てて強くはないのですが、ボディと骨格が控えめなために、味わいのバランスにおいては相対的に酸が目立ちます。普通に栽培すると、収量が高くなってしまうブドウで、それも味のつまらなさにつながっているようです。
しかしながら、フランケンに植わるジルヴァーナーは例外です。「適地適品種」という言葉のお手本のような、類い希な個性を備えた逸品を、このペアは生み出してくれます。頂きでひときわ強い光を放つのが、ヴュルツブルク村の銘醸畑、シュタイン。ドイツ語で「石」を意味する畑名で、生まれでるワインには畑名から容易に連想される、強烈なミネラル感があります。シュタインの名は、土に石が多く含まれるために付けられたのですが、ワインはまるで石を舐めているかのような味です。香りがとりわけ強いわけでもなければ、リースリングのようにピンと張った強い酸があるわけでもないのですが、飲み手の心に爪痕を残す唯一無二性があります。ヴュルツブルガー・シュタインに限らず、収量が低く抑えられたフランケン産のジルヴァーナーは、テロワールを映す鏡です。長期間の瓶熟成にも耐えるので、もしバック・ヴィンテージのボトルを見つけたら、ぜひ試してみましょう。
ジルヴァーナーがフランケンに到来したのは1659年、シュタイガーヴァルト地区のカステル村へ、オーストリアからやってきました。7世紀からワイン造りをしてきた土地なのを考えると、このブドウが主役になったのは割合最近だとも言えます。ジルヴァーナーは、ドイツで現代的なクローン選抜と育種がなされた最初の品種で、その選抜は1876年頃、ドイツ農業協会で育種登録がなされたのが1922年です。
3. ボックスボイテル:愛されつづけるフランケンワインの伝統的な瓶
フランケンワインの名物は、ジルヴァーナーだけではありません。なんとも言えない形の伝統的な瓶、「ボックスボイテル Bocksbeutel」もまた、この土地の象徴です。平べったいフラスコ型と形容すればよいでしょうか。ボルドー、ブルゴーニュ、ライン川沿いのワイン産地にも、それぞれ伝統的なボトルの形がありますが、ここまで個性的ではありません。実際的には、持ちにくい、注ぎにくい、横積みできない、セラーにうまく入らないなど、欠点だらけの形ではあります。それでも、フランケンのもうひとつの象徴として、生産者からも飲み手からも、愛され続けているボトルです。

フランケン地方で用いられるボックスボイテルのボトル
名前の由来は、「山羊 Bock の陰嚢 Beutel」にちなむという説が広まっていますが、低地ドイツ語(主にドイツ北部で話される方言)の「Bockesbeutel」(祈祷書などを入れる袋)が起源という説も、同じく有力なようです。瓶形自体の歴史は非常に古く、紀元前1400年頃の、ケルト族の陶製容器が起源とされています。ワイン用の瓶としては、ユリウスシュピタール醸造所にある、1576年に掘られた石のレリーフが、最も古い記録のようです。1726年以降、このボトルはヴュルツブルクの市議会によって、町が誇る畑「シュタイン」産のワインが本物だという証明に用いられました。フランケン地方全体に広がったのは、第一次世界大戦のあとです。
近年では、伝統的なスタイルのワインにはボックスボイテルを、ピノ・ノワールほかブルゴーニュ品種の現代的なワインにはブルゴーニュ瓶を、という使い分けが定着してきました。それに伴い、ボックスボイテルの利用率は減少傾向にあり、2018年時点で26%となっています。
2015年には、フランケンワイン生産者連盟が、少しモダンなテイストを入れた新しい型、「ボックスボイテルPS」を発表しました。2020年時点で、全体の3分の2を占めるところまで、この新型瓶は急速に普及しています。しかしながら、後述の高級ワイン生産者連盟VDPは、コストが高くなるなどの理由で、加盟生産者に新型の利用を認めていません。
なお、ボックスボイテルの瓶型はフランケンの専売特許ではなく、ドイツ・バーデン地方の一部地域、イタリアおよびギリシャのごく限られた銘柄においても、EUによって使用が認められています。また、ポルトガル北西部のワインも、似た形のボトル(カンティル Cantil)にワインを詰めることがあり、よく知られているのは、莫大な量が生産されるマテウスという中甘口のロゼワインです。
4. フランケンワインの主要な村と特級畑
ドイツの高級ワインは一般に、ラベルに書かれる銘柄名が、「村+単一畑名」という形で構成されます(ただし、後述の特級畑については、記されるのは畑名だけです)。たとえば、ヴュルツブルガー・シュタイン Würzburger Steinという銘柄名であれば、ヴュルツブルク村(ゲマインデ Gemeinde)のシュタイン畑(アインツェルラーゲ Einzellage)という形に分解できます。フランケン地方には、300を超える行政単位としての村(ゲマインデ)がありますが、ブドウ畑があるのはそのうちおおよそ100。その村々に散らばるのは、213の単一畑です。
ドイツには、最高の畑を所有するエリート生産者が加盟する、VDP(ドイツ高級ワイン生産者連盟)という団体があります。現在、約200のワイナリーがメンバーです。全加盟生産者が所有するブドウ畑の合計は、ドイツ全体のわずか5%に過ぎませんが、その中にドイツで最高のテロワールがことごとく含まれています。このVDP、エリアごとに特級畑(グローセ・ラーゲ Grosse Lage)、一級畑(エアステ・ラーゲ Erste Lage)を格付けしていて、それらは公的な格付けとして、ドイツワイン法のシステムに近年組み入れられました。フランケン地方で認定されているのは、23の特級畑と、52の一級畑です。
ここでは、クリームの中のクリームとして、3つの畑をご紹介します。
筆頭に来るのは当然ながら、マインドライエック地区の中心にある、ヴュルツブルガー・シュタイン (Würzburger Stein)です。ヴュルツブルクの町のすぐ北方に広がる畑は、マイン川を見下ろす急峻な南向きで、主に貝殻石灰岩土壌からなります。この畑のジルヴァーナーこそが、フランケンの象徴、精髄です。かつてフランケン産ワイン一般が、「シュタインワイン」と呼ばれていた事実からも、それは窺えるでしょう。ブドウ栽培が始まったのは、紀元779年頃とされます。シトー会の修道院長によって、この畑にジルヴァーナーが植えられたのは1665年で、当品種がドイツに持ち込まれてから間もないタイミングでした。

マイン川に接するヴュルツブルガー・シュタインの畑
イギリスを代表するワインライターであるヒュー・ジョンソンは、1961年に、この畑の1540年ヴィンテージのワインを試飲しています。瓶詰めの時期は17世紀で、それまでのおおよそ一世紀のあいだ、大樽で熟成が続けられ、蒸発して目減りした分は、新しい年のワインで補填されていました。420年もの歳月を経たワインは、ジョンソン曰く、まだ生きていました。ただし、グラスの中でたちまち、酢になってしまったそうです。
ヴュルツブルガー・シュタインは、総面積85ヘクタールと、かなり大きな単一畑になります。そのため、VDPは格付けにあたって、シュタインの中でも特別に優れたふたつの区画、シュタイン・ベルク(Stein-Berg)とシュタイン・ハルフェ(Stein-Harfe)のみを、特級畑に認定しました(それ以外のシュタインの区画は、一級畑の格付け)。
シュタイガーヴァルト地区でことさらに名高いのが、イプホーファー・ユリウスエヒターベルク(Iphöfer Julius-Echter-Berg)です。イプホーフェンが村の名で、畑名は後述のユリウスシュピタール醸造所にちなんで付けられています。石膏を含む粘土質土壌が特徴で、力強さと優雅さが両立するワインが、その最上の姿です。ジルヴァーナーが代表選手ですが、リースリングやバッカスといった他の白品種にも優品があります。面積は約51ヘクタールで、ほとんどが南向き、35~40%という急勾配です。ヴュルツブルクに本拠地を置くユリウスシュピタール醸造所以外に、イプホーフェン村の有力ワイナリーが複数、この区画を所有しています。
フランケン地方の西の端、マインフィアエック地区は、近年秀逸なピノ・ノワール(シュペートブルグンダー)が高い評価を受けるようになりました。ゲマインデをひとつ選ぶとすると、ビュルクシュタット村(Bürgstädt)になるでしょう。特級畑がふたつあり、その片方のフンスリュック(Hundsruck)は面積11ヘクタール、後述のフュルスト醸造所が、フランケン地方で最高価格のピノを生産しています。35~40%の急傾斜で、やはり南向き、土壌は赤色砂岩質です。もうひとつの特級畑、ツェントグラーフェンベルク(Centgrafenberg)は、フンスリュックの西に隣接していて面積28ヘクタール、同じように南向きで土壌は砂岩質ですが、傾斜は10~40%と幅があります。
5. フランケンワインの主要な生産者
長い歴史の産地であるがゆえ、最高の畑を多く所有する老舗ワイナリーが、高い評価を集めがちです。しかし、フュルスト醸造所のような新しいスターも、次々に誕生してきています。
まずは超の付く老舗から。ユリウスシュピタール醸造所(Weingut Juliusspital)は1576年、もともと社会的弱者のための慈善病院として、ヴュルツブルクの町の中心に建てられました。ブルゴーニュ地方の、オスピス・ド・ボーヌと同じような施設ですが、こちらは今日でも病院、老人ホーム、緩和ケアセンターとしての機能を保持しています。ヴュルツブルクのゲマインデを中心に、フランケン地方全域に180ヘクタールもの畑を所有していて、これはドイツのドメーヌとしては、2番目に大きな規模です。うち、ジルヴァーナーの栽培面積が、70ヘクタールを占めています。前述のヴュルツブルガー・シュタイン、イプホーファー・ユリウスエヒターベルクをはじめとして、一級畑ヴュルツブルガー・インネレ・ライステ(Würzburger Innere Leiste)、特級畑ランデルスアッカー・ホーヘライテ(Randersacker Hoheleite)、一級畑ビュルクシュタッター・マインヘルレ(Bürgstadter Mainhölle)、一級畑エッシャーンドルファー・ルンプ(Escherndorfer Lump)などなどと、錚々たるラインナップです。すべての畑のブドウは、施設の地下にある年代物のセラーで醸されています。

大樽が並ぶユリウスシュピタール醸造所の地下セラー
さらなる老舗が、ビュルガーシュピタール醸造所(Bürgerspital zum Heiligen Geist)です。裕福なヴュルツブルク市民が、公共の病院をと財産を遺贈したのが1316年、建った施設はそのまま「市民病院」(Bürgerspital)と呼ばれるようになりました。こちらもまだ、ワイン造りと医療・老人介護を両立させています。所有する畑は、120ヘクタールとやはり広大です。ヴュルツブルク村では、シュタインの畑の約3分の1(28ヘクール)を持っているほか、一級畑インネレ・ライステ、一級畑プファッフェンベルク(Pfaffenberg)からも白眉と呼べるワインを生産しています。上述した、ヒュー・ジョンソンが飲んだ1540年ヴィンテージのヴュルツブルガー・シュタインは、この蔵で瓶詰めされました。
マインドライエック地区で、ヴュルツブルクの少し東にある村が、エシェルンドルフ(Escherndorf)です。ここでは、ホルスト・ザウアー醸造所(Weingut Horst Sauer)が、小規模ながら素晴らしいワインを造っています。ホルストが、協同組合から抜けて、1.5ヘクタールの畑でワイン造りを始めたのは、1977年とまだ最近です。現在、所有畑は20ヘクタールに近づいていて、ジルヴァーナーだけでなくリースリングも、辛口だけでなく甘口も、世界的な名声を獲得しました。とりわけ、トロッケンベーレンアウスレーゼ(TBA)などの貴腐ワインが、賞賛を受けています。
同じくマインドライエック地区、ヴュルツブルクから南東に10キロほどの場所には、ズルツフェルト・アム・マイン(Sulzfeld am Main)という村があります。ここにも、1961年の設立ながらも、フランケン産ジルヴァーナーの先頭を走るようになった造り手がおり、その名はツェントホフ・ルッケルト醸造所(Weingut Zehnthof Luckert)です。17ヘクタールの畑から生まれるワインの90%は白ワインで、リースリングやピノ・ブラン(ヴァイサー・ブルグンダー)もありますが、等級別、畑別に生産される一連のジルヴァーナーが、間違いなくこの蔵の看板になっています。ズルツフェルト唯一の特級畑、モースタル(Maustal)に植わる樹齢60年超のジルヴァーナーが事実上のエースなのですが、実はそのもうひとつ上に、極めて希少なワインがあります。その名はクロイツ(Creutz)。フィロキセラ禍の前に植えられた、樹齢150年以上の古木が植わる小さな区画です。現存する最古のジルヴァーナーで、アメリカ産の台木に接ぎ木がなされていません。出来上がるワインは、年に500~600本とあまりに少なく、大変な高値がついています。
赤ワインの造り手として、同様に一代で名声を築き挙げたのが、ルドルフ・フュルスト醸造所(Weingut Rudolf Fürst)です。フランケン地方の西側、シュタイガーヴァルト地区にあるビュルクシュタット村に居を構えています。前当主のパウル・フュルストは、1971年にラインガウの名門、シュロス・ヨハニスベルクで修行をし、世界クラスのワインを目指そうと決意しました。しかし、品種はリースリングではなく、ピノ・ノワール(シュペートブルグンダー)。ブルゴーニュ地方の造り手たちと交流をしながら、1989年に始めてピノの赤をリリースしました。そこから評価はうなぎ登り、今では「ピノの魔術師」と呼ばれるまでになっています。2018年に父の跡を継いだ息子のセバスチャンも、天才の誉れ高い醸造家で、フュルスト親子には死角が見当たりません。パウルの独立時、1.5ヘクタールに満たなかった畑は、今では22ヘクタールにまで拡大しました。ビュルクシュタット村のふたつの特級畑、フンスリュック、ツェントグラーフェンベルクと、近隣のゲマインデであるクリンゲンベルク村(Klingenberg)の特級畑シュロスベルク(Schlossberg)から生まれるピノ・ノワールは、世界中のピノ・ノワール好きが狙う垂涎の的です。
6. フランケンワインのまとめ
フランケン産のワインは、日本ではあまり見かけません。日本だけではなく、ロンドンでもニューヨークでも、さらにいえばベルリンでも、あまり見かけないそうです。理由は、生産されるワインのほとんどが、地元で消費されてしまうから。ゲーテは、「つまらないワインを飲むには、人生はあまりに短すぎる」という名言を残しましたが、フランケン地方に暮らす人々は、永眠するまでの限られた時間を、最大限に活用しているようです。
彼の地で生まれる辛口のジルヴァーナーは、ワインの歴史に名を刻む記念碑のひとつであり、今もなお、言葉の真の意味でユニーク、「ほかでは飲めない」味をしています。加えて、新たな顔として舞台に上がってきた、ピノ・ノワールも見逃すべきではないでしょう。フランケンのワインは、妙な形をしたボトルに入っているかもしれませんが、それもまた魅力のひとつです。棚に並んでいれば、イヤでも眼に入ります。機会を損なわず、見つけたらぜひ手にとってみてください。