ワイン愛好家なら、誰もがその名を知っています。世界のワイン用ブドウ品種の中で、栽培面積トップ20にも入っています。「世界一のワイン用ブドウ」 カベルネ・ソーヴィニョンの親という、優れた血脈も誇るべきポイントです。
とはいえ、カベルネ・フラン主体のワインを飲む機会は、決して多くはありません。ボルドーの赤では、脇役。重要なブレンド品種ですが、その比率が5割を超えるのは相当に希です。一方、フランス内でもロワール渓谷中流域では、カベルネ・フランが赤の主役。しかし、「青臭く、酸味が強く、タンニンがギザギザしている」、あまり面白みのない素朴なワインがほとんでした。ほかの産地にも、多少はカベルネ・フラン好きの栽培家・醸造家がいるものの、華やかな光を浴びる存在ではなかったのです。
そのためでしょうか、いつしか単に「カベルネ」または「キャブ」と言えば、カベルネ・ソーヴィニョンを指すようになってしまいました。カベルネ・フランは置いてけぼりです。
ところが近年になり、この不遇は急速に改善されつつあります。もとより、品種としてのポテンシャルは大変に高いブドウだったのです。問題は「熟しにくく、青臭い風味が出やすい」ところだったのですが、地球温暖化で事情が変わりました。
本記事では、カベルネ・フランのワインが持つ共通の香りや味わいの特徴から、その栽培特性、興味深い歴史、さらには世界各地の主要産地と代表的な銘柄、そしてワインを最大限に楽しむためのサービス方法とフードペアリングに至るまで、カベルネ・フランの奥深い世界を徹底的に掘り下げてご紹介いたします。
【目次】
1. カベルネ・フランはどんなワイン?
● 風味の特徴
● スタイルの多様性
2. カベルネ・フランの栽培特性
3. カベルネ・フランの起源と子孫
● カベルネ・フランの起源
● カベルネ・フランの子孫
4. カベルネ・フランの主要産地と代表的銘柄
● フランス ロワール渓谷
● フランス ボルドー地方
● イタリア 北東部・トスカーナ州
● アメリカ合衆国
● その他の産地
5. カベルネ・フランのサービス方法とフードペアリング
● サービス方法
● フードペアリング
6. カベルネ・フランのまとめ
1. カベルネ・フランはどんなワイン?
風味の特徴
カベルネ・フランのワインは、子供にあたるカベルネ・ソーヴィニヨンと、非常によく似ています。ただし、横に並べて飲むと、その違いはまずまず顕著で、フランのほうが、色が若干薄く、ボディは軽め、口あたりが柔らかくてフルーティ、よりアロマティックです。アロマの面では、赤い果実や赤い花が連想され、華やか、あでやかな印象を飲み手に与えてくれます(カベルネ・ソーヴィニョンには、そうした色っぽい香りはあまり感じられません)。タンニンは比較的強健な品種ですが、カベルネ・ソーヴィニョンほどではありません。逆に酸味は、カベルネ・ソーヴィニョンより目立ちます。長熟型ワインに仕立てたときの寿命は、一般論としてはカベルネ・ソーヴィニョンより短いですが、シュヴァル・ブラン、ラフルールといった非常に長い命をもつ例外も、珍しくはありません。

カベルネ・フランの葉。親子だけあって、カベルネ・ソーヴィニョンの葉とそっくり。フランのほうが切れ込みが若干浅いのが、判別のポイント
カベルネ・フランのアロマで特徴的なのは、ピーマンや青草と表現される、青っぽい香りであり、これはメトキシピラジンという香り物質が原因です(正式名称は、3-イソブチル-2-メトキシピラジン、略称IBMP、単に「ピラジン」と呼ばれもします)。この化合物には、ブドウが熟するにつれて減っていく性質があります。よく熟したカベルネ・フランから造られたワインにも、少量の、あるいはごくごくわずかなメトキシピラジンは感じられまずが、その場合はワインに独特の清涼感を与えてくれる、プラス要素となります。ところが、畑の気候が冷涼であったり、温暖でも収量が多すぎたりすると、カベルネ・フランは完熟せず、メトキシピラジンがどっさりワインに残る事態に。そうしたワインは、「青臭い」、「野菜のようだ」と表現され、大多数の飲み手には好かれないようです。
カベルネ・ソーヴィニョン、メルロといった、ほかのボルドー赤品種でも、未熟だとこのピラジンがワインに現れるものの、フランほどは目立ちません。なお、ヨーロッパの飲み手は、比較的このメトキシピラジンに寛容なのですが、それは1970年代までのボルドー赤には、程度の差はあれ必ずこの香りが見られたからです。若いうちは多少青臭くても、熟成すれば複雑なブーケの中に統合されて、趣を添える一要素だと考えられてきました。一方、新世界の飲み手たちは、このピラジンを嫌います。ワイン・コンクールなどでも、新世界の国で開催される場合、ピラジンが顕在的なワインは、欠陥品として低い評価しか得られません。
スタイルの多様性
カベルネ・フランは、冷涼な産地でも、温暖な産地でも栽培されるブドウですが、気候によってそのスタイルや仕込みの流儀が変わります。
まず、フランスのロワール渓谷中流域のような冷涼気候の産地では、カベルネ・フランはより軽やかなボディで、タンニンも控えめな赤ワインとなります(アンジュー地区では、この品種を使ったロゼワイン、AOCカベルネ・ダンジューの生産量も少なくありません)。ロワールのフラン赤は、赤い果実のフレーバー、花の香り、そしてハーブの側面が強調されます。軽やかなピノ・ノワールや、ボージョレとスタイル的には共通点があるでしょう。ロワールでは多様な土壌にフランが植わっていますが、砂質、砂利、石灰質でそれぞれ表現に違いがあり、特に石灰質土壌からは、素晴らしい熟成能力を持つワインが生まれるとされます。
ロワールのカベルネ・フラン赤は、一般的にステンレスタンクなどニュートラルな容器で短期間熟成されたのち、瓶詰めされて市場に出ます。一方で、優れた造り手の上級銘柄は、ほとんどの場合は樽熟成を行なっていて、中には新樽が用いられる銘柄もあります。とはいえ、濃厚なワインが好まれた1990年代から2000年代と比べると、新樽の使用は明らかに減っていて、中には樽熟成そのものを止めて、高級銘柄を含めてステンレスタンク熟成に戻した造り手さえいます。アルコール発酵中の抽出についても同様で、かつてはタンニンをしっかり抽出すべく、強いピジャージュや、頻度の高いルモンタージュが行なわれていましたが、状況が変わりました。昨今は、「インフュージョン」と呼ばれる抽出方法が流行りで、これは果帽を液内に沈めた状態を保ち、じわじわと色素やタンニンが出てくるのを待つという方式です(ピジャージュやルモンタージュは行ないません)。

ボルドーでのカベルネ・フランは、仲間の品種であるカベルネ・ソーヴィニョンやメルロなどと、スタイル的に大きくは違いません(風味には、上述の際立った特徴がありますが)。つまり、ロワールよりはボディが強く、骨格もしっかりしたワインになるのです。高級シャトーでは、新樽を含むバリック(容量225リットルの小樽)で熟成されるのが常ですが、最近はアンフォラや、コンクリート製の卵型容器(コンクリート・エッグ)でも、ワインの一部が寝かされています。抽出方法は、こちらも他の仲間品種と同じくルモンタージュが主ですが、一時期と比べて、ボルドーでもより穏やかにという方向にシフトしてきました。
イタリアのトスカーナ州(特に海岸沿いのボルゲリ、マレンマ地区)や、アメリカのカリフォルニア州のような温暖な気候の地域では、ブドウがよく熟すので、ヘヴィィでアルコールも高く、飲み応え十分なスタイルになります(それでも、華やかなアロマティクスは失われません)。熟成容器や抽出方法については、ボルドーとほぼ変わりません。
2. カベルネ・フランの栽培特性
カベルネ・フランは、幅広い土壌と気候に適合し、比較的栽培しやすい品種になります。気候については、ロワール渓谷中流域、アメリカ合衆国ニューヨーク州フィンガー・レイクス地区、カナダのオンタリオ州といったかなり冷涼な産地から、ボルドーのように中庸な温度の産地、アメリカのカリフォルニア州やワシントン州といったかなり温暖な産地までと、守備範囲は広いです(冷涼な気候では完熟しないカベルネ・ソーヴィニョンに、その点では勝ります)。土壌については、粘土石灰質土壌が最良とされますが、水分ストレスが過度でなければ、砂質土壌でも悪い結果にはなりません。
地球規模の気候変動・気温上昇の、恩恵を受けている品種だとされます(今のところは、という留保がつきますが)。ロワールのような冷涼地域でも、よりブドウが完熟しやすくなりました。ピラジンの風味が後ろに引っ込むようになって、好ましい華やかなアロマが前面に出てきたのです。ボルドーにおいても、フランより早熟なメルロが過熟の問題を抱えるようになり、その存在価値が見直されてきています。夏の酷暑、収穫期の雨といった忌むべき天候イベントにも、立ち向かえる力があると評価す造り手もいて、フランス以外の産地でも関心が高まってきました。
生育サイクルは早くも遅くもなく、ボルドーではメルロより遅く、カベルネ・ソーヴィニョンより早く発芽し、収穫時期も同様です。糖度、酸度、色とタンニン量については、全品種の中では中程度とされます。

病虫害については、灰色カビ病へは中程度の耐性をもち、ユータイパやエスカといった幹を冒す病気への耐性も中程度です。葉から樹液を吸汁するヨコバイの耐性は、強くありません。
房の大きさは中程度、果粒は小さいです。クローンにもよりますが、果粒どうしの密着度合いはさほどでもありません。フランスでは、31のクローンが公式に認定されています。収量はクローンによってかなり差があり、ロワールで生産される軽い安価なフランで使われるのは、一般に高収量のクローンです(そのため、ピラジンの青臭い風味が前に出てしまいます)。樹勢もクローンによるものの、総じて言えばやや強めで、その勢いを落ち着かせるために、高い樹齢の木が重宝されます。
3. カベルネ・フランの起源と子孫
カベルネ・フランの起源
ボルドー地方で古くから栽培されているブドウ品種で、それはカベルネ・ソーヴィニョンほかの品種の「親」であるという事実からも伺い知れます。しかしながら、生誕の地はボルドーではなく、スペインのバスク地方(フランスとの国境の南側の地域)だと考える識者たちが、遺伝学的にも歴史学的にも主流です。裏付けのひとつは、カベルネ・フランと、バスク地方の非常に古いブドウ品種ふたつが、親子関係にあるという事実になります。
文献に残る最古の記述は、16世紀のロワールを生きた文人フランソワ・ラブレーによる文章です。代表作のひとつ『ガルガンチュア物語』の中に、「ブルトン」という古い異名が記されています。確からしい筋書きは、ボルドーのカベルネ・フランが、大西洋沿いに北上してブルターニュ地方(ロワール河口のすぐ北に位置する、大西洋に突き出た半島)へ移植され、そこからロワール河に沿って上流へ(東へと)栽培地域を広げ、経由地ブルターニュにちなんで「ブルトン」と呼ばれるようになったというもの。いくつか異論・異説はありますが、このストーリーが一番自然に感じられます。なお、「カベルネ」の語源についても議論はまとまっていませんが、有力なのは、ラテン語で「黒」を意味する「カルボン Carbon」から来ているという説で、果皮の黒さからの名付けだろうという推測です。
ボルドー地方において、カベルネ・フランが文献ではっきりと言及されたのは、18世紀の終わりと比較的最近になってからでした。右岸のサンテミリオン、ポムロール、フロンサックといった地区で、高品質のワインを生むと、記されています。
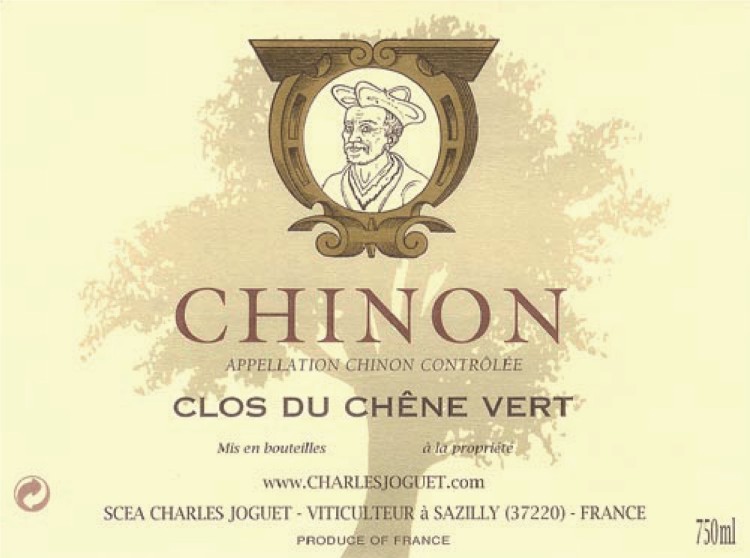
シノンを代表する生産者、シャルル・ジョゲのラベル。同地に生まれたラブレーの肖像が描かれている
カベルネ・フランの子孫
起源が古いブドウ品種だけあって、カベルネ・フランは多くのボルドー系赤品種の親または血族にあたります。子供品種の中で最も有名なのが、カベルネ・ソーヴィニョン。もう片親は白ブドウのソーヴィニョン・ブランで、ブドウ品種のDNA鑑定黎明期の1997年、カリフォルニア大学デイヴィス校のキャロル・メレディス教授のチームが解明しました。子供が両親の姓名をひとつずつ受け継ぐ構図になっていたため、世紀の大発見にもかかわらず、「そんなの前からわかっていた」という感じの反応が多かったようです。しかし、これは単なる偶然。そもそも、「ソーヴィニョン」という言葉は、フランス語で野生を意味する「ソヴァージュ Sauvage」からの派生で、ソーヴィニョン・ブランとは「野生の白ブドウ」という、「そんなの何にでもあてはまるじゃん」的な漠たる名前でしかないのです。
フランスで最も広く栽培されている黒ブドウのメルロも、カベルネ・フランから生まれました。もう片親は、マグドレーヌ・ノワール・デ・シャラントという、今ではもう、ほぼ栽培されていない黒ブドウです。ボルドーでは廃れたものの、チリで象徴品種となったカルメネールもそう。カベルネ・フランと、トゥルソー(またはグロ・カベルネ)の自然交配で誕生しました。
4. カベルネ・フランの主要産地と代表的銘柄
フランス ロワール渓谷
高級銘柄の数や実勢価格の高さをさておけば、世界で最もカベルネ・フランを大切にしている産地は、ロワールの中流域です。かつては、気候的に果実を完熟させるのが困難だったため、青臭く悦びの少ないワインが大半を占めていました。しかしそれも過去の話、地球温暖化で状況が大きく改善されました。栽培面での努力や工夫(収量抑制など)、仕込みの洗練(前述)も、品質向上の大きな要因です。
フランス全土で栽培されるカベルネ・フランのうち、約30%がロワール渓谷に植わっています。赤が名高いAOCは、ロワール渓谷内アンジュー・ソミュール地区のソミュール・シャンピニー、同トゥーレーヌ地区のシノン、ブルグイユ、サン・ニコラ・ド・ブルグイユの4つに絞られるでしょう(4つのAOCはふたつの地区にまたがっていますが、すべて地区の境界線付近に集まっていて、一続きです)。どのAOCでも規定上は、カベルネ・フラン以外に、カベルネ・ソーヴィニョンをブレンドに含められます。しかし、後者は冷涼なロワールでは完熟しないので、少量だとしても実際に使われるのは希です。
4つある赤ワインの主要AOCのうち、26の村を包摂し、最も面積が大きいのがシノン。広いため、平野部、斜面部、標高の高い台地の頂点部の3つに大別され、斜面部の石灰質土壌の畑から、最良のワインが生まれます。軽めのスタイルから、10年以上の長期熟成が可能な本格派まであり、後者のグループではテロワールの表現を追求するために、単一畑や単一エリアでの瓶詰めをする造り手が多いです。シノンはまた、百年戦争中の1429年に、神のお告げを受けた少女ジャンヌ・ダルクが、シャルル王太子(後の国王シャルル7世)に謁見した城がある土地として、観光名所にもなっています。代表的な生産者は、シャルル・ジョゲ、クーリィ・デュテイユ、ベルナール・ボードリー、フィリップ・アリエなど。

ヴィエンヌ河畔に広がるシノンのブドウ畑
シノンとロワール川を挟んで向き合うのが、ブルグイユとサン・ニコラ・ド・ブルグイユの両AOC。テロワールには明確な差はなく、「大人の事情」でふたつに分割されたと言われます。この地域も、それぞれ土壌、方位などが多様なうえ、両AOCに同じ土壌が見られたりもするので、分ける意味を見つけるのが難しいです。代表的生産者は、サン・ニコラに本拠を置くのがイャニック・アミロで、ふたつのAOCの両方から、長期熟成型の目覚ましいワインを造ります。ブルグイユのワイナリーでは、カトリーヌ&ピエール・ブルトンが名高いです。

ブルグイユの町名表示プレート。3.5キロ先がサン・ニコラ・ド・ブルグイユだともわかる
アンジュー・ソミュール地区の東端にあって、シノン、ブルグイユ、サン・ニコラ・ド・ブルグイユに向かい合うのが、ソミュール・シャンピニー。ここには、「ロワール最高の赤ワイン生産者」の誉れも高い、クロ・ルジャールがいます。かつての所有者であったシャルリーとベルナールのフーコー兄弟は、1960年代末に親からワイン造りを引継ぎ、慣行農法(人工化学物質に頼る農法)真っ盛りの時代から、実質的な有機栽培を行なっていました。また、区画ごとの個性に光を当て、小樽で熟成させた単一区画のワイン(レ・ポワイユー、ル・ブール)を生産していました。2015年、兄のシャルリーの逝去にともない、ボルドーのシャトー・モンローズの所有者であるブイグ兄弟に蔵が売却されましたが、その後も名声に陰りはありません。価格面では、むしろ売却後のほうが上昇が著しく、トップ・キュヴェのル・ブールは現在、国際小売価格で税抜6~7万円もします(1990年代後半、日本市場での小売価格は5000円未満でした)。完全なカルトと化していて、こんな価格を付けるロワール産カベルネ・フランは、他にはありません。クロ・ルジャール以外ではドメーヌ・デ・ロッシュ・ヌーヴが、このAOCで評価の高い生産者です。
上記4つのAOCの風味の差については、あれこれ語られてはいるものの、AOC内での共通点よりも、醸造・熟成方法の共通点、土壌の共通点によるスタイルの類似のほうが目立つ、というのが実情です。
フランス ボルドー地方
ロワールとほぼ同量、フランス全体の30%強が植わっていますが、赤ワインの主要品種に採用されている銘柄は希です。しかしながら、カベルネ・フランをブレンドすると、ワイン全体をフレッシュにしつつ、アロマを持ち上げてくれます。かつ、生育サイクルが、メルロとカベルネ・ソーヴィニョンの中間にあるという使い勝手の良さもあるので、脇役としての地位は磐石です。
ボルドー地方内黒ブドウ品種の面積比では9%で、1位のメルロ(66%)、2位のカベルネ・ソーヴィニョン(22%)に、大きく水をあけられています。しかしながら、温暖化の影響で、メルロの栽培がボルドーでは少々厳しくなってきていますから(過熟になりやすい)、この先、カベルネ・フランの植栽比率が増えていく可能性は小さくないでしょう(すでに、そうしたアクションを起こしているシャトーも、複数あります)。エリア別で見ると、比較的冷涼な右岸で、カベルネ・フランが多く畑に植えられています。これは、左岸ではより晩熟なカベルネ・ソーヴィニョンが完熟するため、あるいは右岸ではカベルネ・ソーヴィニョンが完熟しづらいためです。興味深いのは、1960年代後半時点のボルドー地方においては、カベルネ・フランとカベルネ・ソーヴィニョンの面積が、ほぼ同じだったという事実でしょう。これはその後の時代に、収益性の低い白ブドウを植え替えるにあたって、カベルネ・ソーヴィニョンが選ばれたからだと説明されています。
左岸はもちろん、右岸においても、カベルネ・フランがブレンドの3分の1以上を占めている銘柄は希です。とはいえ、カベルネ・フランを重宝する数少ないシャトーが、揃って大物なのは、この品種の潜在性を示しているように思われます。まず、サンテミリオンのツートップ、シュヴァル・ブランとオーゾンヌ。このふたつのシャトーは、畑の植栽比率において、カベルネ・フランが50%を超えています。グラン・ヴァンのブレンドにおける品種構成は毎年異なり、年によってはメルロが多くなりますが、それでも高い比率でカベルネ・フランが使われているのは変わりません。

シャトー・シュヴァル・ブランのブドウ畑
サンテミリオンでツートップに次ぐ存在、アンジェリュスもまた、カベルネ・フランを重用するシャトーです。グラン・ヴァンで、ヴィンテージによってはカベルネ・フランが5割を超えるほか、「オマージュ・ア・エリザベス・ブローシェ」というカベルネ・フランのみのスペシャル・キュヴェを生産しています。この「オマージュ…」は、樹齢60~80年の古木だけを使うので、生産量がとても少なく(年産1500~3000本)、かつ優れた作柄の年にしか仕込まれません。そのために極めて高価になってしまい、現在の国際小売価格は、税抜24万円ほど。カベルネ・フラン主体のワインとしては、世界一の高値です。
このほか、ボルドー右岸でカベルネ・フランが多く用いられている銘柄として、サンテミリオンのル・ドーム、トロットヴィエイユ、ポムロールのラフルールがあります。左岸での珍しい例としては、過去10~15年ほどで、格付け外ながらもグラーヴ地区有数の赤ワインへと成り上がった、レ・カルム・オー・ブリオンを知っておくべきでしょう。
ボルドー地方の南、スペイン国境付近まで広がる南西地方でも、カベルネ・フランは少し栽培されていますが、やはり他の黒ブドウの脇を固める役割で、顔にはなっていません。
イタリア 北東部・トスカーナ州
イタリアは、フランスに次ぐカベルネ・フランの生産国ですが、面積は6分の1程度と、ずいぶんスケールが小さくなります。大半が、ヴェネト州およびフリウリ・ヴェネツィア・ジューリア州の、北東部2州に植わっていますが、トスカーナ州の畑も無視できない広さです(とくにティレニア海沿岸のエリア)。
北東部のカベルネ・フランは、完熟させるのが難しい冷涼な気候、多すぎる収量という、かつてのロワールと同じ問題を抱えていて、今のところスーパースターは誕生していません。品質評価では、トスカーナのフランのほうが明らかに高く、ボルドー・ブレンドで助演するほかに、主演作品が喝采を受けている例がパラパラとあります。有名どころでは、レ・マッキオーレのパレオ・ロッソ、グアド・アル・タッソのマタロッキオ、ドゥエマーニのドゥエマーニ、テヌータ・ディ・トリノーロのカンポ・ディ・マニャコスタなど。
アメリカ合衆国
カリフォルニア州には、2020年時点で1400ヘクタールほどの面積があり、ナパ、ソノマ、サン・ルイス・オビスポの各郡に集中しています。この3郡は、いずれもカベルネ・ソーヴィニョンの植栽が多く、したがってフランは、ブレンディング・パートナーとしての役割が主です。高額品だと、ナパのダラ・ヴァレのフラッグシップワインであるマヤや、ヴィアディアのグラン・ヴァンは、フランのブレンド比率が3分の1以上と、相対的に高いのが知られています。このほか、ナパのレアム・セラーズが造る、ベックストーファー・ト・カロン・カベルネ・フランは、国際小売価格が税抜10万円を超えるカルトワイン。カリフォルニア産のカベルネ・フランは、温暖な気候でブドウが完熟に到るので、ピラジンの風味はほぼ感じられず、華やかさは失われないものの、濃密なスタイルです。
一方、清涼感に満ちたカベルネ・フランを積極的に造るが、ニューヨーク州です。ボルドーと同程度の温暖さをもつロング・アイランド地区のみならず、もっと冷涼なフィンガー・レイクス地区でも、カベルネ・フランは注力・注目すべき品種だと、造り手たちにも飲み手たちにも認知されています。気温上昇の恩恵を受けているのは、ニューヨークも同じで、過去10~15年でカベルネ・フランの品質は確実な上昇を見せてきました。

フィンガー・レイクス地区を代表するワイナリーのひとつ、ハーマン・J・ウィーマーの栽培醸造責任者、フレッド・マーワース。リースリングが有名なワイナリーだが、赤のフラッグシップであるカベルネ・フランも、優れた品質で知られる
その他の産地
カナダのオンタリオ州では、カベルネ・フランを使ったアイスワインを生産しており、希少性もあって高値がついています。同地を代表するワイナリー、イニスキリンの品が高名です。南米ではアルゼンチンで、カベルネ・フランの栽培面積が急激に増えてきました。カテナ・ザパータ、ボデガ・アレアンナが、品種名表示のカベルネ・フランを瓶詰めしており、いずれも高評価です。南アフリカでも、カベルネ・フランの植栽はハイペースで増えています。ステレンボッシュの新星、ラーツ・ファミリーの造るカベルネ・フラン100%の銘柄は、評価が高いです。
5. カベルネ・フランのサービス方法とフードペアリング
サービス方法
ワイン産地や生産者によって、スタイルに幅があるので、サービス温度も15~20℃と幅が生まれます。軽いタイプは低めの温度で楽しみ、濃密なタイプになるほど、温度を高くしてやるといいでしょう。華やかなアロマを楽しむべき品種なので、温度を高くしすぎても(アルコールの刺激臭が強くなる)、低くしすぎても(香りの分子が揮発しなくなり)、いけません。
ワイングラスについては、香りを十分に引き出してくれる、ボウル部分が大きめのグラスを使ってください。ボルドー品種ですので、形状はいわゆるボルドー型が定番にはなります。ただし、ロワール産やニューヨーク州フィンガー・レイクス産など、比較的線が細い赤ワインならば、ブルゴーニュ型を使うのも面白いです。
デキャンタージュは、澱のある古酒については積極的に行ないましょう。若い銘柄については、ロワール産など冷涼系は、典型的なスタイルである限りは必要ありません。一方、骨格の強いボルドー産、ナパ産、トスカーナ産などは、通気によって香りが開く効果が期待できます。
フードペアリング
これまたスタイルに幅があるので、一概には言えません。ただ、骨格が非常に強いカベルネ・ソーヴィニョン、果実味が前にぐっと出るメルロと比すると、中庸の美徳で守備範囲が広いほうです。ざっくり肉料理全般、風味が強めのチーズ全般によく合いますが、ピラジン由来の「青み」を、食材のグリーンなニュアンスや、ハーブに合わせるペアリングがよく提案されています。例えば、肉料理でも、子羊のローストにローズマリーで風味付けした一皿。家庭料理だと「ピーマンの肉詰め」が、ピーマンがそのままブリッジになるので、定番です。チンジャオロースも左に同じ。和の料理だと、鰻の蒲焼きも好んで合わされています。振りかけられた山椒がポイントです。
6. カベルネ・フランのまとめ
ブドウ品種の世界でも、どれが成功し、どれが不遇をかこつかには、運が影響します。家柄がよくても、実力があっても、それだけでスターになれるとは限りません。典型例と言ってよいのが、この記事でとりあげたカベルネ・フランでしょう。なかなか芽が出ず、下積み生活は長かった。さはさりながら、です。実力がありさえすれば、いつか出番が回ってきて、世間に認められる巡り合わせもあります。待てば海路の日和あり、カベルネ・フランにはようやくその時が来たようです。飲むべきワインは、すでに多数あります。この記事を道しるべにしながら、遅咲きのスターの栓を開け、喝采を送ってあげてください。















