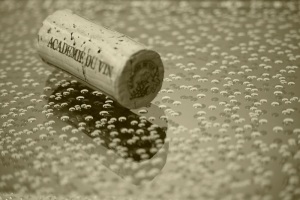俳優、ミュージシャン、スポーツ選手といった、有名人(セレブリティ)の名を冠したワインが増え続けている。そういうビジネスモデルは、すでにおなじみのものだ。三つ星シェフが監修した冷凍食品、スーパーモデルがプロデュースするアパレルブランドなどなど。「名前を貸しているだけで、事実上何もしていない」ケースから、「本業そっちのけで、のめりこんでいる」ケースまで、セレブの関与度合いもさまざまである。
本記事では、セレブリティが関与するワインについて、その起源、メリットとデメリットなどを整理した上で、主要なブランドを紹介する。
【目次】
1. セレブリティ・ブランドとはなにか?
● 起源と変遷
● 狙いとメリット、デメリット
2. ワインとセレブリティ
● なぜセレブはワインを選ぶのか
● セレブ本人の関与の度合い
3. セレブリティ・ワインのブランド紹介
● 俳優のブランド
● ミュージシャンのブランド
● スポーツ選手のブランド
● その他のセレブのブランド
4. おわりに
1. セレブリティ・ブランドとはなにか?
起源と変遷
有名人が商品の広告塔になるという座組みは、なかなかに長い歴史がある。たとえば、英国の陶磁器メーカーでのウェッジウッドは、18世紀に「王室御用達」を宣伝文句に商売をした。日本でも、宮内省が1891年(明治24年)、「宮内省御用達」を制度化したのが類似の事例だ(1954年に廃止)。「あんなに偉い人が使っているのだから、たいそう良いものだろう」という、権威による箔付けが、その手法の根本にある。
現代的な意味でのセレブリティ・プロモーションの始まりは、19世紀末にロンドンの舞台俳優リリー・ラングトリーが、石鹸の広告に登場した事例あたりだろう。20世紀に入ると、この潮流はスポーツ界にも広がり、メジャーリーグ・ベースボールの大スター、ベーブ・ルースが清涼飲料水の広告に起用された。天上人の権威以外に、世俗の成功者への憧れも、商品購入の動機となるのがマーケッターに理解され始める。ただ、この時点ではまだ、セレブの関与は広告への顔出しに留まっており、商品とひとつになったブランドではなかった。
ゲームチェンジャーとなったのは、神と呼ばれたバスケットボール選手、NBAのマイケル・ジョーダンだ。スポーツ関連商品の製造業者ナイキは、1984年に「エア・ジョーダン」という名のバスケットボール・シューズを発売した。このときナイキは、広告への起用のみならず、製品そのものにジョーダンの名を付け、その全人格を埋め込んだ。セレブリティのカリスマ性や美学、ライフスタイルと一体化した商品を創造するという、新しいビジネスモデルの誕生だった。エア・ジョーダンはシリーズ化され、1990年代末までに14モデルが発売、莫大な富をナイキとジョーダンにもたらした。もともとは、バスケ選手が履く靴だったのが、ファッションアイテムとなり、一般人が争って購入した結果だった。

1984年に発売されたエア・ジョーダンの初モデル(エア・ジョーダン1)
狙いとメリット、デメリット
セレブリティのブランドには、製造業者が有名人を起用する場合と、有名人側から業者に働きかける場合がある。いずれでも、狙いやメリット、デメリットはそう変わらない。
まずは製造業者側のメリットから。最も直接的なのは、莫大なフォロワーを持つセレブの知名度を利用した、即時の認知度獲得である。ブランドは短期間で耳目を集め、市場への参入を加速させられる。製造業者のチャネルによる広告やプロモーションに加え、セレブのSNSフォロワーに直接働きかけてもらえば、ファンの塊が一気に動くのも期待できる。
次に重要なのは、セレブがまとうポジティブなイメージを、商品に投影できる点だ。上述のエア・ジョーダンの靴のほか、たとえば俳優ジョージ・クルーニーとネスプレッソの提携では、クルーニーの洗練されたイメージが、ブランドの高級感を高めた。新しい顧客層、多くの場合は若年者を取り込むのも目的のひとつだ。歌手テイラー・スウィフトが、ダイエット・コーラと提携したのは、その顕著な成功例だろう。
セレブリティ側にも、提携相手の業者が適切ならば、大きなメリットがもたらされる。まずは、新しい収益源の確保だ。セレブ自身がどれだけ手を動かすかにもよるが、端的に言ってボロい。名前を貸すだけなら、ほぼ不労所得である。セレブ自身の哲学を反映した商品を通じ、ファンに新たな付加価値や、本業とは違う自己表現を提供できるのも、副次的なメリットだろう。セレブ・ブランド商品の販売を慈善事業にし、セレブ本人の名声が高まったケースもある。俳優ポール・ニューマンが自ら立ち上げた食品加工会社、ニューマンズ・オウンは、純利益の総額を慈善団体に寄付するユニークなブランドだ。ニューマンは2008年に死没したが、ブランドは今も継続していて、2022年までの累積で、6億ドルもの寄付がなされている。

ポール・ニューマン(1958年撮影)
ただし、業者側にもセレブ側にも、デメリットやリスクは存在する。ただちに頭に浮かぶのが、セレブがスキャンダルや不祥事を起こした際の、甚大な被害であろう。ブランドイメージは地に落ち、商品は売れなくなる。多くの場合、業者からセレブに対して違約金の支払いが求められるだろう。ただし、金銭での補償がなされても、業者側に生じるイメージ毀損の影響は、他の商品にまで及ぶ。そもそも業者には、セレブ起用の時点で小さくない金銭的リスクがある。高額な提携料に見合う売上・利益が生じるかは、実際にモノを売ってみないとわからないからだ。
顧客の側では、「同等品質の他のブランドより割高」になりやすいのが、一番のデメリットだろう。製造業者がセレブに支払う「名前料」は、ほとんどの場合、販売価格に上乗せされる。セレブの威光によって売上と利益が十分に増えるのなら、値上げしなくても名前料が回収できるときもあるだろう。ただしそれは例外に留まる。なぜならセレブの「名前料」はあらかじめ、予想される売上と利益に応じて設定されるからだ。
2. ワインとセレブリティ
なぜセレブはワインを選ぶのか
セレブが関与する製品は、多岐に及ぶ。ワインの占める割合がとりわけ大きいとは言えないが、あえてセレブに選ばれるのにはいくつか理由が考えられる。
まず、ワインにからまる歴史的背景と、「成功の象徴」としてのステイタスだ。ヨーロッパの歴史において、ワインは庶民の「水代わり」でもあったが、王侯貴族や高位聖職者の権力・富のシンボルでもあった。たとえば太陽王ルイ十四世が、ことさらに高価で希少なワインを好んだのは、よく知られている。

ふたつめは、芸術性あるいはロマンだ。ワインは、単なる工業製品ではない。畑のテロワール、年々の気候、ブドウ品種、そして醸造家の哲学が融合して生まれ出る。それを「芸術」と呼ぶかはともかく、ロマンティックなアイテムなのは間違いない。セレブリティ、とりわけ表現者(俳優、ミュージシャンなど)にとって、ワイン生産というロマンを追求するプロセスは、自身の創造性や感性を表現する新たな舞台となる。地球環境への配慮が声高に叫ばれる現代においては、「土に還る」という含意が、人々に刺さる面もあるだろう。
みっつめは、洗練されたライフスタイルとの親和性だ。「ワインはオシャレか?」という問いに対する答えは、国や世代で大きく違う。とはいえ、一部の市場ではいまだ、ワインは優雅な暮らしを構成する有力なアイテムである。パートナーや友人との普段の食事から、特別な日の乾杯まで、買い手・飲み手は、憧れのセレブの豊かさに自分を重ねられる。セレブが関与するワインの価格自体は、カジュアルなロゼから高額のシャンパーニュまで幅があるものの、豊かさや洗練といったコンセプトは、すべてに通底している。
かように、ワインはセレブにとって魅力的な商材なのだが、特有のリスクがないわけではない。ワインは、専門性が高い消費財である。顧客、とくにヘビーユーザーには、マニアあるいはオタクと呼ばれる人種が多い。こうした層は、セレブリティの「本気度」を厳しく査定する。単なる「名前貸し」と見なされれば、買ってはくれない。比較的廉価なワインであれば、コア層にそっぽを向かれても商売は成り立つが、高額品だとそうもいかない。
セレブ本人の関与の度合い
ワインに向けられたセレブの「本気度」は、3つの類型で推し量れるだろう。
まず、「名前貸し」に近いモデルから。こちらでは、セレブは当該ブランドの顔として広告に出演したり、製品に自身の名前を冠したりはするが、ブドウ栽培やワイン醸造には、ほとんどあるいはまったく関与しない。セレブにとっては最もお手軽である。ワインに対して、1ミリリットルの愛情がなくても(あるいはアルコールを一切口にしない人でも)、このモデルであれば成立する。
次は「プロデュース型」。ブドウ畑やワイナリーをセレブ本人が所有はしないものの、本業の醸造家と密に連携し、ブレンドやラベルデザインに深く関わる。「名前貸し」モデルと比べて、相当に本気度が高くなる形態だ。ワインへの愛情が強いのは前提である。本職の栽培家や醸造家と対話する必要があるから、製造工程をある程度は理解し、専門用語にも通じていなければならない。
最後は、「オーナー型」である。豊富な個人資産を投下して、自分のワイナリーあるいはブランドを持ってしまう。ワイン造り、ワイナリー経営については、専業のプロを雇う場合がほとんどだが、セレブ本人もかなり深くまで立ち入る場合が多い。栽培や醸造の肉体労働に、自ら進んで参加したりもする。もちろん中には、「見せびらかすためのトロフィー」、「税金対策」といったよこしまな目的で、ワイナリーを保有している者もいるだろう。一方で、ワインがたまらなく好きでのめり込み、どちらが本業が判然としないような有名人もいる。
3. セレブリティ・ワインのブランド紹介
俳優のブランド
いろんな意味で筆頭にあがるのが、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』などが代表作のブラッド・ピットだ。オーナーとして所有するシャトー・ミラヴァル(Château Miraval)は、フランス・プロヴァンス地方にあり、敷地面積は600ヘクタールと広大である(ブドウ畑はその一部)。シャトーヌフ・デュ・パプの超名門生産者、ペラン・ファミリーが技術面の世話をしている。ブラッド・ピットの本気度は高く、たびたびシャトーを訪れては、栽培・醸造作業に携わっているらしい。ブランド名にあえて、ピットの名前を入れていないのも、本気度の表れだろう。2008年の購入時は、元妻であるアンジェリーナ・ジョリーとの共同名義だった。夫妻の離婚に伴い、持ち分を巡るややこしい法廷闘争が勃発し、今も続いている。スキャンダル発生リスクのお手本的事例だが、製品の完成度が高いせいか、シャトー・ミラヴァルのワイン、特にロゼは世界中で売れに売れ続けている。サンソー、グルナッシュなど南仏品種をブレンドした本格派のロゼで、日本市場での実勢価格が5000円前後(2025年時点)とかなり高額なのに、無問題なようだ。

ブラッド・ピット(2024年撮影)ⒸHarald Krichel
『シラノ・ド・ベルジュラック』のシラノ役などで知られる、フランスの名優ジェラール・ドパルデューも、本気のオーナー型だ。フランス・ロワール地方、アンジュー地区にあって、長い歴史をもつシャトー・ド・ティニェ(Château de Tigné)を、1989年に買収した。アンジューの伝統品種であるカベルネ・フラン、カベルネ・ソーヴィニョン、グロロー、シュナン・ブランのほか、ピノ・ノワール、シラー、シャルドネといった国際品種も栽培している(主に中価格帯)。ドパルデューは、栽培、醸造に関わるだけでなく、ワインの国際見本市でもブースに立っているらしい。至近距離で本人からワインを注いでもらい、説明してもらえる機会は、ファンにはたまらないだろう。

ジェラール・ドパルデュー(2010年撮影)ⒸSiebbi
『ブルー・ベルベット』、『ツイン・ピークス』などで知られるカイル・マクラクランは、故郷であるアメリカ・ワシントン州でワインを造っている。ブドウ畑や醸造設備は持たないが、ブランドは自身で経営しているので、どちらかといえばオーナー型だ。ブランド名のパースード・バイ・ベア(…pursued by bear)は、シェイクスピア戯曲にちなんでいて、舞台俳優としても活躍したマクラクランの思い入れが詰まっている。ワインは3種類で、プロヴァンス風のロゼと、本格派のカベルネ・ソーヴィニョンおよびシラーの赤だ。ロゼはお値頃だが、赤は高額である。マクラクランにワインの味を教えたのは、上記作品で監督を務めた、名匠デヴィッド・リンチだという。醸造は、同州ワラワラ・ヴァレーのトップ生産者のひとつ、ダンハム・セラーの設備を借りて行なっている。専業の醸造家を雇ってはいるが、マクラクラン本人も、両手を紫色に染めて仕込みに携わる。

カイル・マクラクラン(2011年撮影)ⒸDavid Shankbone
『セックス・アンド・ザ・シティ』の主役で知られるサラ・ジェシカ・パーカーは、プロデュース型で大きな商業的成功を収めている。ニュージーランドの新進ワイン生産者、インヴィーヴォ・ワインズ(Invivo Wines)と手を組んだ。ブランド名は「そのまま」で、インヴィーヴォ X サラ・ジェシカ・パーカー(Invivo X, SJP)である。中価格帯に絞ったポートフォリオは、マールボロ産のソーヴィニヨン・ブランとピノ・ノワール、プロヴァンス産のロゼという二重国籍のラインナップだ。ジェシカ・パーカーは、ラベルデザインとブレンドに積極的に関わっているそうだ。

サラ・ジェシカ・パーカー(2018年撮影)ⒸGeorges Biard
『チャーリーズ・エンジェル』などが代表作のキャメロン・ディアスも、多国籍のワイン・ブランドを手がけている。ブランド名はアヴァリン(Avaline)で、雑誌『Elle』の元編集者の女性との共同経営だから、オーナー型である。とはいえ、所有するのはブランドのみで、生産自体は、世界各国(フランス、スペインなど)のワイナリーに行なわせている。「体によいワイン、クリーンワインを造ろう」がコンセプトで、有機栽培認証を得たブドウのみを使用、添加物を最小限にしているのがウリだ。ディアスは2014年の映画出演を最後に、俳優業を引退しており、ワイン生産を新たなライフワークと捉えているようである。ワインは中価格帯で、品種も色・スタイルもヴァラエティに富む。

キャメロン・ディアス(2007年)ⒸDrew de F Fawkes
このほか、サム・ニール、ジョージ・クルーニー、イドリス・エルバらに、自身のワイン・ブランドがある。
ミュージシャンのブランド
ミュージシャンの部でトップに紹介すべきなのは、スティングのワイナリー、テヌータ・イル・パラジオ(Tenuta Il Palagio)だろう。本業の実績、ワインへの本気度ともに申し分ない。独自の音楽世界を築いたバンド、ザ・ポリスのフロントマンとして活躍した。1986年のバンド解散後はソロに転じ、今も一線にいる。そんなスティングは、俳優・映画監督・プロデューサーである妻のトルーディ・スタイラーとともに、1997年にトスカーナ州の土地と邸宅を買い、荒れ果てていた11ヘクタールのブドウ畑を再生させた。栽培は、世界的なビオディナミの専門家アラン・ヨークに助言をあおいでいる。醸造は、イタリア屈指のコンサルタント、リカルド・コタレッラが面倒を見ているというから、超強力なお助けチームだ。夫妻とも、栽培や醸造の肉体労働にも本気で関与している。各銘柄に、「メッセージ・イン・ア・ボトル」、「ウェン・ウィ・ダンス」といったザ・ポリス、スティングの楽曲名が使われているから、ファンは大喜び。品種はサンジョヴェーゼが多く、中価格帯中心だが、フラッグシップの「シスター・ムーン」は少し値が張る。

スティング(2018年撮影)ⒸRaph_PH
ミュージシャン本人の関与度合いはともかく、とかく話題にあがるのが、ヒップ・ポップ界の巨人ジェイ・Zが一部所有するシャンパーニュのブランド、アルマン・ド・ブリニャック(Armand de Brignac)であろう。大きなスペードのエースがあしらわれたボトルは、ド派手で、いかにも高額品の雰囲気だ(実際に、非常に高価である)。もともとアルマン・ド・ブリニャックは、老舗シャンパーニュ・メゾンであるキャティア(Cattier)のプレステージ・ラインとして、2006年に誕生した。そのブランドをまるごと、2014年にシャンパーニュ好きのジェイ・Zが買ったのだ。生産は、それまで通りキャティアが続けており、ジェイ・Zは資本提供のほか、ブランド戦略とマーケティングに手を貸しているらしい。2021年にジェイ・Zは、持ち株の半分(総発行株式の50%)をLVMHグループに売却したが、現在も最大株主のひとりである。なお、ジェイ・Zはワインだけでなく、スポーツバー、アパレルブランドなどのサイドビジネスも手がけている。世界一リッチなラッパーだけあって、資金は有り余っている。

ジェイ・Z(2011年撮影)ⒸJoella Marano
長期間現役でいるロックスターでは、ジョン・ボン・ジョヴィもワインに夢中だ。フランス・ラングドック地方に、ハンプトン・ウォーター・ワイン・カンパニー(Hampton Water Wine Co.)を、2018年に設立した。共同経営者は、息子のジェシー、そして同地方ワイン製造業界の大立て者、ジェラール・ベルトランだ。言い出しっぺは、ロゼワインの魅力に心を奪われた息子のほうで、その説得に父のジョンが乗ったらしい。「ハンプトン・ウォーター」とは、ボン・ジョヴィ一家が休暇を過ごすニューヨーク州ハンプトン(日本の軽井沢のような土地)で、ロゼが水のように飲まれている状況から付けられた名前である。ワイン造りはベルトランのチームが行なうが、ボン・ジョヴィ親子もワインのコンセプト設計、ブレンド、銘柄名やラベルデザインには深くコミットしているそうだ。独自の醸造施設や自社のブドウ畑はないので、オーナー型とはいえ、あくまでブランドの所有者という位置づけになる。グルナッシュ主体のロゼと、ピノ・ノワールとグルナッシュ他を使ったロゼ・スパークリングのみで、どちらもお値頃な価格設定である。

ジョン・ボン・ジョヴィ(2024年撮影)ⒸNeil Grabowsky_Montclair Filmjpg
日本人アーティストだと、米国カリフォルニア州在住のYOSHIKIだ。ロックバンドX JAPANのリーダーで、作曲家、プロデューサーとしても活躍している。熱烈なワイン愛好家で、好きが高じた。Y by Yoshikiというのがブランド名で、プロジェクトの開始は2009年。畑や生産施設を所有しないプロデュース型で、ブドウの調達と醸造は、ナパのロバート・モンダヴィ・ジュニアに委ねられている。ただし、ブレンディングにはYOSHIKIが最初から最後まで立会い、その意向が優先されているようだ(YOSHIKIはブレンド作業を、音楽のミキシング・ダウンに喩えている)。新ヴィンテージの発表のたびに、日本で華やかなお披露目界が開かれており、その場にはYOSHIKI本人が登場する。ブドウ品種は、カベルネ・ソーヴィニョン、ピノ・ノワール、シャルドネなどで、高価格~超高価格の銘柄のみ。なお、2025年春には、YOSHIKIが北海道余市町で、新たにワイン生産を始めると報じられた。余市の星、ドメーヌ・タカヒコの曽我貴彦氏が「監修」役を務めるそうだ。同じく余市にあるフィールドオブドリームスワイナリーとの3社共同で、0.4ヘクタールの自社畑に、1100本のピノ・ノワールを植える予定だという。このプロジェクトについてYOSHIKIは、「日本の美を味覚で表現し、世界一のワインを目指したい」とコメントした。

グラミー・ミュージアムでピアノ演奏をするYOSHIKI(2014年撮影)ⒸJustin Higuchi
このほか、メアリー・J・ブライジ、カイリー・ミノーグ、スヌープ・ドック、アレックス・ジェームス、ゲイリー・バーロウらに、自身のワイン・ブランドがある。
スポーツ選手のブランド
まずは南アフリカの大スター・プロゴルファー、アーニー・エルスのワインが挙がるだろう。本気のオーナー型で、その名を冠したワイナリー「アーニー・エルス・ワインズ(Ernie Els Wines)」を2005年、ステレンボッシュ地区にオープンさせた。自社畑も保有している。醸造家として、辣腕で知られるルイ・ストライダドムを雇い、経営はエルス本人が陣頭指揮を執る。ボルドースタイルの本格派赤ワインは、南アフリカ産としては非常に高額ながらも、その品質でデビューと同時に拍手喝采を受けた。現在は、多彩なブドウ品種と色(白・ロゼ・赤)で、中価格帯のワインも生産する。エルスは、「ワイン造りはゴルフのようだ。どちらも最後は自然が支配する」と語っている。

全米オープンでプレイするアーニー・エルス(2008年撮影)ⒸSD Dirk
スペイン・サッカー界の誇り、「魔術師」アンドレス・イニエスタは、少し変わったオーナー型だ。故郷のスペイン中央部ラ・マンチャ地区で1999年、まず実父ホセ・アントニオがブドウを植え始めた。ボデガ・アンドレス・イニエスタ(Bodega Andrés Iniesta)を名乗るワイナリーの代表は、今も父ホセ・アントニオである。息子のアンドレスは、畑の購入、ワイナリー建設、ブランド戦略について資金提供や助言を行なう。ふるさとの経済活性化、雇用創出を目指す企てだと、イニエスタ親子は述べている。ブランド名はコラソン・ロコ(Corazón Loco)で、テンプラニーリョ、ボバル、シラー、ソーヴィニョン・ブランなどを使った、低価格帯から中価格帯にかけての商品ラインナップだ。

ワールドカップでスペイン代表メンバーとしてプレイするアンドレス・イニエスタ(2018年撮影)ⒸАнтон Зайцев
その他のセレブのブランド
現代セレブリティ・ワインの元祖とも言えるのが、映画監督フランシス・フォード・コッポラが所有する、イングルヌック(Inglenook)だろう。カリフォルニア州ナパ・ヴァレーの中心、ラザフォードAVAに位置する老舗名門ワイナリーだ。コッポラによる買収は、『ゴッドファーザー(Ⅰ・Ⅱ)』と『地獄の黙示録』の合間の1975年に行なわれている。その醸造施設とブドウ畑は、20世紀の半ばには最も優れたナパ産赤ワインのひとつを生み出していたのだが、商標も失い、生産もできない状態になっていた。そこからすべてを立て直し、かつての輝かしき商標イングルヌックをも取り戻したのは、コッポラの手腕である。旗艦銘柄に当たるカベルネ・ブレンドのルビコンは、ナパ・ヴァレーを代表する赤ワインのひとつとして、安定した評価を得ている。なお、ワイナリー経営者としてのコッポラは、高額品のみのイングルヌックとは別に、ダイヤモンド・コレクション(Diamond Collection)、ディレクターズ・カット(Director’s Cut)、娘の名を冠した泡のソフィア(Sofia)というブランドも展開する。総体として、さまざまな価格帯やスタイルを取り揃えた、かなり大規模なワイン生産者である。

フランシス・フォード・コッポラ(1973年撮影)ⒸBernard Gotfryd
本人が現在関与しているわけではないものの、取上げざるをえないのが、アメリカ・ヴァージニア州のトランプ・ワイナリー(Trump Winery)である。第45・47代アメリカ合衆国大統領、ドナルド・トランプの次男エリック・トランプが、所有と経営をしている。クルーグ・エステート・ワイナリー・アンド・ヴィンヤード(Kluge Estate Winery and Vineyard)として、1999年に設立されたワイナリーを、2011年にドナルド・トランプ本人が買った。その後、次男に所有権が移転され、現在に至っている。ブドウ畑を含む敷地は約500ヘクタールもあり、ブティック・ホテルをも併設した、米国東海岸屈指の大ワイナリーである。カベルネ・ソーヴィニョン、シャルドネなどのフランス系国際品種を栽培していて、アメリカのワイン雑誌で90点以上を獲得した銘柄もある。ドナルド・トランプ本人は、アルコールを一切口にしないと公言しているので、買収時の意図は多角的投資のひとつだったと推察される。

ドナルド・トランプ公式肖像(2025年撮影)
4. おわりに
上述したように、コアなワイン好きやプロフェッショナルは、セレブのワインに批判的な目を向けがちだ。「名前貸し」による上乗せ金額を、進んで払おうとはしない。セレブの本気度が伝われば印象は変わるが、それでも「ミーハー扱いされたくない」という思いから、公然の場では話題にしないし、なかなか注文・購入しようともしない。
しかし、ワインはマニアやプロだけのものではない。セレブのワインは、「裾野を広げる」という重要な役割を担える存在だ。これまでワインに興味を持たなかった人、口にする機会がない人に、チャンスを与えられるのは素敵ではないか。裾野が広がれば、ワイン業界全体が潤うし、それはマニアを含むあらゆる消費者に還元されていく。服を着ない人はいないし、冷凍食品を食べない人も希だが、ワインを飲まない人はたくさんいる。最難関である最初の一口を、憧れの人の輝きが実現させるのなら、セレブリティ・ワインはもっと増えていい。