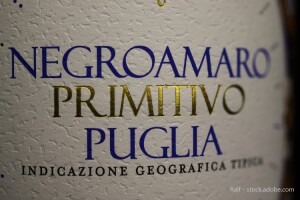イタリアで広く栽培される白ブドウ、トレッビアーノ。その名は、フランス語の「トレビアン très bien」を連想させる響きですが、語源的には関係がありません。また、このブドウから造られるワインが、実際にトレビアンであるのは希です。それでも、イタリア産白ワインの約3分の1が、トレッビアーノから生まれていて、使用可能な原産地呼称名はおおよそ80もあります。ややこしいのは、イタリアには大きく6種のトレッビアーノがあって、それぞれ関係があったりなかったりする点でしょう。そのうちのひとつ、トレッビアーノ・トスカーノは、フランスでも広く栽培され、ワインよりもブランデーの原料として有名です。本レポートでは、トレッビアーノを名乗るブドウの種類についてまず整理し、その最大派閥であるトレッビアーノ・トスカーノについて、ワインの特徴、栽培特性、歴史、主要な産地、サービス方法とフードペアリングについて、深掘りしていきます。
【目次】
1. いろんなトレッビアーノ
● トレッビアーノ・アブルッツェーゼ
● トレッビアーノ・トスカーノ
● トレッビアーノ・ロマニョーロ
● トレッビアーノ・スポレティーノ
● トレッビアーノ・ジャッロ
● トレッビアーノ・モデネーゼ
2. トレッビアーノ・トスカーノはどんなワイン?
● 風味の特徴
● スタイルの多様性
● キアンティへのブレンドについて
3. トレッビアーノ・トスカーノの栽培特性
4. トレッビアーノ・トスカーノの歴史
5. トレッビアーノ・トスカーノの主要産地
● イタリア
● フランス・コニャック地方&アルマニャック地方
● 南フランス
● その他の地域
6. トレッビアーノ・トスカーノのサービス方法とフードペアリング
● サービス方法
● フードペアリング
7. トレッビアーノのまとめ
1. いろんなトレッビアーノ
ワイン用ブドウの百科事典、『Wine Grapes』(ジャンシス・ロビンソン他・著、邦訳『ワイン用 葡萄品種大事典』)には、Trebbianoから始まる見出しが28もあります。ほとんどが、Trebbiano XXXと、後ろになにかの言葉がひっついている形をしていて、「なにか」は産地名が多いですが、それだけではありません。また、28のすべてが別々の品種ではなく、あるものは他のトレッビアーノの異名だったりもします。主要なものは6種類で、トレッビアーノ・アブルッツェーゼ(Trebbiano Abruzzese)、トレッビアーノ・トスカーノ(Trebbiano Toscano)、トレッビアーノ・ロマニョーロ(Trebbiano Romagnolo)、トレッビアーノ・スポレティーノ(Trebbiano Spoletino)、トレッビアーノ・ジャッロ(Trebbiano Giallo)、トレッビアーノ・モデネーゼ(Trebbiano Modenese)です。これらのうち、アブルッツェーゼとスポレティーノの間には、近しい遺伝的関係が見られるようですが、ほかの連中は皆、遺伝的な関係はないか非常に遠いかのようで、なかなかの混乱状態です。日本中に「田中さん」が大勢いるけれど、ほとんどの人たちは血のつながりがないのと似ています。

田中さんの場合は、「田んぼの中に家があった」という理由で、明治維新時にその姓を選んだ人が、日本全国にいっぱいいました。トレッビアーノも似たような話で、ブドウの外観や育ち方に共通の特徴があったために、同じ名前が付いたのではないかと推測されています。具体的に言うと、どのトレッビアーノも樹勢が強く、収量が多く、房が長く大きく、かつ晩熟であるといった特性です。トレッビアーノという名前が、もともとどこから来たかの語源については、後述します。
トレッビアーノ・アブルッツェーゼ
その名の通り、イタリアのアブルッツォ州にそのほとんどが植わっています。いろんなトレッビアーノの中では、トスカーノ、ロマニョーロに次ぐ面積です(2016年時点で2630ヘクタール)。DNA鑑定による品種同定技術が、1990年代末に実用化されるまでは、複数の異なる白ブドウと間違えられていました(ボンビーノ・ビアンコ Bombino Bianco、モストーザ Mostosa、トレッビアーノ・トスカーノ)。6つのトレッビアーノの中では最も品質評価が高く、味わいに密度と緊張感があり、熟成能力も有します(とあるイタリアワインの専門家は、上質のシャブリに喩えました)。代表的な原産地呼称はDOCトレッビアーノ・ダブルッツォです。このDOCの名で辛口白を造る生産者の中に、気高きヴァレンティーニ Valentiniがいます。古めかしいデザインのラベルは、マニア垂涎の的で、イタリアで最も手に入れにくい(そして高価な)白ワインのひとつです。言うならば、「トレッビアーノの星」。しかしながら、このヴァレンティーニの畑に植わっている古木は、実はボンビーノ・ビアンコという別品種ではないかと噂されていまして、なんだか妙なハナシです。

ヴァレンティーニのトレッビアーノ・ダブルッツォのラベル
トレッビアーノ・トスカーノ
イタリアの白・グリ品種の中では、1位のグレーラ(プロセッコの原料品種)、2位のピノ・グリージョに続く第3位で、1位との差もそう大きくはありません。イタリア国内総面積は、2016年時点で約3.5万ヘクタール。名前の由来になったトスカーナ州でもそこそこ栽培されていますが、プーリア州にはその5倍以上植わっていますし、ラツィオ州、アブルッツォ州の面積もトスカーナ州より多いです。ほかにも、マルケ州、カンパーニア州、シチリア州、ウンブリア州に、まとまった本数の樹があります。フランスでの呼び名はユニ・ブラン(Ugni Blanc)、あるいはサンテミリオン(St-Emilion)で、かの国では2位のシャルドネに大差をつけて、白ブドウ栽培面積第1位。トレッビアーノ・トスカーノは、イタリア、フランス両国以外には、さほど植わっていないのですが、それでも白ブドウでは世界第3位です(シャルドネ、アイレンに次ぐ)。かように、面積では世界クラスなのですが、味わいのほうはパッとしません。ヴェネト州の高名な白ワイン、ソアーヴェの原料ブドウであるガルガネーガは、トレッビアーノ・トスカーノと親子関係です。非常にややこしいのですが、ヴェネト州で「トレッビアーノ・ディ・ソアーヴェ」と呼ばれている白ブドウは、上記6つのどのトレッビアーノとも関係がなく、マルケ州に広く植わる品種ヴェルディッキオと同一だったりします(ロンバルディア州の「トレッビアーノ・ディ・ヴァルテネージ」も、ヴェルディッキオと同じ品種です)。

トレッビアーノ・ロマニョーロ
エミリア・ロマーニャ州に集中して植わっています(他州での栽培面積は、ほぼゼロ)。イタリア国内総面積は、2016年時点で約1.9万ヘクタールと結構な広さです。トスカーノと比べると、果実味が豊富でよりコシのあるワインになりますが、複数のバイオタイプ(品種内系統)があるので、「どのロマニョーロか?」によります。主に丘陵地に植わるバイオタイプは、赤みがかった果皮の色をしていて、酸味が豊かで複雑なワインになるようです。ただし、収量が少ないために、このバイオタイプは1960年代以降、減少の一途を辿ってきました。
トレッビアーノ・スポレティーノ
ウンブリア州のスポレート(Spoleto)と、モンテファルコ(Montefalco)周辺に集中的に植わっています。このほか、ヴェネト州にも若干の畑がありますが、イタリア国内総面積は、2016年時点で121ヘクタールと、マイナーな品種です。生まれる辛口白ワインは、そのスタイルや品質に多様性があるようですが、なにぶん畑の面積が小さいので、はっきりとした傾向を語れません。
トレッビアーノ・ジャッロ
ラツィオ州のカステッリ・ロマーニ(Castelli Romani)地方と、歴史的に関連の深い品種です。完熟時に果皮が黄金色になることから、「ジャッロ Giallo」(黄色)の名前がつけられました。イタリア国内総面積は、2016年時点で2275ヘクタール。しかしながら、「本拠地」であるべきラツィオ州には、ジャッロが184ヘクタールしか植わっていません(現在の主産地は、エミリア・ロマーニャ州とプーリア州です)。一方で、トスカーノはラツィオ州に、4277ヘクタールも植わっています。ラツィオ州の高名な辛口白ワイン、DOCエスト!エスト!!エスト!!!・ディ・モンテフィアスコーネ(Est ! Est !! Est !!! di Montefiascone)、DOCフラスカーティ(Frascati)、DOCマリーノ(Marino)などは、伝統的にトレッビアーノ・ジャッロと結びついてきました。しかし、後になって余所からやってきた、トレッビアーノ・トスカーノに乗っ取られてしまった格好です(DOC法規上は、両方の品種の利用が認められています)。品質的にはジャッロがトスカーノを上回るのですが、収量が少ないために、栽培家から好まれなくなってしまいました。

トレッビアーノ・モデネーゼ
ほぼ全量が、エミリア・ロマーニャ州に植わっていますが、イタリア国内総面積は、2016年時点で287ヘクタールと小さいです。ワインよりも主に、同州モデナ産の非常に高名なバルサミコ酢、「アチェート・バルサミコ・トラディツィオナーレ・ディ・モデナ(Aceto Balsamico Tradizionale di Modena)」の原料として用いられます。優れた辛口白ワインもありますが、ごく少数です。

モデナ産のバルサミコ酢のボトル(3年熟成)
2. トレッビアーノ・トスカーノはどんなワイン?
ここからは、6つのトレッビアーノの中で、群を抜いて栽培面積が広い、トスカーノについて解説していきます。
風味の特徴
トレッビアーノ・トスカーノのほとんどは、辛口白ワインになります。香りはニュートラルで、レモンやカモミールのフレーヴァーが特徴と言われるものの、ユニークさはありません。比較的温暖なイタリア中・南部で栽培しても、きりっとした酸味が保たれるのは長所ですが、ボディは軽く、深みに欠けます。あり体に言って、軽くて面白みのないワイン、もっと悪く言うならどこにでもある水っぽいワインと評価されるでしょう。

スタイルの多様性
辛口白ワインの原料としては、あまり評判が芳しくないトレッビアーノ・トスカーノですが、「毎日が日曜日」ではありません。やるときはやる、そんな一面もあるのです。まず、酸味が強いという特徴は、スパークリングワインの原料として、強みになります。また、トスカーナ州の伝統的な陰干し高級甘口ワイン、ヴィン・サント(Vin Santo)においても、トレッビアーノ・トスカーノはマルヴァジア・ビアンカとともに主役級の原料品種です。ヴィン・サントで重宝されるのも、高い酸味ゆえのこと。加えて、アルプス山脈を越えた北側のフランスでは、トレッビアーノ・トスカーノが蒸留用ブドウとして、光輝いています。最高級のブランデーを生産するには、ニュートラルな風味で酸味の強い白ブドウが、一番もよい結果を出すのです。
キアンティへのブレンドについて
トスカーナ州を代表する赤ワインのひとつ、DOCGキアンティ(Chianti)においては、白ブドウを最大10%までブレンドするのが認められていて、その対象品種の中にはトレッビアーノ・トスカーノが含まれています。これには、ちょっとした裏話があります。19世紀後半、当時すでに高名であったキアンティの赤ワインについて、「このブレンド比率で造ろうぜ」という提案がなされました。言い出したのは、今日も地域屈指の生産者一族の領袖、リカゾーリ男爵です(のちに統一イタリアの第二代首相になった人物)。男爵曰く、「キアンティは サンジョヴェーゼを主体とし、長期熟成型のワインにはカナイオーロのみを、若飲みのワインにはカナイオーロとマルヴァジアをブレンドするべし」と。「リカゾーリ方式」と呼ばれるようになった、このブレンド法では、カナイオーロ(黒品種)やマルヴァジア(白品種)が、サンジョヴェーゼの荒々しいタンニンを和らげ、酒質を柔らかくする役目を果たしていました。1967年にキアンティがDOCに認定されたときにも、このリカゾーリ方式が踏襲されたのですが、風味豊かなマルヴァジアだけでなく、高収量のトレッビアーノ・トスカーノまでもが潜り込みます。それから、同地のワイン造りは進歩し、サンジョヴェーゼのタンニンを手懐ける術を生産者が身につけたので、今では白ブドウの使用は合理的根拠を失いました(DOCキアンティから1996年に分離独立した、DOCGキアンティ・クラッシコでは、白ブドウのブレンドは禁止です)。それでも、一部の志の低い造り手は、増量剤としてのトレッビアーノを、今もキアンティに混ぜ続けています。
3. トレッビアーノ・トスカーノの栽培特性
温暖な気候を好み、育てやすく歩留まりもよいため、最北部を除くイタリア全土と、南フランスで旺盛に茂っています。芽吹きは遅いので、春の霜のリスクは高くありません。樹勢が強く、収量は非常に高く、ヘクタールあたり150ヘクトリットルといった超高水準にも難なく達します。元来は晩熟のブドウですが、強い酸味という特性を生かすため、早めに摘まれるケースが珍しくありません。カビ系の病害については、ベト病にはやられやすいものの、灰色カビ病とウドンコ病へは強い耐性があります。

マルケ州にあるトレッビアーノ・トスカーノの畑
4. トレッビアーノ・トスカーノの歴史
「トレッビアーノ」という名前が、どこから来たのかについては、諸説あって、今もよくわかっていません。有力な説のひとつが、ローマ時代のワインに由来するというものです。古代ローマの博物学者プリニウスは、著書『博物誌』の中で、現在のカンパーニア州カプア近くの「アグロ・トリブラニス(Agro Tribulanis)」で生産された、「Vinum tribulanum(ヴィヌム・トリブラヌム)」というワインについて記しています。また、ウンブリアやトスカーナでも、「tribulanum」という名のワインが当時知られていました。この「tribulanum」が、「Trebbiano」に転じたという仮説があります。
名前の前半がどこから来たかはさておき、トレッビアーノ・トスカーノはその名のとおり、長きにわたってトスカーナ州で知られてきました。1600年にソデリーニという人物は、トレッビアーノ(特定されていないが、おそらくトスカーノ)とマルヴァジアが、地域で最も広く栽培されている品種だと記しています。上述の通り、ソアーヴェのガルガネーガとは親子関係にあると、DNA鑑定で確認されており、そこからイタリア起源のブドウだと考えるのが現在の定説です(ガルガネーガは、トレッビアーノ・トスカーノ以外にも、アルバーナ、カタラット・ビアンコなど、多くのイタリア品種と親子関係にあります)。
フランスにこの品種が渡ったのは14世紀、カトリック教会の教皇庁がローヌ渓谷南部の町、アヴィニョンにあった頃のようです(1309-1377、教皇のアヴィニョン捕囚)。当初、ローヌ南部ではウニエール(Uniers)と名付けられて、そこからプロヴァンス地方へと南下、地中海沿いにラングドック地方へ広がりました。ラングドックから北へ上って、アルマニャック地方、コニャック地方へと達した、という経路のようです。その過程で、ユニ・ブラン(Ugni Blanc)と呼ばれるようになったのですが、ウニ(Ugni)という語は、プロヴァンス方言の「ユニ(uni)」(「早摘みブドウ」の意味)に由来するという説があります。

ローヌ渓谷南部にあるアヴィニョン教皇庁 ©JM_Rosier
5. トレッビアーノ・トスカーノの主要産地
イタリア
多数の産地で、トレッビアーノ・トスカーノは用いられています。州ごとに、有名なDOC名を列記すると、原産地トスカーナ州では、エルバ・ビアンコ(Elba Bianco)、モンテクッコ(Montecucco)ほか、かなりの数のDOCで使用可能です。キアンティ、モンテプルチアーノ(Montepulciano)、カルミニャーノ(Carmignano)といった有名赤ワイン産地で生産されるヴィン・サントでも、トレッビアーノ・トスカーノは欠かせません。

ヴィン・サント用に陰干しされるトレッビアーノ・トスカーノ
さほど量は多くないものの、イタリア北部ではヴェネト州の、ビアンコ・ディ・クストーザ(Bianco di Custoza)で、トレッビアーノ・トスカーノが使われています。
アブルッツォ州では、コントログレッラ・ビアンコ(Cotroguerra Bianco)、オルトーナ(Ortona)、トレッビアーノ・ダブルッツォ(Trebbiano d’Abruzzo)、アブルッツォ・ビアンコ(Abruzzo Bianco)という、白のDOCすべてで、トレッビアーノ・アブルッツェーゼとともに、トスカーノの利用が認めれています(植栽面積は、トスカーノのほうがうんと多いです)。
カンパーニア州の白ワインというと、ファランギーナ(Falanghina)やグレコ(Greco)という2品種のイメージが強いですが、DOCカステル・サン・ロレンツォ・ビアンコ(Castel San Lorenzo Bianco)、チレント・ビアンコ(Cilento Bianco)、サンニオ・ビアンコ(Sannio Bianco)で、トレッビアーノ・トスカーノを利用できます。
ラツィオ州では、上述のフラスカーティ、エスト!エスト!!エスト!!!・ディ・モンテフィアスコーネ、マリーノの白のほか、オルヴィエート(Orvieto)、コッリ・アルバーニ(Colli Albani)などなど、ほとんどのDOCの白ワインで、トレッビアーノ・トスカーノは認可品種です。
マルケ州では、コッリ・マチェラテージ・ビアンコ(Colli Maceratesi Bianco)、コッリ・ペサレージ・ビアンコ(Collli Pesaresi Bianco)、ファレリオ(Falerio)で使えます。
モリーゼ州でも、白ワインを造れるDOCすべてで、トレッビアーノ・トスカーノが使えます。特に、ビフェルノ・ビアンコ(Biferno Bianco)では、ブレンドの70~80%を占めるべしと定められており、主役を張っています。
ダントツに栽培面積が多いプーリア州では、ジョイア・デル・コッレ・ビアンコ(Gioia del Colle Bianco)、リッツァーノ・ビアンコ(Lizzano Bianco)の両DOCで、トレッビアーノ・トスカーノが主力品種です(前者は50~70%、後者は40~60%)。ただし、同州内のトレッビアーノの大半は、DOC未満の廉価な白ワイン(IGTなど)に、用いられています。
シチリア州は、栽培面積はトスカーナ州と同程度(約2400ヘクタール)と少なくないのに、DOC以上のワインで、トレッビアーノ・トスカーノはまったく認可されていません。プーリア州と同じく、DOC未満の廉価な白ワインに、仕向けられています。
フランス・コニャック地方&アルマニャック地方
トレッビアーノ・トスカーノは、イタリア原産のブドウなのに、フランスのほうが今ではずっと栽培面積が広くなりました。フランス名ユニ・ブランの、2016年時点の仏国内総栽培面積は、約7.9万ヘクタールもあって、イタリアの倍以上です。その9割以上はシャラント県、すなわち世界一高貴なブランデー、コニャックの産地に植わっています。フランス第二のブランデー産地である、アルマニャック地方でも、ユニ・ブランは主力品種ですが、生産規模がコニャックの20~30分の1しかないので、栽培面積はずっと小さくなります。なお、コニャック、アルマニャックともに、19世紀後半のフィロキセラ禍までは、現在二番手品種の地位にあるフォル・ブランシュ(Folle Blanche)が主役でした。交代劇が起きたのは、フォロキセラと同時期に頭痛の種になった、ウドンコ病や灰色カビ病に対し、ユニ・ブランが強い耐性をもっていたからです。

コニャック地方、グランド・シャンパーニュ地区のブドウ畑
南フランス
ローヌ渓谷では、広域AOCのコート・デュ・ローヌ(Côtes du Rhône)およびコート・デュ・ローヌ・ヴィラージュ(Côtes du Rhône Villages)の白で、多数の品種のうちのひとつとして、ユニ・ブランも認められています。渓谷北部の格上AOC(クリュ)ではユニ・ブランを使えませんが、南部のクリュでは、まずジゴンダス(Gigondas)で認可品種のひとつです(ただし、作付け面積で、ヴィオニエとの合計で5%未満)。リュベロン(Luberon)の白でも、補助品種の扱いですが、ブレンドにおいて50%まで使えます。デュシェ・デュゼス(Duché d’Uzès)の白でも補助品種で、こちらはブレンドの上限が10%。ローヌ南部は、ユニ・ブランがイタリアから入ってきたゆかりの地の割に、冷遇されています。教皇庁ゆかりの産地、AOCシャトーヌフ・デュ・パプ(Châteauneuf-du-Pape)では、少なくない数の白ブドウが認可されているのに、ユニ・ブランは仲間に入れてもらえませんでした。
ローヌ渓谷の南に位置するプロヴァンス地方のほうが、ユニ・ブランの扱いは良いです。広域AOCのコート・ド・プロヴァンス(Côtes de Provence)の白では、4つある主要品種のひとつになっています。バンドール(Bandol)、カシス(Cassis)といった名高い地域を含むほとんどのAOCで、主要品種か補助品種かはさておき、ユニ・ブランは認可品種です。
ラングドック・ルーション地方は、プロヴァンスからアルマニャックへの橋渡しとなったエリアですが、現在はユニ・ブランが少量しか栽培されていません。この地方のAOCでユニ・ブランは認可品種になっておらず、AOC未満の廉価なワインに用いられているようです。
その他の地域
ヨーロッパ諸国では、ポルトガルに少々、トレッビアーノ・トスカーノは植わっています(122ヘクタール/2016年時点)。エリアは、ドウロ渓谷の南側、セントロ(Centro)と呼ばれる一帯で、「タリア(Tália)」というのがこの国での呼び名です。このほか、ブルガリア(738ヘクタール)、ギリシャ(211ヘクタール)、モルドバ(277ヘクタール)が、欧州におけるこの品種の主要産地になります。
新世界ではアルゼンチンにおいて、メンドーサ地域を中心に、まずまずの面積(1622ヘクタール/2016年時点)が植わっています。ただし、国際市場ではこの品種名を掲げたアルゼンチンワインをまず目にしません。とはいえ南米では、トレッビアーノ・トスカーノに一定のニーズがあるようで、ウルグアイ(682ヘクタール)、ブラジル(231ヘクタール)にもまずまずの量の植栽が見られます。中国(1500ヘクタール)、インド(300ヘクタール)は、意外に多くて少し不思議です。アメリカ合衆国(あるいはカリフォルニア州)やオーストラリアといった、「代替品種」への挑戦が近年盛んな産地では、100ヘクタールに至りません。ワイン用品種としてのポテンシャルが、いまひとつという値踏みなのでしょう。
6. トレッビアーノ・トスカーノのサービス方法とフードペアリング
辛口白としてのトレッビアーノ・トスカーノは、ごく一部の例外をのぞき、たいしたワインにはなりません。よって、以下に述べるサービス方法やフードペアリングは、「軽い白ワイン」に対する一般的な内容となります。
サービス方法
ライト・ボディの白なので、7〜10℃の温度で提供するのがよいでしょう。この温度帯では、ワインの爽やかさが強調されますし、唯一の長所と言うべき酸味にもキレが出ます。グラスは、小ぶりな白ワイン用のものが最適です。大ぶりなグラスのボウルを満たすだけのアロマはありませんし、飲みきるまで時間がかかると、ぬるくなってしまい適温の帯から外れます。澱のない白ワインですし、軽い酒質なので、デキャンティングは必要ありません。
フードペアリング
ぼんやりと「魚介類全般」と言えますが、しっかりしたソースを使った重めの皿には不向きです。ソースやトッピングによるとはいえ、パスタやピザとはおおむね好相性でしょう。チーズなら、モツァレラなどフレッシュタイプがオススメです。

7. トレッビアーノのまとめ
マルヴァジア、マスカットもそうですが、古い欧州の品種は程度の差はあれ、その多くが「田中さん」状態にはなっています。DNA鑑定技術の登場によって、これはアレでそれはドレでというのが分かるようにはなりましたが、大昔から使われてきた名前はそう簡単には変わりません。大きく6種類あるトレッビアーノ、多少の優劣とわずかな例外があるとはいえ、冴えない品種なのは一緒です(だからこそ、同じ名前でグルーピングされています)。「天はブドウの上にブドウを作らず」と、自信をもって言えたらいいのですが、現実の壁はなかなか高いです。とはいえ、伝統が幅を利かすワインの世界とて、壁をたたき壊す「怒れる若者たち」は、常にどこかで登場しています。この記事を、もっと好意的な内容に書き直す日が来るのが、筆者は待ち遠しいです。