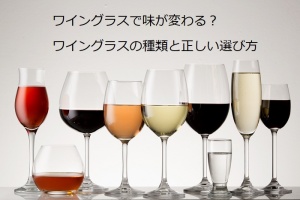国連世界観光機関主催のワインツーリズム会議。2025年はブルガリアのワイン産地、トラキア低地のプルヴディフで10月に開催予定です。ヨーロピアン・ベストデスティネーションというヨーロッパの観光地調査機関の投票でも、プルヴディフは、ヨーロッパのワイン都市第1位。
第2次大戦後から、ベルリンの壁が崩壊する1989年の間は、ワイン産業が国営化。その後、産地の再興に苦労したブルガリアに、今、光が当たっています。一時は、フランスに次いで、世界第2位のワイン輸出国であったブルガリア。華麗なる復活を遂げることはできるのでしょうか。
【目次】
1. ブルガリアワイン:産地の概観と原産地呼称制度
2. ワインと政治は無縁ではいられない
3. 復活なるか~ブルガリアワイン第二の黄金時代
4. 国際品種と土着品種のワインと産地の特色
5. ブルガリアワインのまとめ
1. ブルガリアワイン:産地の概観と原産地呼称制度

ブルガリアは、北にルーマニア、南にギリシャ及びトルコと国境を接しています。北緯42度で、スペインのリオハや、イタリアのマルケ州辺りと同じ緯度。ブドウ生育期間の平均気温は、首都ソフィアでは10℃前半から20℃前半を推移し、年間降雨量は600ミリ前後。北部は温和な大陸性気候で、黒海沿岸は海洋性、南部は地中海性の影響を受けます。日照時間には恵まれていて、年間で2千時間を超えます。
2007年のEU加盟により、2つのPGI産地のみが認知。国の中部を東西に走るバルカン山脈によって分割された北部の温和な大陸性気候のドナウ平原PGIと、トラキア低地PGIです。
PDOは、52の産地が指定されていますが、ワインのラベルに印刷されているのを見るのは稀。1パーセントにも満たない小規模な生産量で、規則も厳しいので生産者から注目されていません。
一方、PGIはワイン生産の内、35パーセント程度を占めます。でも、特定の気候や土壌を表現するような、地理的表示の役割を果たしていないという批判もあります。例えば、どちらもPGIトラキア低地に属する、海洋性の影響を受ける黒海沿岸と、地中海性気候に近いストゥルマヴァレーでは、だいぶ気候が異なります。
他方、厳しい制約が少ないPGIの産地では、新しい品種や逆に土着の古い品種に注目して生産を行うなど、様々な試みが可能。長所も短所もあるのです。
2007年以前の産地呼称で、今でも良く使われる、1960年に定められた伝統的な5つの産地名称。こちらの方がわかりやすいかも知れません。北部のドナウ平原、南西部のストゥルマヴァレー、中部のローズヴァレー、南部のトラキアヴァレー、東部の黒海沿岸の5産地。
しかし、この分類以外にも、全国を4つや6つの産地に分割される場合も。ブルガリアのワイン産業に関する、諸情報はまだ上手く統合されていないのが実情です。
現在、こうした産地の分類を改めて整理をしようという議論が行われています。歴史的な5つの産地をPDOに格上げする案や、いやいや6つ、あるいは8つの産地をPDOにしようという案も議論されているようです。
ブルガリアは、所得が向上し、都市化が進み若い世代の消費が活況。PDOやPGIの需要が増えて、量より質への転換が起こり始めています。また、白ワインと共にロゼワインも伸長。多様化が進んでいます。
2. ワインと政治は無縁ではいられない
古代~近代
ブルガリアの建国は681年に遡りますが、ワイン造りはさらに古い歴史を有しています。ブドウ栽培は3,000年以上前から。『博物誌』で知られる大プリニウスも、最初のブドウ栽培を行ったのは、トラキア人だと述べています。トラキア人は、ブルガリア人の祖先。
古代ギリシャ神話の酒神デュオニュソス、ローマ神話で言えばバッカスは、トラキアに由来する神とされています。ローマの支配を受けた時代の、グラディエイターの反乱として名高い、スパルタクスもトラキア人。

ギリシャ神話の酒神デュオニソス像
その後のオスマン帝国の支配下、非イスラム教徒には、ブドウ栽培は許されていました。そして、19世紀末に帝国の支配から自由になる頃には、10万ヘクタールを超える栽培面積を有していたとも。
御多分に漏れず、フィロキセラの被害を受けたものの、フランスの著名な栽培学者のピエール・ヴィアラを招聘。アメリカ産台木の活用で対策し、プレヴェンにある国立ブドウ・ワイン研究所の設立に貢献しました。20世紀に入ると、協同組合が設立。大規模生産の基盤づくりが進みました。1939年までには、協同組合が60を数え、フランスで学んだ醸造家がワイン生産に参画。
ソ連の影響
1944年には、ソ連軍が進出します。ブルガリアの社会主義国家への転換点となり、王政が廃止。1947年に共産党政権が確立。大半の土地は国有化~集団化されました。結果、ブドウ畑も、大規模なブドウ栽培地帯として、統合。1949年に国営のワイン栽培・醸造・販売公社ヴィンプロムが設立。1950年代に大量にブドウ樹が植樹され、ソ連向けのデイリーワインが続々と生産されました。
1970年代迄には、20万ヘクタールにも及ぶ栽培面積を有し、ソ連と東欧諸国の経済圏のコメコン向けにワインを輸出。それでも、1970年代後半には、米国との取引が進みました。積算温度による気候区分を考案した、UCデイヴィスのメイナード・アメリンも、ワイン造りのアドバイスを実施。
1960年代から80年代には、ブルガリアは世界有数の輸出国へと発展。とは言っても、大半のワインはソ連に供給されたので、西側諸国での知名度は限定的でした。
ところが、ゴルバチョフ書記長の在位期間である1985年から1990年は、アルコール規制により、輸出が大幅に減少。

by Achim Wagner – stock.adobe.com
ソ連崩壊~現代
1990年前後には東欧諸国の体制転換とソ連が崩壊。ワイン産業も混乱に陥ります。集団化されていたブドウ畑を、個人所有者への移管するのは簡単ではなく、手入れがされない畑では、品質も悪化していきました。
ブドウが不足するため、完熟前に、醸造用の原料を確保しようと、収穫の奪い合いが起こりました。
未熟なブドウによる品質の低下。その為、90年代後半には輸出が減少。21世紀に入るまで、良質なワイン生産を軌道に載せるには厳しい状況が続きました。ブドウの多くを調達に頼る大手ワイナリー。ブルガリア全土のブドウを寄せ集めたワインを造るため、PGIは、2つどころか1つにして欲しかったとも言われます。
21世紀に入り、EUの支援プログラム、農業および農村開発のための特別加盟準備プログラム(SAPARD)などがワイナリーやブドウ畑での投資を大幅に支援。海外からの資本や技術協力が行われました。イタリアの実業家でワイン生産者でもある、エドアルド・ミログリオがトラキア地方でワイナリーを創設。ミシェル・ローランも、カストラ・ルブラ・ワイナリーに、コンサルタントとしてワイン造りの指導。こうして、21世紀には小規模の品質重視のワイナリー設立に拍車が掛かりました。
3. 復活なるか~ブルガリアワイン第二の黄金時代
2000年には、カベルネ・ソーヴィニョン等のブドウ品種を使った、マキシマ1999リザーヴがリリース。ロンドンのワイン品評会でも高評価を受け、当時のブルガリアでは画期的な高品質ワインとして注目を集めました。ドナウ平原の小規模生産者、アドリアナ・スレブリノヴァが立ち上げたブランド。後に、やはり品質重視のボロヴィッツアを、2005年にオグニャン・ツヴェタノフと共に始動しました。
2007年のEU加盟後は、栽培面積拡大の方針もあったようですが、基本的には、小規模の生産者による量より質を追求する方向で発展してきています。
ワイナリー数も栽培面積も、今日ではある程度、増加傾向ではあります。260ほどから300社ほどのワイナリー数で、栽培面積は、6万ヘクタールを超えて、2018年には、6万4千ヘクタール。ただし、実際に収穫に供された畑の面積は、3万ヘクタールに届かないとも。
難しいのは、このように、栽培面積とされている面積と、実際の収穫面積に大きな差異があること。実際に収穫されているブドウ品種含めて、正確な諸データを把握するには、難しい所があります。
特徴的なのは、多くのブルガリアの家庭でワインを造っていること。2018年では、収穫されたブドウの内の家庭用は、17パーセントを占めるとされています。味わいや香りは微妙な出来のものが多そうですが、一度、味見させていただきたいもの。欧州で最も、最低賃金が低いことでも知られるブルガリア。時間当たり、3ユーロそこそこで、最高賃金を得ているルクセンブルクの5分の1ほどです。個人でワイン造りをして、手軽に楽しむのは自然な流れでしょう。
輸出の方は、2014年にロシアのクリミア併合を受けた経済制裁に加わったことと、ロシアの通貨下落により、ロシア向けが減少。ロシアに代わって、ポーランドがワインの輸出相手国として第1位となりました。他には、スウェーデン、英国、そして中国でブルガリアワインが存在感を放っています。
国内のワイン消費は、レストランやバーよりも、小売店での販売が主流。国内産ワインに加えて、イタリアを中心にスペインやフランスからも輸入されています。
ワインの大規模なイベントも開催されています。ワインテイスティングはもちろん、ワイン製造機器の出展も行われる国際展示会ヴィナリア。政府の後援も受けて5万人以上の来場者を迎えています。また、500社以上のインポーターが集い、多くのマスタークラスも開催されるディヴィーノ。こうしたイベントが盛大におこなわれています。
4. 国際品種と土着品種のワインと産地の特色
ブルガリアでは、200種類に及ぶブドウ品種が栽培されていると言われています。そして、近年の大きな変化は、5つのワイン産地が定められた1960年以降、大規模な改植が行われたこと。土着品種をフランスやドイツを中心とした国際品種へ転換。1980年代には安価なカベルネ・ソーヴィニョンで、海外でも有名になりました。
今日でもカベルネ・ソーヴィニョンの他にも、メルロ、シャルドネやソーヴィニョン・ブランの栽培が広く見られます。シャルドネは、樽を使わないフレッシュなスタイルが主流。ソーヴィニョン・ブランは、まだ歴史が若く、21世紀に入ってから本格的に栽培されています。
一方、国際品種に混じって、パミッドも栽培面積の主流に。トラキアの時代に遡るほど、古くから栽培されていたとされる、土着の黒ブドウです。近年では、土着のブドウ品種を盛り上げようという機運も勢いを得ているのです。
白ブドウの最大品種は、ルカツィテリ。ブレンドを中心に活用されています。ジョージアの土着ブドウ品種として有名。
トラキアヴァレーとストゥルマヴァレー
多くの赤ワインは、南部のトラキアヴァレーで造られています。カベルネ・ソーヴィニョンやマヴルッドが黒ブドウの重要品種。厳しい北風が山脈でさえぎられ、土壌は、赤褐色のシナモン色の片麻岩や花崗岩などです。
マヴルッドは、マルベックに似ているとも言われ、収量が多くなりがち。晩熟で、台木との相性も難しいとされ、ソ連の影響下ではあまり栽培が広がりませんでした。カベルネ・ソーヴィニョンともブレンドされます。
ミダリダーレはブルガリアで最も尊敬されているワイン生産者の1つ。美しいワイナリーで、ワインツーリズムの拠点としても注目を浴びています。スパが併設されていて、高級レストランも完備されていて休暇を過ごすのに最適。
ドラゴミールは、2006年からワイン造りに参入した若いワイナリー。土着品種を大切にしています。黒ブドウのルビンの単一品種ワインに加えて、カベルネ・ソーヴィニョンやメルロとのブレンドも造っています。
ルビンは、1944年にシラーとネッビオーロの交配で造られた品種。病害にはさほど強くはありませんが、濃い色合いで、タンニンとボディのしっかりしたワインになります。
南西部のストゥルマヴァレーは、メルロやカベルネ・ソーヴィニョンも栽培されていますが、注目すべきは土着の黒ブドウ品種、メルニック。大陸性の他の産地とは違い、エーゲ海の暖かい空気が川伝いに流入。地中海性に近い気候です。このブドウ品種では、葉が広くかなり晩熟なメルニックと、早熟なメルニック55が知られています。
前者は、シロカ・メルニシュカ・ロザとも呼ばれ、高品質で長期熟成可能なワインを生み出します。完熟させるのに苦労しますが、糖度が上がっても酸が落ちません。そのほとんどが、暖かいストゥルマヴァレーでのみ栽培。中世に遡る栽培の歴史があります。
一方、メルニック55は、シロカ・メルニシュカ・ロザとフランス原産のヴェルディギエとの交配種で早熟。軽快なワインになります。メルニックと、メルニック55夫々の特徴を活かしたブレンドも造られています。
ヴィラ・メルニクは、2020年に「世界のベストワイナリー50」にランクインして国際的に認知。家族経営のワイナリーで、現在の当主のニコラ・ジカタノフは、米国留学経験も持っています。土着品種のメルニックを大切に育てながらも、国際品種も栽培しています。
ドナウ平原とローズヴァレー
緩やかな丘陵地帯と河川が多いドナウ平原でも、赤ワインは、メルロやカベルネ・ソーヴィニョンが中心。ブルゴゾーネ・ワイナリーでは、地場の黒ブドウ品種のガムザも栽培しています。ドナウ川の南岸に位置し、周囲には広大なぶどう畑が広がる素晴らしい景観に恵まれています。一方、貧しい地域で、労働者の確保には苦労があると言います。
ロヴイコ・スヒンドルは、元は協同組合で歴史は20世紀初頭に遡ります。300ヘクタールに及ぶ広大な栽培面積。カベルネ・ソーヴィニョンやシャルドネの他、やはりガムザに注力しています。ハンガリーでも栽培されているガムザは、冷涼な気候を好み、北部ブルガリアで栽培されてきました。軽快で酸に恵まれて、スパイスやハーブの印象。
ローズヴァレーは、ダマスクローズで知られるブルガリア産のローズオイルやローズウォーターでも有名。バルカン山脈に並行して走る、スレドナ・ゴラ山脈の山麓は、日較差に恵まれています。粘土質や石灰岩質、泥灰土などの多様な土壌で、メルロ、カベルネ・ソーヴィニョンやルカツィテリを栽培。
この産地のブティックワイナリーで有名なのは、シャトー・コプサ。先代の当主は、ヴィンプロムの幹部。今では家族経営の、ホテルやレストランを併設した滞在型のリゾートワイナリーです。主に、シャルドネや、ソーヴィニョン・ブランを使った白ワイン、カベルネ・ソーヴィニョン、メルロの赤ワイン、セニエ方式のロゼなどを取り揃えています。

シャトー・コプサ
黒海沿岸
黒海沿岸の、北東部では、ディミャット、マスカット・オットネルやルカツィテリと言った、高品質白ワインが生産されています。
白ワインのディミャットはニュートラル品種。ピノと並んで、現代のブドウ品種の祖先とも言えるグエ・ブランと、モルドバのブドウ品種との自然交配。爽やかな酸に恵まれて、白い花の印象があります。飲み口は軽やかで味わいは爽やかな酸味で優しい余韻。スパークリングワインにも用いられます。
マスカット・オットネルは、ミュスカ・ブラン・ア・プティ・グランやミュスカ・オブ・アレクサンドリアよりは、早熟で香りの華やかさは劣ります。
ディミャットで注目されているのは、小規模な都市型ワイナリーのオデッソス。歴史は浅いのですが、海外で経験を積んだ兄弟が運営し、高い評価を得ています。
一方、黒海沿岸の代表的な大手ワイナリーと言えば、ブラック・シー・ゴールドが挙げられます。650ヘクタールの畑を有する、大手の代表格。20世紀初頭に協同組合として設立されました。
5. ブルガリアワインのまとめ
相当なワイン愛好家や、熟練ソムリエでもなかなか出会うことが少ないブルガリアワイン。今回は、政治体制に翻弄されたブルガリアワインの歴史を掘り下げつつ、光が当たり始めた産地と土着ブドウ品種を勉強しました。
フランス、イタリア、スペインと言った伝統的な産地のワインは、当たりはずれも少ないですが、歴史は古くても、知る人ぞ知るというブルガリア。今、詳しくなっておくと尊敬されること間違いなしです!最近は、ブルガリアワインを出すレストランやショップも見かけます。ぜひ、先ずは1本手に取ってみて、お気に入りの生産者を見つけませんか。