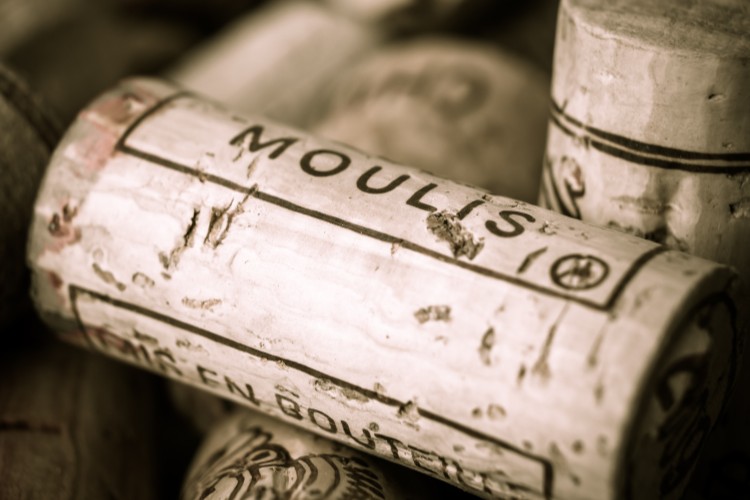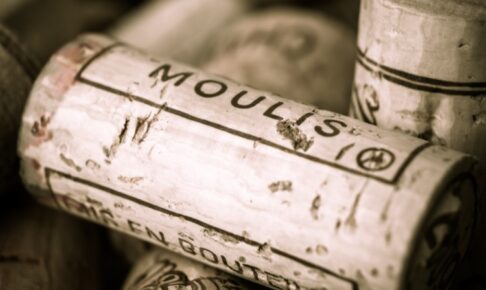ボルドー地方の心臓部であるオー・メドック地区には、6つの村名AOCがあります。ジロンド川沿いに北から南へと並ぶ4つ、サン・テステフ、ポイヤック、サン・ジュリアン、マルゴーの各AOCは、愛好家なら誰もが知るメジャーリーガー。1855年に行なわれた同地方の赤ワイン格付けに選ばれた、1~5級の特級シャトーが多数あるからです。いっぽう、ジロンド川から少し離れ、内陸側(西側)に入ったところにあるふたつの村名AOC、ムーリス(Molis)とリストラック・メドック(Listrac- Médoc)は、あまり知名度がありません。理由は単純で、1855年の格付けシャトーがひとつもないから。とはいえ、それは優れたワインがないのとは違います。多数のコミューン(行政区分上の「村」)で構成される地区名AOCオー・メドックから、ムーリスとリストラック・メドックが単独の村名AOCとして切り出されたのは、際立ったテロワールが認められるからです。実際、AOCムーリスには、「無冠の帝王」とでも呼ぶべき、「格付け外ながら、5級と同等かそれ以上の実力を備えたシャトー」があります。本記事では、そんなムーリスを深掘りしましょう。
【目次】
1. 概要:ムーリス村とAOCムーリス
● 位置と範囲
● コミューンとしてのムーリス・ザン・メドック
● ムーリスのAOC認定
● ムーリスの主要ブドウ品種とスタイル
2. ムーリスのテロワール
● 土壌の特徴
● 気候の特徴
● 土壌とブドウ品種のマッチング
3. なぜムーリスには格付けシャトーがないのか
● 価格差とその原因
● クリュ・ブルジョワ(Crus Bourgeois)
4. ムーリスの代表的シャトー紹介
● シャトー・シャス・スプリーン(Château Chasse-Spleen)
● シャトー・プジョー(Château Poujeaux)
● シャトー・モーカイユ(Château Maucaillou)
5. ムーリスのまとめ
1. 概要:ムーリス村とAOCムーリス
位置と範囲
AOCムーリスが位置するのは、AOCサン・ジュリアンの南西方向、AOCマルゴーの北西方向で、もうひとつの「格付けシャトー無し村名AOC」のリストラック・メドック(Listrac)と、南北に隣り合っています(ムーリスが南側)。北東から南西にかけての方角に、細長く連なる帯状の産地です(長さは約12キロメートル)。行政区分上のコミューン(村)であるムーリス・ザン・メドック(Moulis-en-Médoc)が、AOCムーリスに認定されるエリアの大半を占めますが、周辺のアルサン(Arcins)、カステルノー・ド・メドック(Castelnau-de-Médoc)、ラマルク(Lamarque)、リストラック・メドック(Listrac-Médoc)の各コミューンに位置する一部の区画も、AOCムーリスには含まれています。メドック・エリアにある6つのAOCの中では、ムーリスが最小です。

ムーリス・ザン・メドックと周辺のコミューン
コミューンとしてのムーリス・ザン・メドック
行政区分上の正式なコミューン名は、ムーリス・ザン・メドック(Moulis-en-Médoc)です。ムーリスという地名は、ラテン語の「moles」あるいは「molis」(土塁、石積み、突堤、建物、建造物)に由来します(諸説あり)。ボルドー地方が、ローマ帝国の領土だった頃からブドウが栽培されていて、カベルネ・フランの祖先とされるヴィティス・ビテュリカが、その当時は植わっていたと地元では言われています。その後、中世には穀倉地帯となり、ワイン産地として再発展したのは18世紀になってからです。19世紀末には、1500ヘクタールもの面積があったそうですが、フィロキセラのために大幅減となり、現在はおよそ600ヘクタールほどで落ち着いています(メドック・エリアの約4%、ワインの年産は約400万本)。今日、この集落の人口は2000人ほどで、ワイン生産者の数は約50です(うち7つが協同組合)。名所と呼べる建造物としては、ロマネスク様式のサン・サチュルナン教会があり、その歴史は12世紀までさかのぼります。

ムーリスのサン・サチュルナン教会 ©René Hourdry.jpg
ムーリスのAOC認定
ムーリスが村名AOCとして認定されたのは、1938年で、ジロンド川沿いのサン・テステフ、ポイヤック、サン・ジュリアンの各AOCが認定された1936年から、間もない時期です(マルゴーAOCは、諸事情で1954年になってようやく認定されました)。北隣のAOCリストラック・メドックの認定は1957年で、ムーリスより約20年遅くなります。ムーリスには、1936年にワイン生産者団体が設立されており、それが申請から認可までのプロセスが迅速に進んだ大きな理由です。ラベルに表示可能なAOC名は、ムーリス(Moulis)に加えて、ムーリス・ザン・メドック(Moulis-en-Médoc)も認められています。
ムーリスの主要ブドウ品種とスタイル
生産可能なワインの色は赤のみで、許可品種はカベルネ・ソーヴィニョン、メルロ、カベルネ・フラン、プティ・ヴェルドほか、ボルドー左岸で一般的な顔ぶれです。ブレンド比率としては、カベルネ・ソーヴィニョンとメルロがおおむね同量含められる傾向があります。ボルドーワイン委員会が描写するAOCムーリスの典型的スタイルは、「エレガントだがたくましい姿で、しなやかなタンニンがワインに丸みを与え、愛らしいヴェルヴェットのような口あたりにつながる」です。同委員会はまた、AOCムーリス産ワインの熟成ポテンシャルとして、5~30年という範囲を示しています。この年数は、AOCマルゴー、AOCポイヤックと同じです(AOCサン・テステフ、AOCサン・ジュリアンについては、「5~50年」と、さらに長寿だという見立てになっています)。なお、AOCムーリス域内のブドウ畑から白ワインを生産した場合は、AOCボルドー・ブランとしてしか市場に出せません。ムーリスでは、シャス・スプリーンほかごく少数のシャトーが、少量ながら白を生産しています。

カベルネ・ソーヴィニョンの房 ©Par BerndtF.jpg
2. ムーリスのテロワール
土壌の特徴
ムーリスのブドウ畑は、北東~南西へと細長く伸びる形のなかで、砂利質、粘土石灰質、砂質という三つの土壌が短い距離で切り替わる、モザイク型の構成になっています。おおまかに言って、ジロンド川に距離が近づくほど砂利質の比率が高まり、内陸寄りほど粘土石灰質が多いです。東側にあるグラン・プジョー(Grand-Poujeaux)という台地は、ガロンヌ川によって運ばれた分厚い砂利層が粘土石灰質層を覆う構造で、排水性と保水性のバランスに優れ、ムーリスで最も優れたテロワールだとされます。土壌および微気候の差(次項参照)によって、栽培適性やワインのスタイルが顕著に分かれるのが、ムーリスの多様性の源泉です。砂利質土壌からは、優雅ながらも骨格があって複雑なワインが、粘土石灰質土壌からは、より力強いけれども少々野暮ったいワインが生まれます。
気候の特徴
ムーリスは、メドックのエリア内では内陸に位置しますが、東端はジロンド川から3キロメートルほどの距離で、川の影響を一部受けています。年較差の小さい海洋性気候で、降水は秋から春にかけて多く、7月が比較的乾燥するというのがおおまかな傾向です。内陸側(西側)では夜間の放射冷却がやや強く出やすいですが、砂利が多い東側は砂利が昼間の熱を蓄えるので、ブドウは成熟しやすく、春の霜にもあいにくいです。全体としては、ジロンド川沿いの村名AOCより、若干冷涼になります。そのため、カベルネ・ソーヴィニョンが完熟しやすい、温暖な年に良い結果が出やすいアペラシオンです。なお、ムーリスは、同じ内陸のAOCであるリストラック・メドック(北側に隣接)よりも、少しばかり熟するのが早いとされますが、ヴィンテージの諸条件によってしばしば逆転します。
土壌とブドウ品種のマッチング
先ほど、カベルネ・ソーヴィニョンとメルロが、おおむね同量ブレンドされると述べましたが、土壌タイプによって植え付け品種には差が認められます。砂利質が優位な区画ではカベルネ・ソーヴィニョンの比率が高まり、粘土石灰質ではメルロの比率が高まるのが一般的です。厚い砂利層のグラン・プジョー台地に多くの区画を有するシャトー・プジョーや、シャトー・シャス・スプリーン(Chasse-Spleen)が、カベルネ・ソーヴィニョンを主軸にしているのは、この傾向と一致しています。

グラン・プジョーの台地(砂利質土壌)に植わるブドウ樹 ©Par Berndt Fernow
3. なぜムーリスには格付けシャトーがないのか
価格差とその原因
ムーリスには。1855年に実施された「特級格付け(Grands Crus Classés)」に該当するシャトーはありません。同格付けは、ごくわずかな例外(1973年に起きたシャトー・ムートンの一級昇格など)を除き、実施以来170年間不動です。そのため、19世紀なかばの時点で、秀逸と捉えられていなかったシャトーは入っていません。1855年の格付けを単純化して言えば、当時の市場で高値を付けていたワインを、値段順に並べたリストです。その頃に高価格だったワインはほとんど、ジロンド川に近接したエリアに位置するシャトーから生まれており、内陸部のムーリスにはありませでした。
なぜこの格差が生まれたかは、メドック地区の卓越性の源、砂利質土壌の有無によって説明されます。ムーリスも、東側には砂利質土壌があり、ジロンド川沿いのAOCと大きな条件差はありませんが、西側は粘土石灰質土壌で、メドックの象徴たるカベルネ・ソーヴィニョンにはあまり向きません。東側と西側を足して2で割った平均値にすると、ムーリスは不利だという理屈になります。
ジロンド川沿いのシャトーは、水上交通による輸出がしやすかったという物理的距離の差も、19世紀半ばの名声の差につながりました。川に近いシャトーが、英国への輸出を通じて国際的な知名度と評価を確立していったのに対し、内陸部のコミューンはそううまく事が運びませんでした。知名度が、価格のプレミアに結びつくのは今も昔も同じですから、ムーリスはこの点でも不遇をかこつことになります。
クリュ・ブルジョワ(Crus Bourgeois)
1855年の格付けには入れなかったものの、ムーリスのシャトーはクリュ・ブルジョワ(Crus Bourgeois)の格付け・認証制度と強く結びつき、同制度の中核コミューンのひとつとして重要な役割を果たしてきました。クリュ・ブルジョワについて、「1855年の格付けに漏れた二軍」だと悪くいう人はいますが、玉と石を分けるためのひとつの基準としては有益です。ただし、1932年に導入されて以来、制度の枠組みが何度も変わっており、1855年の格付けと比べ、基準の不安定性が憂慮されてきました(そのため、意図的にこの制度に加わらないシャトーも少なくありません)。2020年の格付けが最新で(次の見直しは2025年の予定)、次の三つの階層、下から上へ「クリュ・ブルジョワ(Cru Bourgeois)」、「クリュ・ブルジョワ・シュペリウール(Cru Bourgeois Supérieur)」、「クリュ・ブルジョワ・エクセプショネル(Cru Bourgeois Exceptionnel)に分かれます。ムーリスにあるのは、全体で180シャトーあるクリュ・ブルジョワのうち5シャトー、56シャトーあるシュペリウールのうち4シャトーです(14シャトーあるエクセプショネルには、ムーリのシャトーは含まれていません)。合計で9シャトーは少なく思われるかもしれませんが、対象のコミューンは全部で80ほどありますから、ムーリスはなかなかの占有率だと言ってよいでしょう。ただし、同AOCのトップ・シャトーであるシャス・スプリーン、プジョー、モーカイユは、いずれもクリュ・ブルジョワの枠組みに参加していません。
4. ムーリスの代表的シャトー紹介
シャトー・シャス・スプリーン(Château Chasse-Spleen)
- クリュ・ブルジョワの格付け: なし
- 所有者: メルロー家
- 畑の面積: 103ヘクタール(黒ブドウ101ヘクタール、白ブドウ2ヘクタール)
- 品種構成: 54%カベルネ・ソーヴィニョン、39%メルロ、5%プティ・ヴェルド、2%カベルネ・フラン/65%セミヨン、35%ソーヴィニョン・ブラン(※2022年時点の数値)
- 生産本数: 50万本 (※2022年時点の数値)
- セカンドワイン: ロラトワール・ド・シャス=スプリーン(L’Oratoire de Chasse-Spleen)
次項のシャトー・プジョーと並び、ムーリスを代表する高品質シャトーです。16世紀にはすでに、この土地でブドウが栽培されていました。1822年に、隣のシャトー・グレシエ・グラン・プジョー(Gressier-Grand-Poujeaux)と分割されたのですが、2003年にシャス・スプリーンがグレシエ・グラン・プジョーを吸収合併し、再びひとつになっています。2023年には、同じく隣接するシャトー・ブリレット(Brillette)から約35ヘクタールの畑を買い取り、AOCで一番の大きさへと成長しました。現在の所有者は、ネゴシアン(ワイン商)のメルロー家で、1976年の買収後に現代化を進め、品質が大幅に向上、トップリーグに入っています。主たる区画は、優れたテロワールで知られるグラン・プジョーの台地にあり、そこから生まれるワインは、しっかりしたタンニンが骨格を形作る、クラシックなスタイルです。1932年に制定された、オリジナルのクリュ・ブルジョワの格付けでは、6シャトーから構成される「エクセプショネル」のひとつでしたが、現在は離脱しています。ムーリスAOCにおける「無冠の帝王」といえば、やはりこのシャス・スプリーンになるでしょう。

ムーリスのサン・サチュルナン教会 ©René Hourdry
シャトー・プジョー(Château Poujeaux)
- クリュ・ブルジョワの格付け: なし
- 所有者: キュヴリエ家
- 畑の面積: 70ヘクタール
- 品種構成: 50%カベルネ・ソーヴィニョン、40%メルロ、5%プティ・ヴェルド、5%カベルネ・フラン
- 生産本数: 30万本
- セカンドワイン: ラ・サル・ド・プジョー(La Salle de Poujeaux)
前項のシャス・スプリーンとともに、ムーリスの「顔」になっているシャトーです。1880年に3つの地所に分割されたのを、1921年にフランソワ・テイユが取得して再統合します。20世紀末には、すでに高い市場の評価を受けていました。2008年、サンテミリオンの一級特級クロ・フルテを保有するキュヴリエ家がプジョーを取得し、辣腕醸造コンサルタントのステファン・ドゥルノンクールを招聘、さらに品質・名声が高まります。ブドウ畑の大半が、グラン・プジョーの台地にひとかたまりになっているのも、高品質の理由のひとつです。ワインはバランスに秀で、厚みのある果実味と、それを後ろから支える力強いタンニンが見られます。力強さのみならず、優雅さが強く表現されている銘柄です。
シャトー・モーカイユ(Château Maucaillou)
- クリュ・ブルジョワの格付け: なし
- 所有者: ドゥルト家
- 畑の面積: 90ヘクタール
- 品種構成: 52%カベルネ・ソーヴィニョン、41%メルロ、7%プティ・ヴェルド
- 生産本数: 55万本
- セカンドワイン: ル・ヌメロ・ドゥ・ド・モーカイユ(Le No 2 de Maucaillou)
プティ・ラロシュ家が設立したシャトーで、壮麗な建物は1875年、当主から妻へのウェディング・ギフトとして築かれました。名前は、「Mauvais Caillou」(悪い石)にちなんだもので、砂利質の畑が、穀物栽培に不向き(しかしブドウには最適)だったからです。1929年以降は、ネゴシアンのドゥルト家が所有してきました。同家の購入時、ブドウ畑は20ヘクタールに満ちませんでしたが、その後の買収によりずいぶん広くなっています。畑はあちこちに散らばっていますが、グラン・プジョーの台地にまとまった面積があり、それが高品質の源です。多数の絵画を所蔵するワイン美術館が、シャトーに併設されています。
5. ムーリスのまとめ
ジロンド川沿いの4村名AOCを除けば、ムーリスのブドウ畑はメドック・エリアにおいて、最も高額で売買されています。つまり、優れたワインが生まれるポテンシャルが大きいのです。1855年の格付けから外れてしまったのは、ムーリスのシャトーにとってはアンラッキーでしたが、21世紀の消費者にとってはラッキーでしかありません。川沿いの格付けシャトーに比べれてコスパ良し、美味しいのに手が届く値段なのですから。近年では、ムーリスのブドウ畑に資金を注入し、名声を手にしようとする外部の投資家も増えていて、アペラシオン全体で品質は上昇傾向にあります。上述したトップ生産者3軒以外にも、シャトー・アントニック(Anthonic)、シャトー・ムーリス(Moulis)、シャトー・ブラナス・グラン・プジョー(Branas Grand Poujeaux)、シャトー・デュプレシス(Duplessis)あたりは注目株です。ムーリスを指して、「貧乏人のポイヤック」とは言いませんが、バーゲンハンターが狙うべき産地なのは間違いありません。単なる廉価版ではない、ムーリス独自の「テロワールの味」もちゃんとあります。大枚をはたかず、本格的なボルドー赤を試したいときは、ぜひ一度ムーリスをお試しあれ。