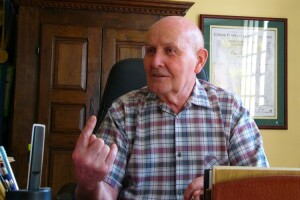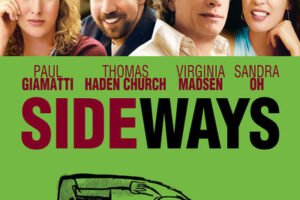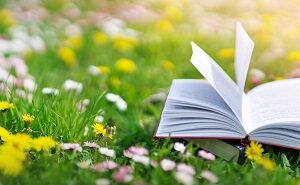ワインは毎年、秋が来れば仕込まれる。偉大と称されるワインは皆、ブドウが摘まれ、酵母の力で酒に変わった年――ヴィンテージをラベルに記している(シャンパーニュなどで一部例外はあるが)。好天続きで、労せずして優品が量産されたような年もあれば、雨、霜、雹、熱波といった天候イベントによって、造り手が唇を噛んだ年もある。ただ、どれひとつとして同じ年はなく、優れたワインはどこの地域の産であれ、ヴィンテージの個性が刻印されている。
本連載では、第二次世界大戦が終わった年から現在に至るまでのヴィンテージを、世相や文化とともに、ひとつずつ解説していく。ワイン産地の解説としては、フランスの二大銘醸地であるボルドー、ブルゴーニュを中心とするが、折にふれて他国、他産地の状況も紹介していく。
本記事では、1953年を取上げよう。世界の政治では、米ソ冷戦が新しいフェーズに入った。科学史に残る大発見がなされた。日本では、水害で多数の死者が出た。ボルドーで、最高の赤ワインが造られた
【目次】
1. 1953年はどんな年だったか?
● 世界の出来事
● 日本の出来事
● カルチャー(本、映画など)
2. 1953年にはどんなワインが造られたか?
● ボルドーワインの1953年ヴィンテージ
● ブルゴーニュワインの1953年ヴィンテージ
● その他の産地
● 伝説のワインは生まれたか
3. 1953年ヴィンテージのまとめ
1. 1953年はどんな年だったか?
世界の出来事
1953年は、第二次世界大戦後の世界を規定してきた冷戦の潮流が、目に見えて変わり始めた年として記憶される。最大の転換点となったのが、ソビエト連邦の最高指導者ヨシフ・スターリンの死と、同年夏の朝鮮戦争の休戦である。
3月5日、スターリンが脳出血の発作により死去した。単に、一国の指導者が死んだのではなかった。巨大な全体主義国家を、恐怖と粛清によって支配し、鉄のカーテンで囲んだ東側諸国を服従させ、戦後世界の分断を象徴していた人物の時代が、終わりを告げたのだ。スターリンの死後から半年間の集団指導体制を経て、ニキータ・フルシチョフが書記長に就任すると、ソ連の外交はこれまでの強硬一本槍から「平和共存」へと舵を切り始める。新たな路線は、1956年のソ連共産党大会で、フルシチョフの「スターリン批判」とともに示されることになるが、萌芽はすでにこの年に見られた。

アメリカ大使館から撮影されたスターリンの葬列
7月27日には、アジアにおける冷戦の最前線であった朝鮮戦争の、休戦協定が板門店で調印された。1950年に勃発したこの戦争においては、ソ連・中国が北朝鮮を、アメリカを中心とする国連軍が韓国を支援するという、米ソ両陣営による代理戦争の構図が顕著であった。3年にわたる激しい戦闘は膨大な犠牲者を生んだが、この休戦によって、少なくとも軍事的な衝突は一段落した。ただし、次の段階である平和条約の締結は実現していないため、北朝鮮と韓国は現在も、国際法上は「交戦中」の状態にある。

朝鮮戦争の休戦協定が調印された、軍事境界線上に位置する板門店(正式名称:軍事停戦委員会板門店共同警備区域)
このふたつの出来事が同時期に起きたため、冷戦の構図は静かに変化していった。核兵器の大量保有を軸とした軍拡のいたちごっこから、より広範な分野での競争へと移行したのだ。経済成長、宇宙開発、イデオロギー対立をめぐるプロパガンダ戦といったフィールドである。一方で、1953年にはソ連が水爆実験に初めて成功しており(アメリカの初実験成功は1952年)、核の競争が止んだわけではなかった。
フランス第四共和政は、依然として植民地独立問題、特に第一次インドシナ戦争(1945-1954)で国力を消耗していた。ベトナム、ラオス、カンボジアといった植民地の独立をめぐる厳しい戦いは、膨大な戦費をフランス国民に負担させ、政局を不安定にしていた。1953年には、ラオスがフランス連合内の枠組みを超えて完全独立を果たしたが、これは第一次インドシナ戦争の終結と、フランスが植民地帝国から脱却していく流れの一部であった。
東西に分断されたドイツは、それぞれ異なるイデオロギーの下で道を歩み始めていた。この年の東ドイツでは、政府が定めた職業別のノルマまで、到達しなかった労働者の賃金がカットされた。この政策がきっかけとなり6月16日、首都東ベルリンの建設労働者による、大規模なストライキと暴動が起きる(東ベルリン暴動)。だが、発生の翌日には、東ドイツ駐留ソ連軍と東ドイツ兵営人民警察によって暴動は鎮圧され、労働者側には多数の死者が出た(当日の衝突による死者と、逮捕・裁判の末に死刑に処された者の両方がいる)。当事件は、東側諸国の民衆が抗議の声をあげた際に、ソ連軍が武力で押さえ付ける先例となった。後年のハンガリー暴動(1956年)、プラハの春(1968年)でも同じような鎮圧がなされている。西側諸国は、これら東側で起きたソ連の強権発動に対し、常に静観の姿勢を取っていた。

暴動鎮圧のために出動した、東ベルリン市内のソ連軍の戦車
冷戦の長期化は、フランコ独裁政権下で孤立していたスペインに、国際社会へ復帰する機会をもたらす。1953年、スペインはアメリカとの間で軍事協定を結んだ。アメリカが、地中海の要衝に位置するスペインの地理的重要性に着目し、ソ連封じ込めのための戦略的拠点を築いたのだ(スペインは当時、NATOへの加盟を認められていなかった)。スペインはアメリカから軍事的・経済的援助を得る代わりに、米軍に海軍・空軍基地を提供することになった。この動きは、スペインによる1955年の国連加盟へとつながっていく。
イギリスでは、前年に即位した女王エリザベス2世(1926-2022)が、ロンドンのウェストミンスター寺院で戴冠式を行なった。英国とコモンウェルスにとって、戦後復興の象徴と言えるイベントだった。
科学の分野ではこの年、その後長きにわたって世界を変える、世紀の大発見が発表されている。科学雑誌『Nature』に、ワトソンとクリックによるDNAの二重らせん構造についての論文が掲載されたのだ。両名は、1962年にノーベル生理学・医学賞を受賞している。

ワトソンとクリックが発見したDNAの二重らせん構造
日本の出来事
国内政治では吉田茂首相が、2月28日に開かれた衆議院予算委員会で「バカヤロー」と発言し、3月14日に衆院が解散されるという前代未聞の事態が発生した(バカヤロー解散)。
一方、第二次大戦で失われた領土の回復では、大きな進展が見られた。1952年の平和条約では米国施政下に残された奄美群島が、この年のクリスマスに日本に返還されたのである。沖縄と小笠原諸島の返還はまだだったが、奄美群島が戻ってきたのは、将来への道筋を見せた一歩だった。
経済面では、1950年に始まった朝鮮戦争による特需が、1953年にピークを迎えたものの、休戦によりその終わりが予見されるようになった。同年7月14日に発表された内閣府の経済白書は、『自立経済達成の諸条件』と題され、特需に依存した経済からの脱却と、自立経済の確立を訴えている。
社会生活では、新たな消費文化の萌芽が見られた。この年、NHKと日本テレビがテレビ本放送を開始する。駅前や商店街に設置された「街頭テレビ」が、人々に新たな大衆娯楽を提供した(当時のテレビ受像機は、高卒初任給の約30か月分に相当する高額品だったため、庶民の手には届かなかった)。特に、翌年に始まった力道山のプロレス中継は絶大な人気を博し、国民は敗戦の鬱屈を晴らすかのように熱狂した。

力道山戦の放送を見ようと街頭テレビに群がる市民(1955年撮影)
東京・青山には日本初のスーパーマーケット、「紀ノ国屋」がオープンした(前身は、1910年開業の果物商)。従前の対面販売中心の小売店から、セルフサービスと大量販売による新たな流通・消費形態への移行の始まりで、暮らしが豊かになっていくステップのひとつと捉えられる。
大雨による大規模災害が、1953年にはふたつ起きている(昭和28年西日本水害)。ひとつめは、北九州を襲った6月の集中豪雨で、河川氾濫により死者・行方不明者が約1000名、浸水家屋45万棟、被災者数約100万人という大災害になった。もうひとつは、和歌山県で7月に発生した集中豪雨で、河川氾濫や土砂崩れなどにより、こちらも甚大な被害が出ている。死者・行方不明者が約1000人、家屋全壊が約3200棟、家屋流出が約4000棟、崖崩れ約4000か所などで、被災者は26万以上に上った。

昭和28年西日本水害の際の福岡県朝倉郡大福村(村落に流木が押し寄せている)
カルチャー(本、映画など)
芥川賞の受賞作は、安岡章太郎の『悪い仲間』、『陰気な愉しみ』だった。安岡は、私小説・短編小説への回帰を図った作家グループ「第三の新人」のひとりで、晩年まで活躍を続けた。直木賞はこの年、上期・下期ともに受賞作なし。1953年の日本におけるベストセラー1位は、角川書店編の『昭和文学全集』だった。第4位には、1949年に原書が刊行されたフェミニズムの聖典、ボーヴォワール著の『第二の性』の翻訳(新潮社)が入っている。
海外文学に目を向けると、1953年にアメリカで一番売れたのは、ロイド・ダグラスによる歴史小説『ザ・ローブ』であった(『パブリッシャーズ・ウィークリー』調べ)。刊行自体は1942年で、当時もベストセラーになったが、1953年に映画化されたために再度小説が売れた。1953年に刊行された他の重要作品としては、レイ・ブラッドベリによるディストピアSFの『華氏451度』、レイモンド・チャンドラーのハードボイルド小説『ロング・グッドバイ』などがある。

『華氏451度』 原書初版本の表紙。冷戦下の思想弾圧に着想を得た、時代を象徴する作品のひとつ
1953年のノーベル文学賞の受賞者は、イギリスの政治家ウィンストン・チャーチルだ。多才なチャーチルは執筆活動も旺盛に行なっており、歴史家としての著作活動、特に第二次世界大戦に関する作品が評価されての受賞になった。
1953年の日本映画界は、キネマ旬報ベストテンの上位に傑作が並んだ。第1位は今井正監督の『にごりえ』で、樋口一葉の短編小説を原作に、明治時代の貧しい庶民の悲哀を深く描いた。第2位は小津安二郎監督の『東京物語』で、老夫婦と子供たちの間のすれ違いから、日本社会で進む核家族化の問題を描き出した。第3位は溝口健二監督の『雨月物語』で、上田秋成、モーパッサンの短編小説を下敷きに、戦乱の中で生きる人々の姿を描いた。小津、溝口の両作品は、現在も海外で極めて高い評価を受け続けており、日本映画界が誇るべきレガシーである。

『雨月物語』のポスター
アメリカ映画の世界はどうだったか。この年のアカデミー作品賞を受けたのは、セシル・B・デミル監督の『地上最大のショウ』である(公開は前年の1952年)。作品賞だけでなく、原案賞も穫った。サーカス一座を舞台にした恋愛・人間ドラマで、豪華キャストにきらびやかな衣装を着せた、派手な作品である。この年はほかに、ジョン・フォード監督の人情喜劇である『静かなる男』(アカデミー監督賞を受賞)や、フレッド・ジンネマン監督の西部劇である『真昼の決闘』といった、今日でも名作とされるハリウッド映画が、作品賞にノミネートされていた。
ヨーロッパの国際映画祭の筆頭であるカンヌでは、アンリ・ジョルジュ・クルーゾー監督の『恐怖の報酬』がグランプリに輝いた。中米を舞台に、火薬の運び屋たちを描いた傑作サスペンスで、批評家筋の評価は今でも高い。ヴェネツィア国際映画祭で最高の作品に贈られる金獅子賞は、この年は受賞作なし。銀獅子賞には6作品が選ばれたが、そのうちのひとつが、上述の『雨月物語』である。ベルリン国際映画祭でも、最高賞である金熊賞は、『恐怖の報酬』に贈られた。
クラシック音楽の世界では、「20世紀最高のソプラノ歌手」と呼ばれたマリア・カラス(1923-1977)が、十八番のひとつであるプッチーニのオペラ『トスカ』を、初めてスタジオで録音した。カラスがトスカをレコードにしたのは生涯で2度で、もう一度は1964~1965年のステレオ録音盤だ。
1953年のビルボード年間チャートで最高位に輝いたのは、作曲家・指揮者のパーシー・フェイスが歌手のフェリシア・サンダースをフューチャリングした『ムーラン・ルージュの歌』。この軽音楽の曲は、映画『赤い風車』の劇中で歌われる主題歌で、歌詞の言語や演奏家・歌手が異なるバージョンがいくつか存在する。
1953年に生を受けた著名人について、手短に紹介しよう。政治の世界では、中華人民共和国最高指導者の習近平、イギリスで首相を務めたトニー・ブレア、民主党代表・外務大臣などを務めた岡田克也など。スポーツ界では、プロ野球選手の真弓明信とウォーレン・クロマティと落合博満、マラソン選手の宗茂・武(双子の兄弟)、サッカー選手・指導者のジーコとアルベルト・ザッケローニ、F1レーサーのナイジェル・マンセルと中嶋悟、大相撲の北の湖敏満、ボクサーのレオン・スピンクス、プロレスラーのハルク・ホーガンと藤波辰爾、国際オリンピック委員会(IOC)代表のトーマス・バッハら。アカデミアでは政治哲学者のマイケル・サンデル、経済学者のポール・クルーグマン、数学者のアンドリュー・ワイルズら。文学界では高村薫、栗本薫、四方田犬彦ら。音楽界ではシンディ・ローパー、マイケル・ボルトン、山下達郎、喜多郞、大貫妙子、甲斐よしひろ、稲垣潤一、テレサ・テン、研ナオコ、小林幸子、円広志ら。俳優では、キム・ベイシンガー、ピアース・ブロスナン、松平健、島田陽子、竹下景子、三田村邦彦ら。漫画家は魔夜峰央、小林よしのり、車田正美らが、それぞれこの年の生まれである。
死没者としては、ソ連共産党書記長のヨシフ・スターリン、民俗学者の折口信夫、アメリカの劇作家ユージン・オニールらがいる。
2. 1953年にはどんなワインが造られたか?
ボルドーワインの1953年ヴィンテージ
1949年以来の大当たり年である。古酒の神様マイケル・ブロードベントの採点は、赤に対する評価が堂々の五つ星満点、甘口白も四つ星と高評価だ。赤は、「全ヴィンテージの中で、もっともお気に入りのひとつ」と、あふれる愛情を隠さない。ボルドーのヴィンテージに関する大著を書いたニール・マーティンは、この年の赤について、濃密なワインが多数生まれた1947とスタイルが似ていると指摘している。対象的にブロードベントは、大柄さよりもフィネスを協調しており、ふたりの見立てを合わせると、「果実味豊富だが、しなやかで優雅な年」という姿が浮かび上がる。もうひとりのボルドーワインのイギリス人専門家ジェーン・アンソンは、1953を「クラシックな年」とした上で、豊満だがバランスのとれた果実味、フィネスがあり、長期熟成もすると記した。マーティンによれば、1953はブロードベントを含むイギリス人識者へのウケが著しく良いため、しばしば「イギリス人向けヴィンテージ」と呼ばれるそうだ。この年のボルドー赤は、左岸、右岸問わずよい出来映えとされるが、最高の評価を受ける銘柄数は、左岸のほうが多い。

前年の12月に大雨が降ったあと、1月からは好天が続いた。やや水不足の環境の中、3月下旬にブドウ樹が芽吹いたあと、4月初旬に恵みの雨が降る。同月中旬には霜の被害が出た。5月の初旬は肌寒かったが、その後気温が上昇したので、最初の開花が23日に観察されている。一部の地域で花震いが見られたものの、収量は多くなりそうな見込みだった。6月の気温は高めで推移し、後半にはかなり雨が降った。7月は適度な暑さで良好に推移したが、AOCマルゴーでは雹の被害が出ている。8月もほどよい気温で、雨が降らなかった。ブドウ樹の水分ストレスを癒やしたのは、9月15日からの激しい雨である。左岸での黒ブドウの摘み取りは9月末に始まり、多くは10月半ばに再びやってきた大雨までに終えられている。発酵が終わって樽に入ったワインは、その時点で果実味が豊富でしなやかだった。そのため、長期熟成に必要な骨格を欠くのではと心配されたが、ありがたくもこれは杞憂に終わった。赤の収量は非常に多く、平年の倍ほどになったシャトーも出ている。ソーテルヌは、10月半ばの大雨で貴腐菌の繁殖が始まったので、遅い収穫のシーズンとなった。
ブルゴーニュワインの1953年ヴィンテージ
前年(1952)は、ボルドーよりもブルゴーニュの品質が勝ったが、1953は逆になった。ただ、この年のブルゴーニュも、決して悪いヴィンテージではない。ブロードベントの評価は、赤白ともに四つ星だ。赤は、若いうちから魅力を放つタイプで、そのぶん寿命が「非常に長い」とはいかなかった。優品は、1970年代半ばから1980年代半ばに、飲み頃のピークに達したようである。白も、瓶詰め当初からバランスがよく、すぐに楽しめるスタイルだった。1950年代後半から1960年代前半が、白のグラン・ヴァンの飲み頃だったようで、今ではもう盛りを過ぎた。とはいえ、「若飲み、(比較的)短命」というのは、赤白ともに一般的な傾向に過ぎず、後述するように例外はある。
冬の終わりは寒く、春になってもそのまま低い気温が続いた。春は雨も多く、シャブリなど標高の低い土地では、霜の被害が出ている。6月も雨模様で、開花・結実はうまく運ばなかった(花震いとミルランダージュが多く生じた)。とはいえ、極端に収量が低かった前年の反動で、1953年はもともとの収量ポテンシャルが高かったため、結実不良が出ても、まだ高い歩留まりが見込めた。6月の雨は、斜面の表土を下方へと押し流してしまったので、人力で、あるいは馬の力を借りて、土を運び上げねばならなかった(当時はまだ、トラクターが普及していなかった)。7月になっても天候は回復せず、相変わらず低い気温と雨が続いた。7月末の時点では、惨めなヴィンテージになるのではという悲観が、ヴィニュロンたちのあいだに立ちこめていたが、8月、9月は好天が続き、気温も十分なところまで上がった。収穫が始まったのは9月末で、おおむね健全でほどよく熟した果実がセラーへ運ばれている。最終的な収量は、平年よりやや多めだった。
その他の産地
ローヌ渓谷は、北部は優良ヴィンテージで(ブロードベント四つ星)、南部はまずまずといったところ(同三つ星)だった。ロワール渓谷も、悪くはないがそうよくもない(同三つ星)。アルザス地方も、同様だった(同三つ星)。シャンパーニュ地方は、優良ヴィンテージ(同四つ星)で、天候には比較的恵まれた。堅い1952年産シャンパーニュと対象的に、若いうちから楽しめるスタイルになったのは、ボルドー、ブルゴーニュと共通している。
ドイツは傑出したヴィンテージで、ブロードベントの五つ星。優れた甘口が多く生まれた。ただ、この時期のドイツで用いられていた天然コルクは、品質に大きなバラツキがあり、長期熟成させたワイン瓶差につながっているらしい。
イタリアは、ドイツとは対照的に厳しい年だった(ブロードベントの星はゼロ)。気温が低く、雨が多く、収穫期になっても天候の回復がなかった。
スペインはどうだったか。当時の中心産地リオハの評価は、総体としてはいまひとつ。10月半ばに降った大雨が原因だが、それまでに収穫を終えていた蔵は、まずまず良いワインを造った。リベラ・デル・ドゥエロ地区においては、当時唯一の銘醸だったベガ・シシリアが、非常に力強い旗艦銘柄ウニコを、この年に生産している。

ベガ・シシリアの旗艦銘柄ウニコのボトル。1980年代に入るまでは、リベラ・デル・ドゥエロ地区における唯一の超高級ワインだった/©Jordi Muray – stock.adobe.com
ポートワインの産地ドウロ渓谷はこの年、ブロードベントの二つ星。酷暑と水不足で、ヴィンテージ宣言できる水準のブドウはほとんど実らなかった。同じポルトガル領の酒精強化の産地、マデイラ島もこの年はふるわなかった。
1953年のカリフォルニア(ナパ)は、まずまず良いヴィンテージだった。ただし、春の遅霜のせいで、収量が非常に低くなった。
伝説のワインは生まれたか
ボルドーの赤には、ブロードベントが五つ星を付けた名品が多数並ぶ。左岸の五大シャトーでは、ラフィット、マルゴー、ムートン、オー・ブリオン。珍しくラトゥールは、この年には真価を発揮できずで四つ星。メドック地区の二級格付けレオヴィル・ラス・カーズ、コス・デストゥルネル、グリュオ・ラローズ、三級格付けのカロン・セギュール、五級のランシュ・バージュ、グラン・ピュイ・ラコスト、グラーヴ地区のラ・ミッション・オー・ブリオンも五つ星をもらった。右岸では、シュヴァル・ブラン、ペトリュス、フィジャック、ヴュー・シャトー・セルタンが五つ星である。甘口白で、ブロードベントが五つ星を付けた銘柄はなかったが、ソーテルヌ地区のイケム、ドワジ・デーヌ、ジレット・クレーム・ド・テット、ルーミューに四つ星を与えた。ニール・マーティンは上記に加えて、赤ではメドック地区の二級格付けデュクリュ・ボーカイユとモンローズ、右岸ポムロール地区のラ・コンセイヤントとレグリーズ・クリネ、甘口白ではソーテルヌ地区のクリマンを、この年の秀逸なワインとして挙げている。
ブロードベントは、1953年産ブルゴーニュ赤のどの銘柄にも、五つ星を付けなかった。四つ星をもらったのは、DRCのラ・ターシュ、エリティエール・ラトゥールのシャンベルタン、ルロワのマジ・シャンベルタン、ルイ・ラトゥールのロマネ・サン・ヴィヴァン・レ・キャトル・ジュルノーの四銘柄だが、ラ・ターシュのみ1998年時点の試飲評価で、あとは1980年代半ばの採点である。アレン・メドウズが、この年に95点以上の得点を与えた赤は、アンリ・ジャイエのヴィーヌ・ロマネ・ボーモン(96点/2016年試飲)、DRCのラ・ターシュ(95点/2008年)、コント・リジェ・ベレール(ルロワ瓶詰め)のラ・ロマネ(95点/2018年試飲)、ルロワのシャンベルタン(95点/2012年試飲)、ブシャール・ペール・エ・フィスのマジ・シャンベルタン(95点/2015年試飲)、白はブシャール・ペール・エ・フィスのモンラッシェ(95点/2004年試飲)。この頃のブシャールは、光輝いていたようだ。のちに長いスランプに入り、1995年にはシャンパーニュッ生産者のアンリオに売却されてしまう(2022年以降は、富豪フランソワ・ピノー率いるアルテミス・グループの傘下)。アンリ・ジャイエの1953ボーモンは、まだほとんど元詰めをしていない時期だから、極めて希少なボトルである。
シャンパーニュで、ブロードベントが五つ星を献上した銘柄はクリュッグのみ、四つ星がヴーヴ・クリコのみだった。作柄評価自体は優良だから、ほかにも素晴らしいヴィンテージ・シャンパーニュはあっただろうと想像される。
1953年産で、ロバート・パーカー自身が100点満点を与えたワインは、シャトー・ラフィット・ロッチルドのみである。
スティーヴン・スパリュアが、『死ぬ前に飲むべき100のワイン』の中に含めた、1953年産のワインはない。
さてここで、1953年のワイン・オブ・ザ・ヴィンテージ、伝説のボトルを選ぶとしよう。この年は、ボルドーはメドック地区の格付け一級、シャトー・ラフィット・ロッチルドを推す声が非常に多い。専門家たちのレヴューには、「伝説的」、「戦後最高のラフィット」といった賞賛が並ぶ。ブロードベントは、「押しが強いわけでも、けばけばしいわけでもなく、この上ないフィネスと魅力を備えたワイン」、「言葉では、その美徳をうまく表現できないから、口をつぐむべき」と評した。2000年時点でブロードベントは、「この年のラフィットを、40回近く試飲してきたが、状態の悪いボトルに当った経験は皆無だった」と述べている。

シャトー・ラフィット・ロッチルドのラベル。クラシックなデザインは、1953年当時から変化していない/©ltyuan – stock.adobe.com
ラフィットが、現オーナーであるロスチャイルド家の手に渡ったのは、1868年である。買取り額は500万フランで、当時としては天文学的な金額だったらしい(現在の貨幣価値に換算すると、50~100億円程度。ただし、今のラフィットが仮に売却されたとすれば、その額はおそらく桁がひとつかふたつ増えるだろう)。購入以来、代々ロスチャイルド男爵家の人間がこのシャトーを管理してきたのだが、例外がある。第二次世界大戦中の1942年から1945年、当時フランスを占領していたドイツの傀儡ヴィシー政権が、ラフィットを収用したのだ。終戦後、シャトーはエリ・ド・ロッチルド男爵のもとに戻り、男爵は戦争中に荒れた畑や建物を修復するとともに、種々の仕事のやり方を改善した。1953は、ラフィットが戦争の傷を癒やし、輝かしい復活を遂げた証のヴィンテージなのである。
3. 1953年ヴィンテージのまとめ
世界の政治状況は、「熱い戦争」から「冷たい戦争」へと完全に移った。ワインの世界では、「熱い戦争」という災害からの復旧が、この年のあたりでようやく済んだように見える。発展途上国での「熱い」代理戦争は起きていたが、主要なワイン産出国は核の傘のもと、戦車やミサイルといった物理的な脅威からは遠ざかった。それでも、悪天候という別の物理的脅威の前では、ヴィニュロンたちはなす術がなかった。1953年、たとえばボルドーでは天候被害が許容範囲内だったから、素晴らしい作柄となったが、翌年にはまた暗転する。「不作年はなくなった」と、ボルドーで語られるようになるのは、まだ40年ほど未来の話である。
【主要参考文献】
『世紀のワイン』 ミッシェル・ドヴァス著(柴田書店、2000)
『ブルゴーニュワイン100年のヴィンテージ 1900-2005』 ジャッキー・リゴー著(白水社、2006)
『ブルゴーニュワイン大全』 ジャスパー・モリス著(白水社、2012)
Jasper Morris, Inside Burgundy 2nd Edition, BB&R Press, 2021
Jane Anson, Inside Bordeaux, BB&R Press, 2020
Stephen Brook, Complete Bordeaux 4th Edition, Mitchell Beazley, 2022
Allen Meadows, Burgundy Vintages A History From 1845, BurghoundBooks, 2018
Michael Broadbent, Vintage Wine, Websters, 2006
Steven Spurrier, 100 Wines to Try before you Die, Deanter, 2010
Robert Parker’s 100-Point Wines, Wine-Searcher